
*JR中野駅徒歩10分* 一般申し込みは6月4日(火)開始となります。 周りのご参加希望の方にぜひお伝えください。 初めての楽しい俳句講座〈午前クラス〉 | 恩田 侑布子 |[公開講座] 早稲田大学エクステンションセンター 初めての楽しい俳句講座〈午後クラス〉 | 恩田 侑布子 |[公開講座] 早稲田大学エクステンションセンター
7月11日(木)〜
恩田侑布子「初めての楽しい俳句講座」開講
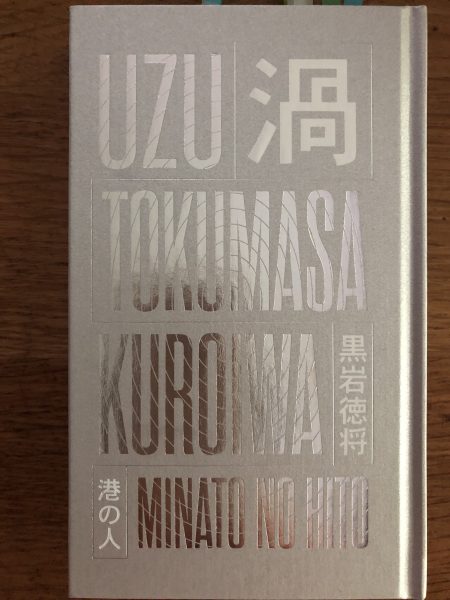
二〇〇六年〜二〇二三年の三三〇句を収録し、十代から青春期を総覧する句集である。物象感の鮮やかさがいい。「白薔薇」はついに一ミリも触れない回転ドアのために際立ち、赤子の尻は「曼珠沙華」の蕊によってこの世のほかの果実めく。「夕桜」の抒情も、「花馬酔木」の惜春も、たしかな物量として感じられる。前職を捨てる実感として「股の下」に収まる「九月の海」以上のものがあるだろうか。いま一つの美点は独自な空間把握にある。「龍の玉」と母の痩せ。「はくれん」と橋下からの呼び声という、無縁のもの同士に透明な橋が架かる。瞠目するのは「渦潮」と哺乳瓶の一句。みどりごの両手に摑まれたことで両者はめくるめくいのちの奔流の渦に巻き込まれ、波飛沫を上げるのである。 (恩田侑布子選評) ↑ クリックすると拡大します
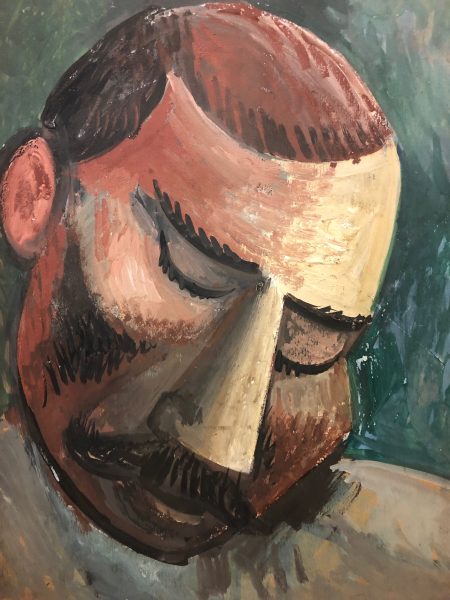
photo by 侑布子 2024年 5月5日 樸句会特選句 春眠や彼の地は鉄の雨ならむ 小松浩 ああ、ぐっすり眠ったなあと甘い眠りから覚めた春の朝。戦地のことが心をよぎる。パレスチナの子が逃げ惑うガザか、三年目も終戦の手立てのないウクライナか。天井のない牢獄に閉じ込められてきた罪もないガザ市民は、昨秋からさらに水も満足に飲めない飢餓にさらされ、学校も病院も砲弾で破壊され、子どもたちまで一三〇〇〇人以上も殺された。原爆の「黒い雨」は井伏鱒二の専売特許だが、「鉄の雨」は戦争のミサイルや砲弾。胸を突き刺す措辞だ。いま「春眠」の許されている日本も、防衛費を突出させる予算に政権が舵を切った。新たな戦前が日本でも始まっている。読み下した瞬時、胸を衝かれる。 (選・鑑賞 恩田侑布子)
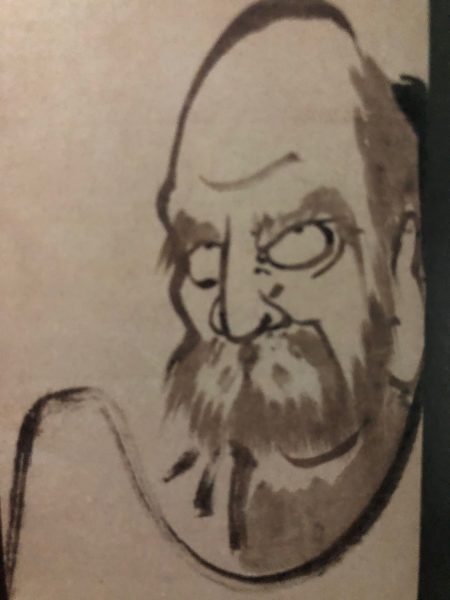
photo by 侑布子 2024年 5月5日 樸句会特選句 ぼうたんや達磨大師の上睨み 古田秀 禅宗の開祖、菩提達磨といえば、一葉の蘆に乗ってインドから中国まで渡ってきた「蘆葉達磨」の画題が有名。日本では雪舟の「慧可断臂図」が国宝。でも、どちらも牡丹の花との取り合わせは見られない。それがこの句の新しみとなっている。「ぼうたんや」と上五で打ち出したことで、大輪の牡丹色が目一杯広がり、そこに一枚の糞掃衣をまとった墨絵の達磨がどっと現れる。しかも強烈な目玉でこちらを睨みかえしてくる。「上睨み」の措辞は鋭い。華やかな牡丹は中国の国花。大陸の風土性をもつ印象鮮やかで力のある俳句だ。 (選・鑑賞 恩田侑布子)
2024年4月7日 樸句会報 【第139号】
4月7日は静岡では丁度桜が満開で、句会も花の下一杯やりながらといきたいところだが、案の定参加者がいつもより少なく残念でした。というのは、俳句は一方的に作るのでなく、作者と鑑賞者が一句独特の魅力です。省略とか余白は、より鑑賞者の自由な解釈ができるためのツールとしてあるのではないでしょうか。今まで句会において何気ない良句が、鑑賞というフィルターを通して、名句へと旅立っていくのを目の当たりにしました。ここに、投句だけでなく、句会に参加すべき意義があるのでないでしょうか。
今回の兼題は「鴉の巣」「古草」「花」です。入選4句を紹介します。
○入選
ファインダー花冷の都市無音なり
古田秀
【恩田侑布子評】
高階からカメラのファインダーを覗くと、「花冷の都市」は思わぬ静まりようです。まるで無人都市のよう。にわかに現実とVRが溶け合い、すべての肌触りが遠ざかります。薄い灰色と桜色の雨もよいの都市そのものが非日常の空間としてデジタル画素の網に浮かび上がるハードボイルドな都会詠です。
○入選
春雨か微睡のなか聴く霧笛
星野光慶
【恩田侑布子評】
「霧笛」なので、大きな港湾の近くの住まいが想像されます。うつらうつらした心地よい「微睡のなか」で、外国船の霧笛が遠く聞こえ、その潤みようから、ああ外は「春雨」が降っているのかなと思います。この上五の「か」の切れ字、よく出ました。しかも自然です。「や」なら平凡な句になったものを、「か」の問いかけの一字が救っています。音楽的にも「か」行の脚韻の効果が、春雨のしっとりしていながら、そこはかとなく明るい春光を句全体ににじませています。
○入選
古草や読み続けゐる文庫本
猪狩みき
【恩田侑布子評】
「古草」の季語の本意を深く自分のものとした実直な俳句です。古草は春になっても野山や空き地に残り、誰にも顧みられなくなりますが、一年前には芽吹きも成長もあり、緑の葉の茂みもありました。花も咲かせました。今は、色の抜けた柔らかなわら色の光を投げかけるばかり。「読み続けゐる文庫本」はきっと古典でしょう。なんべん繙いても、前には気づけなかった角度から新しい泉が湧いてきます。人間の精神の財産は一人ひとりの真摯な感受があって、初めて継承され生かされてゆくのだと、静かに襟を正される思いがする俳句です。
○入選
痛む身の杖の先にも菫かな
都築しづ子
【恩田侑布子評】
「痛む身」をおして、春先の日光を全身に浴びようと、杖で歩かれる前向きの作者です。ふと、「杖の先に」すみれをみつけた瞬間のよろこび。足元からやさしく励まされる春ならではの光景のたしかさ。「杖と作者の身体はもはや一体と化しているようだ」という優れた鑑賞が句会でありました。
【後記】
私は昨年の秋あたりから、意識して選句に力を入れております。動機となったのは、いつも投句の際作った複数句から三句を選ぶのに苦労しているからです。自分の句の優劣も判らぬものが、ひと様の句を批評するなんておこがましいと思ったからです。たまたま恩田代表の「選句に力を注げよ」の檄に乗っかり、これはこれでよかったのですが、判定を代表の選句を正として照らし合わせると、惨たる現状に我ながら呆れかえります。で、他の人も似たかよったかだとの捨て台詞を封印して、「名句を作る近道は選句を磨くにあり」との言葉を信じ、もう少し真剣に取り組もうと思います。また、句作において伸びしろは期待できませんが、鑑賞において、若い方の飛躍の一助になるかも知れないという期待は持っています。
(岸 裕之)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
====================
4月21日 樸俳句会
兼題は「春の雲 」「遠足 」「磯巾着 」です。
特選2句、入選4句を紹介します。
◎ 特選
姉妹してイソギンチャクをつぼまする
猪狩みき
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「磯巾着」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
街棄つるやうに遠足出発す
古田秀
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「遠足」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
遠足のキリンの舌のかく長き
小松浩
【恩田侑布子評】
麒麟は動物園でもひときわ印象的な美しい動物。その舌に魅入られていつまでも見惚れている子ども心が端的に表現されています。キリンというカタカナ表記が童心にふさわしく、その長い灰色の舌への驚きと、食べられて次々消えてゆく葉っぱの不思議さが伝わってきます。童心をつねに養っていないとつくれない俳句です。
○入選
春の雲水子地蔵のまるい頬 ...