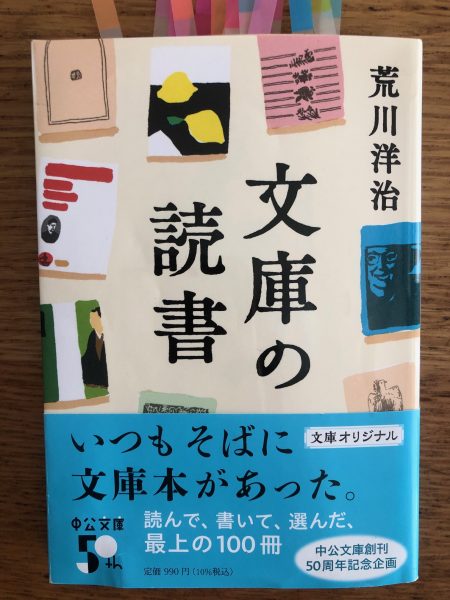2023年6月4日 樸句会特選句
空蟬はゆびきり拳万の記憶 益田隆久 川崎展宏の〈夕焼けて指切りの指のみ残り〉が面影として浮かびます。展宏の句は、滅びてしまった片恋の思い出です。こちらは、一句の構造がもう少し複雑です。たぶん蟬殻を樹肌からそっと引き剥がしたのでしょう。なぜか、痛い、と感じた刹那、作者の初恋は蘇りました。針のように細い足が意外にもしっかりと幹を抱いていたからでしょうか。わたしもあの時、あなたと痛いほどゆびきり拳万を交わしたのです。蟬がすき透る殻を残して大空に飛び立ったように、わたしたちも離れ離れになりました。手のひらの上の軽さを嗤うような、精巧に刻まれた眼、胸、腹、そして足爪。詩的飛躍が素晴らしい、忘れられなくなる俳句です。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年6月4日 樸句会特選句
隠沼こもりぬにあすを誘ふ栗の花 田中泥炭 栗の花がひとけのない忘れられた隠沼へ明日を誘っているとは異様な光景です。明日は、とうぜん、明るい希望に満ちたものではないでしょう。中七の「いざなふ」の濁音がいつまでもざらざらと胸にのこります、いったん嵌まりこんだら、二度と出られないずぶずぶとした泥の沼沢地でしょう。私は即座に、夢幻能の「通小町」の「煩悩の犬となって打たるると離れじ」が胸に甦りました。恋の妄執のはげしさを吐露したこれ以上のものはないという詞章です。一句はさらに隠微に、物狂おしい栗の花の香を燻らせています。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年6月4日 樸句会特選句
人類に忘却の銅羅水海月 田中泥炭 中七に、深い切れのある俳句です。近代の百年は戦争につぐ戦争をし続けた反省のない時代でした。忘れっぽい人類に銅羅が鳴り響きます。それは海の沖に上りたての赤い望月かもしれません。めぐる月日はすべてを忘却の彼方に押しさり流し去ります。埠頭に立つ作者の足下、岸壁の近くへ水海月が押し寄せています。太古からいのちを育んでくれた海には透明な月の光のような水海月が、花のようにひしめき泳いでいます。腹まで透き通る透明で美しい生き物と一緒に、母なる海に身を浸せば、果たして罪深いわたしたち人類にも、なまなまとした記憶が蘇るでしょうか。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)
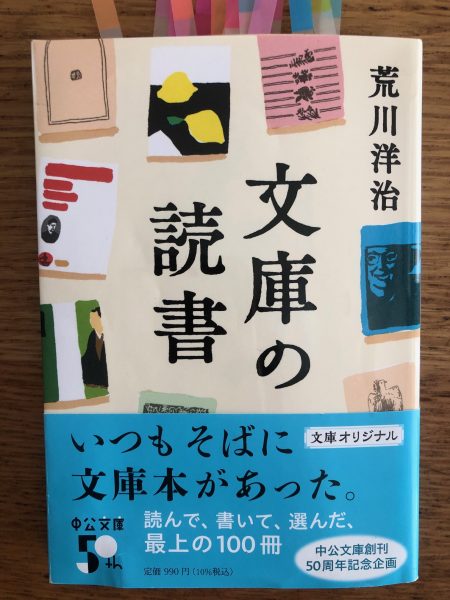
中公文庫創刊50周年記念
荒川洋治『文庫の読書』(900円+税)たちまち増刷。 尊敬する当代一の現代詩作家・荒川洋治さんの30年間の書評を精選した『文庫の読書』100冊の主要62冊に、『久保田万太郎俳句集』(恩田侑布子編・岩波文庫※2021年9月刊行5刷)を入集していただきました。 どれも今すぐ読みたくなる本ばかり。付箋紙で満艦飾になってしまいます。荒川船長を頼りに、七つの海に漂うよろこび。純文学が止まらない。丸谷才一の書評を凌ぐ、たのしくあたたかく立ち止まらせる書評芸術! 恩田侑布子のいまや座右の書、ほんとうに価値ある文庫です。

2023年5月7日 樸句会報 【第128号】 太陽暦5月、[さつき]です。今回から季語が[夏]になりました。歳時記の冊が改まりました。実感としては まだ[夏]には早い感もありましたが、季節感は捉え直すものと思い直しました。
兼題は「立夏」「葉桜」「柏餅」です。特選2句、入選2句、原石賞3句を紹介します。
◎ 特選
父母は茅花流しの向かう岸
活洲みな子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「茅花流し」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
紙兜脱ぎて休戦柏餅
上村正明 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「柏餅」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
初夏やタンクトップにビーズ植う
都築しづ子 【恩田侑布子評】 なんの飾りもないタンクトップに、細やかなビーズの光を添える。一人の手芸の時間を楽しむ作者に、心ときめく夏の日々の予定が想像される。ことに、句末の「植う」は秀逸。たんなるおしゃれさんではない聡明な作者の横顔が目に浮かぶよう。
○入選
葉桜の校庭脇の土俵かな
都築しづ子 【恩田侑布子評】 相撲部のために校庭の隅に「土俵」がこしらえてある。すべすべして白い土俵の土と葉桜の配合がいかにも初夏の涼風を感じさせる。ひとけがなく静まっている土俵というものはいいもの。
【原石賞】真新しちちの墓石に緑さす
前島裕子 【恩田侑布子評・添削】 ついこの間まで肉体があって手に触れられた父が、墓石になってしまった。「真新しい」という句頭に思いが溢れる。おりしも白御影と思われる石に若葉のかげがさしている。墓石になった父が、地中から自分を励ましてくれるようだ。「生きているうちはしっかり前を見て歩きなさいよ」。原句は、「真新し」の終止形で上五に切れが生じ、中七の「ぼせきに」も軽い一呼吸があり、リズムがややたどたどしい。「真新しき」と打ち出したいが字余りになるので、上五は「真新まつさらな」として感動の焦点を絞り、「ぼせき」は「はかいし」とやわらかい調べにしたい。悲しみが言外に伝わるとともに作者の決意が感じられてくる。
【添削例】真新なちちの墓石緑さす
【原石賞】スマホおす付け爪のゆび薄暑光
前島裕子 【恩田侑布子評・添削】 現代の若い女性は爪先に凝る人が多い。ネイルアートや付け爪まで。それをスマホと取り合わせた動きのある光景がいい。ただし、「おす」は鈍い感じ。「すべる」にすれば、上滑りの生の在り方まで暗に感じられ、現代人の表層的な生の哀しみも微かににじむ。
【添削例】スマホすべる付け爪のゆび薄暑光
【原石賞】黒々と命名の「郎」の柏餅
都築しづ子 【恩田侑布子評・添削】 生まれてまず子供に名前をつける。この時の高揚感は生涯忘れられないもの。うやうやしく墨を摺り、真っ白な奉書紙にその名を大きく記す。親になった確かな感慨が迫る。原句はこうしたゆたかな内容に、のんべんだらりとしたリズムがそぐわずもったいない。「黒々と」ではマジックペンもあり得る。墨書であることを打ち出せばさらに格調が生まれよう。
【添削例】命名の「郎」の墨痕柏餅
【後記】
Zoom句会は毎回、参加者の一人か二人に小さな機械トラブルがありますが、「PCを買い替えた」「これを買い足した」とのご報告が相次ぎました。すっかり安定したという報告の方もあり、少しずつ安心しています。句会は、先生から「今回は好句が多かった」とのお言葉で、お点を頂戴した者も嬉しかったことでした。
私事ですが、坂井は東京で務めた新聞の後の地元紙での勤務も期限となり、ほぼ隠棲の身になりました。今後とも一層、よろしくお願いします。 (坂井則之) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) ==================== 5月21日 樸俳句会
兼題は「卯波」「蜥蜴」「新樹」です。
特選1句、入選1句、原石賞4句を紹介します。
◎ 特選
卯波立つ廃炉作業の発電所
猪狩みき 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「卯波」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
碌山の≪女≫漆黒新樹光
岸裕之 【恩田侑布子評】 長野県の碌山記念館は新樹の木立に包まれている。天井のステンドグラスから緑のひかりがさす。安曇野を生地とする夭折の彫刻家、荻原守衛(号・碌山)の代表作にして遺作「女」は、作者自身の、叶うはずもなかった片恋に発した、憧憬と懊悩を体現している。裸婦の漆黒の肌に移ろってやまない初夏の碧いひかりに魅せられる。
【原石賞】囀りに絢爛湧きぬ身内かな
見原万智子 【恩田侑布子評・添削】 「囀り」は春の季語で、五月下旬の句会投句には不適切。とはいえ、発想にめざましい詩がある。自然のなかで春鳥の豊潤な囀りに包まれていると、わが身の裡からも「絢爛」たるものが湧き立ってくるようだ。原句は中七の「湧きぬ」で切れ、囀りと自分の身とが分断されてしまった。句末の切字「かな」もはたらいていない。沸き立つ思いは一挙に書き下ろすべき。
【添削例】囀りに身の絢爛の湧き立ちぬ
【原石賞】寄せ返す頭痛卯の花腐しかな
古田秀 【恩田侑布子評・添削】 新緑は美しいが、神経の繊細なひとにはつらい時期でもある。朝から頭痛が寄せては返す波のよう。卯の花腐しの雨も降っていて、やるせない。暖かくなったとはいえ、足元や首筋は若葉寒である。原句は、「寄せ返す」が、やや辿々しい。「さざなみの」とすれば、「卯の花」の細やかな白い花ともひびき、愛誦性も増しそうだ。
【添削例】さざなみの頭痛卯の花腐しかな
【原石賞】緑蔭に水滴の兎と居れり
益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 山居の新緑の木立に文房四宝の白兎の水滴。美しい光景である。とはいえ、内容は詩、読み下すと散文。句末の「居れり」は取ってつけたよう。つまり、原句は「緑蔭に水滴の兎」。ここまでで見事に完成した短詩、あるいは短律になっている。個人的には短律もいいと思うが、作者が定型の俳句にしたいなら、さらに「水滴の兎」の焦点を絞りたい。
【添削例】緑蔭にみみたて水滴の兎
【原石賞】沖の卯波海道の名はストロベリー
都築しづ子 【恩田侑布子評・添削】 言わんとするところは面白い。原句の「海道の名はストロベリー」は説明っぽいので、いっそ、ひと塊の固有名詞、「ストロベリー海道」にしてしまおう。いちごの赤い色の点在と、白い卯波とが引き立て合い、調べも軽快になる。
【添削例】ストロベリー海道よする卯波かな

2023年5月21日 樸句会特選句
卯波立つ廃炉作業の発電所 猪狩みき メルトダウンを起こした福島原発である。太平洋から打ち寄せる卯波は、事故の前も後も変わらない。海原は無数の白い卯波を立てて夏の到来を告げる。が、陸に目を転じれば、一世代では解決できない廃炉作業が、未来永劫続いてゆく。歳時記では「卯波」の由来を、卯月の波、卯の花の咲く頃の波と説明するが、中国の『説文解字』では「卯」は門を開ける象形とされ、天門の意をもつ。万物が地を冒して出る、茂ることから、「顕現」の含意がある。掲出句は即物的な乾いた措辞が卯波の白さを引き立てる。季語の本意に、新たに、二十一世紀という時代の翳りを付け加え得た俳句である。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

『17音の青春 2023』(角川書店 2023・4・10)が発売されました。
第25回目の全国高校生俳句大賞は例年にも増して秀作揃いです。
夏こそ、31,000句から選ばれた若さのパンチを浴びてください。
ことのほか心打たれた10句をご紹介します。(恩田侑布子) 実るなと掴む乳房や春嵐 旭丘高校3年・渡邉美愛
向日葵の群ゆれてゐる忌中かな 徳山高校2年・大迫悠真
二ページで終わる戦争鰯雲 松山東高校3年・宇都宮駿介
炎帝の弾丸スロー走者刺す 西日本短期大学附属高校3年・早川彰太郎
雲泥が交わる干潟ここにあり 神奈川大学附属高校2年・里見直哉
やはらかき泡ほど苦し髪洗ふ 立教池袋高校2年 辻村幸多
夕凪やズボンをめくる手の血筋 慶應義塾湘南藤沢高校3年・魚池妃夏
竜淵に潜み列車は鉄橋へ 横浜翠嵐高校3年・齋藤妃樂
風船の日ごとに色の濃くなりぬ 興南高校3年・安和音南
文字と文字は塊になる夜焚火に 海城高校3年・尾崎寛太

2023年5月7日 樸句会特選句
父母は茅花流しの向かう岸 活洲みな子 土手や河川敷のそこここに茅花が群生し吹き靡いている。そんな大空の下を歩くと、胸の中の思いも広がってゆく。湿気っぽい南風に空も薄曇り、いつか亡き父母のことを思っている。幼かった日、茅花も卯の花も、名前など何も知らないみどりの野山に親に連れられて遊び呆けたっけ。茅花はほほけて銀色のひかりをすでに白く濁らせている。彼岸に行ってしまった両親との間に水量を増した川が流れている。座五の「向かう岸」を発見したことで、詩的真実が生き物のようにやどった。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。