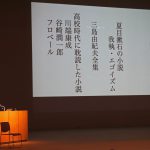令和元年 8月28日 樸句会報【第75号】
8月2回目の句会。夏の終わりの豪雨をついて連衆が集いました。なかには神奈川県から1年半ぶりに馳せ参じた方も。
兼題は、「夜食」と「盆」です。
特選句、入選句及び原石賞のうち2句を紹介します。
◎特選 みな死んでをはる戯曲や夜食喰ふ 山本正幸 登場人物がことごとく死んで終わる戯曲は、ギリシャ悲劇やシェークスピアなど、純文学に多い。人類最古の文学ギルガメシュ叙事詩も、英雄の不死への希求は叶わず、死を以て終る。作者は秋の夜長、重厚な戯曲に引きずり込まれ、こころを騒がせ共感する。はるかまで旅した劇のおわり、主人公のみならず全員が死んでしまった。なぜかいつもは食べない夜食を食べたくなるのである。
するどい感性の句である。理屈上の関係はない「みな死んでをはる戯曲」と「夜食」に、詩のゆたかな橋が架かった。みな死ぬのは戯曲ばかりじゃない。ここにいるものは一人残らず死ぬのだ。死の入れ子ともいうべきマトリョーシカが夜の闇に広がりだす。おれは元気だ。寝腹を肥やそう。熱 々のカップ麺をすすったにちがいない。「喰ふ」という身体性に着地したそこはかとない滑稽がいい。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)
○入選
夜食とるまだ読点の心地して
猪狩みき
やりかけの仕事がまだまだ残っている。でもひとまずここで小休憩をかねた夜食としよう。サンドイッチなどの軽食をつまみながら、こころは落ち着かない。それを「読点の心地」と表現した巧みさ。壮年期のしなやかな働きぶりが伺われる。 (恩田侑布子) 合評では
「作者の自分の仕事への誠実さを感じます」
「勉強なのか仕事なのか、やり残しがある。その中途半端な気持ち悪さが“読点の心地”という措辞に出ている」
「“読点の心地”が素晴らしいと思います。まだまだ仕事が終わらず気がかりだったとき、上司がピザを取ってくれて、軽くササっと食べたことを思い出しました」
「“読点”をどう評価するか。クサいような気も・・・」
「何かが中断されたことのメタファーじゃないんですか?」
など様々な感想・意見が飛び交いました。 (山本正幸)
【原】晩夏光機影ひとつを残しをり
田村千春 【改】晩夏光機影一つを地に残し 原句では、飛行機の機体が晩夏の空中にとどまっているようで、心に浮かんだ幻想にすぎなくなる。ひとつを「一つ」と漢字表記にし、「地」という措辞一字を新たに入れるだけで、機体の影はくっきりと黒く、大地のみならず胸にも刻印される。 (恩田侑布子)
合評では
「夏の終わりのものさびしさがよく出ています」
「ロシアかどこかの軍用機が領空侵犯して飛び去ったとか…」
などの感想が述べられました。
(山本正幸)
【原】荷台より足垂らしてやいざ夜食
島田 淳 【改】荷台より足を垂らしていざ夜食
原句では、中七の「や」の切字と、下五の「いざ」というさそいかけの感動詞とが混線している。トラックの荷台に足を垂らして夜食を摂る働く仲間同士の労働歌なので、「いざ」だけにしてすっきりさせれば、やっと夜食と休憩にありつけたつつましやかな安堵とよろこびがにじむ自然ないい句になる。(恩田侑布子)
投句の合評に入る前に芭蕉の『野ざらし紀行』を少し読みすすめました。
取りあげられた三句と恩田の解説の要点は次のとおりです。
市人(いちびと)よこの笠うらう雪の傘
客気(かっき)の句。昂揚感があらわれている。風狂精神あり。
馬をさへながむる雪の旦(あした)かな
古典の中でうまれたのではなく、眼前の句。茶色の馬体と雪の朝とが釣りあっている。省略がよく効いており、暗誦性に富む。
海くれて鴨の聲ほのかに白し
余白に富んだ名句。波間から鴨の声が聞こえてくる。「ほのかに白し」にいのちのほの白さが宿る。芭蕉の中の「白」のイメージには清浄たるものへの憧れがある。「淡いかなしみの安堵感」と捉えた高橋庄次説も紹介して、連衆それぞれの感受を問うた。聴覚(声)が視覚(白)として捉えられているところに時代を超えた新しみがある。(「共感覚」に関するテキストとして中村雄二郎『共通感覚論』(岩波現代文庫)が恩田から紹介されました)
合評・講評の後は、最近出版された
行方克巳句集『晩緑』(2019年8月)
から恩田が抽出した句を鑑賞しました。
連衆の共感を集めたのは次の句です。
冬空のその一碧を嵌め殺す 地下モールにも木枯の出入口 尋ね当てたれば障子を貼つてをる 雪螢しんそこ好きになればいい
行方克巳『晩緑』のページへ
[後記]
本日の特選句について、「西鶴の女みな死ぬ夜の秋」(長谷川かな女)の等類ではないかとの指摘がありました。恩田は、「かな女の句は浮世草子のなかの女の人生に終始しますが、正幸さんの句は、最後に自身の身体性に引きつけて終るのがいいです。詠まれている世界が異なるので、類句とは言えないでしょう」とこれを退けましたが、講師の評価に対しても疑義を呈し、闊達に議論できる樸俳句会の自由さ、風通しの良さをあらためて実感した次第です。
筆者としてはかな女の句をそもそも知らなかったおのれの不勉強が身に沁みましたが・・。
次回の兼題は「月」「爽やか」です。 (山本正幸) 今回は、特選1句、入選1句、原石3句、△2句、 ゝシルシ4句、・8句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

令和元年 8月4日 樸句会報【第74号】 猛暑日が続く八月最初の句会。暑さのためか欠席者がいつもより多くちょっとさびしい句会になるかと思いましたが、始まれば熱のある楽しい句会となりました。
兼題は、「夕焼」と「祭」です。 今回は原石賞1句と△2句を紹介します。
【原】はらつぱに忘れものあり夕焼かな
田村千春
【改】はらつぱに忘れものある夕焼かな
「はらつぱ」というなつかしい措辞は、万人の胸に郷愁を呼び起こす。そこに少女は大事なものを忘れて来てしまった。石けり遊びでいつも使うお気に入りの石だったかもしれない。人にはどうでもいいものだが、自分にはかけがえのないものが大人になった今もある。それは少女の日の忘れもののように、胸の底に夕焼けと一緒に住んでいる。 遠い街でふと夕焼を見上げても、その下でいまも自分を待っているような気がして胸がうずく。 この句の忘れものは、昔と今とがダブルイメージになっているところがいい。作者の永遠の忘れものなのだろう。
俳句初心者の作者は、切字「かな」の使い方に通じず、中七を「あり」と終止形で切ってしまい、「忘れ物」と「夕焼」がばらばらになってしまった。
連体形の「ある」にすればすべて解決する。 句頭の「はらっぱ」から「夕焼」まで一気につながり、句末の「かな」で、そこまでに撓められた圧力が一挙に放出され、夕焼けが大きく広がってくれる。 (恩田侑布子)
合評では「一日の終わりの夕焼けのもつかなしみと”忘れもの”が重なる」「逆に、“忘れもの”と “夕焼”のさみしさが即き過ぎのような気もします」「ぽつんと残っているものの感じが書けている」などの感想がありました。 (猪狩みき)
切字「かな」を使った芝不器男の名句が恩田から紹介されました。
この奥に暮るゝ峡ある柳かな 芝不器男 南風の蟻吹きこぼす畳かな 芝不器男 あなたなる夜雨の葛のあなたかな 芝不器男
△ 小遣ひを残して帰る祭の夜
島田 淳
子供のころ、お祭の日は親から特別なお小遣いがもらえた。チャックのお財布を握りしめて、参道の夜店や神社の境内を見て歩く。でもこの子はあれもこれもとすぐ使ったりしない。「もったいない。あとは貯金しよう」と決めて、暗くなった夜道を帰っていく。誰にもある子ども時代のさりげない体験を掬い取ったよさ。いじらしく思慮深い子どもは、その後どんな人生を歩いていくのだろう。「祭かな」だと他人事めいてしまうが、「祭りの夜」としたことで実感がこもった。 (恩田侑布子)
本日の最高点句でした。「よくある光景だが、その光景を句としてよくすくいあげている」「こども時代を思い出した。こどもの気持ちがよく出ている」「帰り道の暗さ、心細さが感じられました」という評でした。 (猪狩みき)
△ 外れなき籤引き待つや氷水
芹沢雄太郎 かき氷をガリガリ手動で掻いてくれるおばさんのいる店。狭い店内で、子どもどうしぎゅうぎゅう坐って、氷いちごや、氷レモンを食べる。赤や黃に染まった口でふざけあう。今日はおまけのくじ付きだ。何か当たるよ。飴かもしれないけど、車のおもちゃかもしれない。楽しみ。氷水のチープさが横丁に住みなすよろこびと合っている。「外れなき」の句頭が心地よい。(恩田侑布子) 合評でも、「こどものわくわく感」「こどもの喜び、うれしい感じ」「ハズレがないんだ!という安心感」がよくあらわされているという意見が多くでていました。 (猪狩みき)
今回の兼題の例句として恩田が板書したものは以下の句です。 夕焼て指切りの指のみ残り 川崎展宏
夕焼の金をまつげにつけてゆく 富沢赤黄男
夕焼のほかは背負はず猿田彦 恩田侑布子
肉塊に沈没もする神輿あり 阿波野青畝
神田川祭の中をながれけり 久保田万太郎
祭笛吹くとき男佳かりける 橋本多佳子
老杉の根方灯ともす祭かな 恩田侑布子
合評の後は、中嶋鬼谷、行方克巳、小川軽舟 各氏の最近の句集から抄出した36句(12句×3)を読みました。三人の句風の違いから、自分たちは俳句で何を書くのか、書きたいと思っているのかという話題になりました。
連衆の点を多く集めたのは次の句でした。 西行忌花と死の文字相似たり 中嶋鬼谷
都鳥水の火宅もありぬべし 行方克巳
雪降るや雪降る前のこと古し 小川軽舟
[後記]
原石賞句の鑑賞で、恩田先生が切れ字「かな」について書いています。切れ字によって句のリズムや間、言葉の圧が変わっていくことがわかります。「切れ字の役割」というような学習をするだけでなく(この学習も足りないのですが)、実際に使って作句すること、良い句を多く読んで感覚を得ることが大切であることがわかりました。
次回の兼題は「盆」「夜食」です。 (猪狩みき)
今回は、 特選、 入選ともなく、 原石賞2句、 △3句、ゝシルシ3句、・7句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
なお、7月7日と7月24日の句会報は、特選、入選、原石賞がなくお休みしました。

令和元年 6月2日 樸句会報【第72号】 6月最初の句会。
兼題は、「五月・皐月」と「“手”という字を使って」です。
特選2句、△2句、ゝシルシ3句を紹介します。
◎特選
メーデーや白髪禿頭鬨の声
島田 淳
日本の労働者は正規社員と非正規社員に分断され、メーデーにもかつての勢いはない。その退潮ぎみの令和元年のメーデーを内側から捉えた歴史の証人たる俳句である。「見渡せば、しらが頭にハゲ頭、もう闘いの似合う若さじゃねえよ」という自嘲めいた諧謔が効いている。それを、「鬨の声」という鎌倉時代以来の戦乱の世の措辞で締めたところがニクイ。一句はたんなるヤワな俳味で終わらなくなった。「オオッー!!」と拳を振り上げる声、団結の高揚感は、労働者の生活と権利を自分たちで守り抜くのだ、という真率の息吹になった。ハゲオヤジの横顔に、古武士の面影がにわかに重なってくるのである。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)
◎特選
さつき雨猿の掌光る屋久の森
林 彰
季語を本題の「五月雨(さみだれ)」にするか、傍題の「さつき雨」にするかで迷われたのではないか。最終的に林彰さんの言語感覚が「さつき雨」を選びとったことに敬服する。
〈五月雨や猿の掌光る屋久の森〉だったら、この句は定式化し、気がぬけた。調べの上でも鮮度の上でも天地の差がある。さつき雨としたことで、五月雨にはない日の光と雨筋が臨場感ゆたかに混じり合うのである。猿の、そこだけ毛の生えていないぬめっとした手のひらが、屋久島の茂り枝を背後からとび移って消えた。瞬間の原生林の匂いまで、ムッと迫って来る。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)
△ 一舟のごとき焙炉や新茶揉む
村松なつを
合評では
「“一舟のごとき”がうまいですね。香りが立ちあがってきます」
「焙炉の中で新茶を揉んでいる手が見えてくるようだ」との感想がありました。
「“一舟のごとき”に孤独感を感じます。手揉み茶の保存会があって、年配者を中心に頑張ってくださっていますね。若い世代が継承してくれるといいですね」と恩田が述べました。
△ 地を進むやうに蜥蜴の落ちにけり
芹沢雄太郎
恩田だけが採り、
「蜥蜴は敏捷なのに崖か塀の上から落ちてしまったという面白い句です。斬新でこれまで見たことがありません」と評しました。
ゝ 麦笛や土の男を荼毘に付す
松井誠司
本日の最高点句でした。
恩田は、
「“荼毘に付す”まで言ってしまわず、“付す”を取ってもうひとつ表現するといい。また“土の男”がどこまで普遍性を持つかが少し疑問」と講評しました。
ゝ 酔ざめの水ごくごくと五月富士
萩倉 誠 「静岡人の二日酔いの句ですか?」と県外からの参加者の声。
「夏のくっきりとした富士との取り合わせが面白い。ただし、水は“ごくごくと”飲むものなので、作者ならではのオノマトペになるとさらにいい句になるのでは?」と恩田が評しました。
ゝ 病む人にこの囀りを届けたし
樋口千鶴子
「病気で臥せっている人を元気づけたいという作者のやさしさを感じました」との共感の声がありました。
恩田も「素直でやさしい千鶴子さんならではの良さが出ています。病院のベッドは無機的ですものね」と評しました。
今回の兼題の例句が恩田によって板書されました。
古寺に狐狸の噂や五月雨 江戸川乱歩
彼の岸も斯くの如きか五月闇 相生垣瓜人
やはらかきものはくちびる五月闇 日野草城
手花火に妹がかひなの照らさるる 山口誓子
手品師の指いきいきと地下の街 西東三鬼
手花火の柳が好きでそれつきり 恩田侑布子
生きて死ぬ素手素足なり雲の峰 恩田侑布子
歳月やここに捺されし守宮の手 恩田侑布子
樸俳句会の幹事を長年務めてくださっていた久保田利昭さんが、本日をもって勇退されることになり、恩田から感謝を込めて、これまでの久保田さんの代表句73句(◎と〇)が配布されました。
そのなかで特に連衆の熱い共感を呼んだのは次の句です。 母のごとでんと座したり鏡餅 オンザロック揺らしほのかに涼を嗅ぐ 父の日や花もなければ風もなき 音沙汰の無き子に新茶送りけり 青田風新幹線の断ち切りぬ
久保田さんの今後のますますのご健勝をお祈りいたします。
[後記]
句会の前に、連衆のひとりから自家製の新茶を頂きました。川根(静岡県の中部、大井川沿の茶所)のお茶とのことです。帰宅後、賞味させていただきました。
本日の句会では、特選二句にはほとんど連衆の点が入らず、恩田の選と重なりませんでした。最高点句を恩田はシルシで採りました。連衆の選句眼が問われます。「選といふことは一つの創作であると思ふ」という虚子の言葉を噛みしめたいと思います。
次回の兼題は「青蛙・雨蛙」「薔薇」です。(山本正幸)
今回は、特選2句、△2句、ゝシルシ9句、・10句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

令和元年 6月26日 樸句会報【第73号】 いかにも梅雨の季節という日に句会がありました。 兼題は「青蛙、雨蛙」と「薔薇」。
◎特選2句、○入選1句を紹介します。
◎特選
薔薇園の眼下海抜ゼロの町
天野智美
近景の薔薇園と、眼下に広がる海抜ゼロメートルの町並みの対比が衝撃的である。
赤やピンクの薔薇の中を歩けば王侯貴族の気分を味わえる。ましてや花園は空中庭園と言ってもいいほど、遮るもののない海に突き出た山鼻にある。真っ青な空と海と、あでやかに感覚を蕩かす薔薇の色と匂いと。しかし、遠い海ではない中景の足下には、マッチ箱のような屋根が陽光を反射し無数にひしめいている。防潮堤一枚に囲われ、海と同じ平面に張り付いた町並み。ひとたび、地震による津波が起これば阿鼻叫喚の地獄になる。妖しい美しさと恐怖の危険とが隣り合っている。それは、この薔薇園に限らない。わたしたち二十一世紀日本の普遍的な現実の姿なのだ。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)
◎特選
金山やつるはし跡の青蛙
海野二美
静岡県では梅ヶ島と土肥が、全国では佐渡金山が有名である。どこも金山といえば、金堀人夫たちが命がけで坑道に取り組んでいた。その昔のつるはしの跡に乗っかって、青蛙が可愛い顔をしてこっちを見ている。四〇〇年前の採掘当時も青蛙が同じようにケロリとやってきたことだろう。無宿人の地獄のような一生の一方で、ゴールドラッシュに沸き返るお大尽もいたに違いない。人間の欲と苦労の営 々たる歴史を何も知らない青蛙のかわいさが印象的だ。洗い立てたような青蛙の眼が、逆に人間の営みを浮かび上がらせる射程距離は大きい。平易な措辞によるさりげない俳句の裏には、作者の長年にわたる修練の裏付けがある。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)
◯入選
引きこもる窓に一匹青蛙
林 彰
引きこもるそのひとの窓に一匹の青蛙が貼り付いている。
「大丈夫かい。ぼくのいるところまで出ておいでよ」というように。梅雨時の雨が、ときどき降って、窓に雨滴が溜まっている。
物音もしない。なかに人がいるとは思えない静けさ。でもぼくは知っている。そのひとはそのなかに暮らしている。
80-50問題がマスコミでさわがれる。ひきこもりはいまや少青年のみならず全世代の問題だ。時事俳句といえなくはないが、そういいたくない静謐さは、作者のやさしさがそのまま青蛙に乗り移っているから。(恩田侑布子) 今回の最高点句のひとつでした。(もう一句は特選の“薔薇園の”句)
合評では、青蛙のやさしさ、かわいらしさに言及した評が多くありました。また、この句が、部屋の内側から見て書いている句か部屋の外から見ての句かの議論がありました。「内側から詠んだ句と読むと短歌的叙情句となり、つらさが出過ぎる。外から見た方が世界が広がる。俳句的には、‟距離‟がある方が良いので、外から見ている句と読みたい」と恩田が評しました。(猪狩みき)
合評の後は、『文芸春秋』(7月号)、『現代俳句』(6月号)に載った俳句を鑑賞しました。
息継ぎのなき狂鶯となりゆくも 恩田侑布子 教会の鐘に目覚めて風五月 片山由美子 水無月の底なる父の手を摑む 水野真由美
などが連衆に人気。 「写生、即物具象での作句が絶対と考える作家もいれば、象徴詩として俳句をとらえ、隠喩を大事にしている作家もいる。‟どの考え、方法でなければいけない‟とは私は考えていない。それぞれが自分の足場から水準の高い俳句を作ってくれればよい」と恩田が述べました。
[後記]
鑑賞の中で、「詠んでいるものとの距離」が話題になりました。短歌との違い、俳句らしさはその距離にあるということだったと思います。また、ある句について「平易だけれど射程が深い句」と恩田先生が表現していたのが印象的でした。「俳句」の表現についていつも以上に考えさせられた回でした。
次回兼題は、「夏の朝」と「雷」です。(猪狩みき)
今回は、特選2句、入選1句、△3句、ゝシルシ4句、・シルシ 7句でした。欠席投句者の入選が多かった会になりました。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
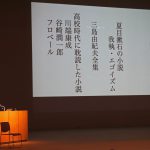
講演「あなたの橋を架けよう」に対して、もったいないほどの感想をあまたの高校生からお寄せいただきました。頼もしいみなさまと出会えて幸せです。深く感謝し、ほんの一部を紹介させていただきます。
これから80年余を生きてゆかれる若いみなさまの真摯な声に、力尽きるまで私もお応えしていきたいです。
こころ痛ましめることがあろうと、新たなステージへ転依(てんね)し、志を持して、大いなる前途を拓いてゆかれますよう、応援しています。
恩田侑布子
教育講演会についての生徒アンケートが寄せられました。その中の12人の方の感想を下記に紹介します。恩田のメッセージが、若いしなやかな感性によって確かに深く受けとめられたことが分かります。 ◯今回の講演は驚きが大きかったです。俳句の表現の深さや、知性と感性、想像力の重要さをよく知ることができました。特に『落葉踏んで人道念を全うす』の奥深さ、味わい深さは驚きでした。先生の講演で、俳句の最も面白いところを教えていただいたと思います。特に衝撃だったのは、俳句朗読パフォーマンスです。最初は静かに朗読するものと思っていたのですが、フランス語や、全身を使った表現に度肝を抜かれました。おそらくあの会場にいたほとんどの人がそうだったと思います。新しいものを感じ、非常に素敵でした。(1年・男) ◯自分が絶望的になっていても文学になんとか頼って生きる希望を得たということは、私にはわかることができない。死にたいと思ったことがないからである。でも、そのような状況の人間をも救い、私のように幸せな人間の生活をさらに豊かにしてくれる文学は本当に素晴らしく、人類にとって偉大なものであるということは、今更ながら知ることができた。
今回の講演でいちばん心に残ったのは「未知の地平を拓く」という言葉である。私は「読む」ことで、自分の世界を広げ、世の中を支えられる人材になってほしいと、恩田さんに託された気がした。時間がたつのは止められないけれど、今、自分にできること、やるべきことを怠らず、一生懸命に努めたい。そして、自分の世界のみならず、誰かの世界をも広げられるような人間になりたい。(1年・女) ◯私は、恩田さんがはじめに説明してくださった、「会へば兄弟ひぐらしの声林立す」という句が、1番印象に残っています。兄弟の部分をはらからと読む理由が、とても奥深くてびっくりしました。実際にひぐらしの声を、恩田さんは体感していたから、とても感動されたんだなと思いました。また、この句を読んで、私もひぐらしの声を肌で感じてみたいと思いました。恩田さんは、今の私には想像できないような高校生活を送っていたことにおどろきました。先が見えない生活をしていたからこそ、俳句のすばらしさに気づくことができたのではないかと思います。今、スマートフォンでのSNS、とくにLINEでの会話がどんどん増えてきていて、俳句のような、日本古来の日本語の美しさに触れる機会が大幅に減っています。私には、この講演会がすごく新鮮なものに感じました。これを良い機会に、俳句や古文などに興味を持ち、昔の日本に触れられたらいいなと思います。ありがとうございました。(1年・女) ◯ぼくが今回の講演会で印象に残ったものは三つあります。
一つ目は、恩田さんの豊かな経験の話です。ひぐらしの句も、鳴き声をたくさん聞いたことのある恩田さんだからこその解釈が面白かったです。
二つ目は、仏教の話です。依りどころを変えてこころを磨く転依という言葉が印象に残り、自分たちとも重なる話が多く、心に残りました。
三つ目は、俳句の朗読です。「三つ編みの髪の根つよし原爆忌」では、床に伏せて悲しみを表現していたのが心に残っています。「三千大千世界」を、仏教用語で「みちおほち」と読んだり、俳句をフランス語で読んだりしていたので、後から「言語によって体の動き方も変わる」という話を聞き、納得しました。俳句は日本語だけでなく、いろいろな楽しみ方もあるのかと思いました。
恩田さんの解釈に納得し、今までよりも俳句に興味がわきました。(1年・男) ◯講演会で一番印象に残ったことは特に2つあります。1つ目は自分の人生を支えてくれるような古典に出会い、耕し読解するということです。私は古典をただの教材としてしか読んだことがありません。しかし恩田さんの話から確かに古典の一つ一つには死者の魂が詰まっていて人生の岐路に立ったときに参考となるものが多く学ぶことができると思いました。私も本が好きなので視点を変えて挑戦してみたいです。2つ目は生身の人間と出会って刺激を受けるということです。今はどこにいてもスマホを持っていれば顔を見たことがない人とさえ会話ができますが、やはり直接会ったほうがより良い刺激を吸収し、自分を成長させてくれると思います。だから積極的に男女問わず様々な人と関わっていきたいです。そして恩田さんが俳句で日本と世界の架け橋になられたように将来誰かのため、何かのための架け橋になるような人間になりたいです。(2年・女) ◯「俳句には共同体に根付く季語が不可欠でいつも背後には自然が存在している。自然は近代的な自我を超えたものであり、作者は感情を季物に託し広やかなものに自我を解放する。今までのものの見方、感じ方の枠を破ることを氏は破行句と呼んでいる。読者は切れの余白の中で作者のいのちと出会う。」と言う考え方は今までであったことがなく、面白いと思った。また、耕し読解…現実社会を能動的に読むという読解方法…を実践して「クリエイティビティーの土台となり心身まるごとの価値観を新たに想像」していきたい。(2年・男) ◯今回、恩田侑布子さんの講演を聞いて、当たり前にあると思っているものを、当たり前と見ず、違う視点で見ることが大切だと思った。恩田さんは、俳句を作る時に身の回りのものを違った視点で見ることで素敵な一句を作り出している。また、配られた紙に載っていた恩田さんが高校1年生の時に書いた卬高新聞にも心が惹かれた。恩田さんの高校時代はまだ家庭科は女子だけというのが当たり前だったのに対して、それを当たり前と思わず、自分の意見をはっきり述べていて、読んでいてすごく共感できる内容だった。また、俳句朗読パフォーマンスでは、それぞれの俳句に合わせて読み方を変えていて表現の仕方によって同じ人が作った俳句でも雰囲気が全く違ってしまうので驚いた。特にフランス語で朗読した時は、日本語のおしとやかな感じと違い、かなり感情的にできることも知った。私は俳句を作ることはあまり得意ではないが、今回の講演で学んだことは普段の生活でも他のことにも当てはまることだと思うので、心に留めておきたい。楽しく有意義な講演だった。(2年・女) ◯先生が何度も仰っていた「耕し読解」という言葉が印象に残りました。仏教のこともあまり知らなかったので、考え方を教えていただけて、とてもよい機会でした。また、何より印象に残ったのは、オウム真理教の中川死刑囚の詠んだという俳句です。人としての感情を失わないまま死刑に処せられたのだと思うと、やりきれない気持ちになりました。
先生の半生を聞いて、子どもの頃の経験がそのまま詩作に生きているのだなと思いました。壮絶な子ども時代を経て、ここ静高にいる間も思い悩み、色々なものに触れた経験が人生を豊かにしているのだろうと思いました。
俳句パフォーマンスも初めて見たので、圧倒されました。貴重な経験になりました。(2年・女) ◯その少女のような声とは似合わない深い言葉は、私の心に深く深く響いた。きっといろいろな困難を乗り越えてきたからこそ心にひびくのだと思った。私も日常生活で使う言葉に影響力を持てるような人間になりたいと思ったし、そのために一日一日を大切に使っていきたいと思った。最後の俳句パフォーマンスも迫力がすごく、とても楽しい時間をすごすことができました(3年・女) ◯(前半略) 今まで「読む」ことについて特に何も考えていなかったけれども、もっと能動的に「読む」という行為をしていきたいと思った。ただ読んでインプットするだけでは確かにAIと何も変わらない。僕は人間なので人間らしく読んで考え発信していくことを意識していきたい。AI に負けないよう、機械にならないようにする。さすが俳人。話し方がきれいだった。「音」にこだわった話し方をしていると感じた。僕も心ひかれるものにはどっぷりとつかろうと思う。(3年・男) ◯仏教の話が一番心に残った。すべてのものは実体がない「空」である、苦悩は嘆くものではないのだ、とうことなどは、現代の生き方、考え方と大きく関わってくるものであると感じた。そして「読む」行為。それは必ずしも字などで示してあるものを対象とはしない。この世界について、様々な抱えている問題について、さらには宇宙の真理なんかも含まれるだろうか。どうしてそうなっているのか、なぜなのか、…。それを読み解いて行き、皆に共有し、よりよい生活を送れるようにする、「耕し読解」をしていくことが大切だという。(中略)今後の社会においては、特にこの「原始仏典」の方の考え方が、生きていくカギとなってきそうである(3年・男) ◯自らの経験から仏教なども絡めた「思想」「生き方」の話をしてくださった。「たがやし読解」という言葉にすごく感銘を受けた。文学に向き合う姿勢は理系の人間だとしてもないがしろにしてはいけないし、先人から多くのことを学びとっていくべきだと感じた。全体を通して、高校生を引きつけるための話し方をすごく意識されているなと感じた。高校生がかかえがちな悩みを共有してくださり、自分としても話に聞き入ってしまった。内容については、仏教観を人生の柱としながら、先生自身の教訓も赤裸々に語ってくださり、あまりそういった話をじっくりと聞くこともなく、宗教を遠いものと感じていた私には衝撃だった。 宗教の主体は神ではなく、そこに救いを求める人間なのだということを改めて感じた。最後の朗読パフォーマンスについても非常に鮮烈で、俳句というのは座っておごそかな気持ちで詠むものだという先入観を見事に打ち破るもので、非常に感動した。 海外で活動なさっているというのもあって、日本人の感覚にとらわれない広い視野や感覚と語り草にすごく刺戟を受けたし、自分も古典にもっと真剣に向き合って見識を広げていきたいと思った。(3年・男)

2019年4月2日より、読売新聞「たしなみ」に恩田侑布子のエッセーが掲載されています。火曜日夕刊に4週毎の1年間連載予定です。
挿画は銅版画家の山本容子さんです。
ご高覧いただければ倖いです。
なお、銅版画は山本容子さんのオフィシャルサイトでも見ることができます。

「あなたの橋を架けよう」
第40回静岡高校教育講演会
・日時 2019年5月10日(金)13時30分開演
・会場 静岡市民文化会館 大ホール
・講師 恩田侑布子 川面忠男様ご寄稿の(下)として、第3章を掲載します。 第3章 世界でなぜ俳句が人気か
《恩田侑布子さんは、2014年にパリ日本文化会館客員教授としてコレ―ジュ・ド・フランス、リヨン第Ⅲ大学、エクスマルセイユ大学などで講演している。それで今回の講演の第三章が「世界でなぜ俳句が人気か」というテーマになっていることも頷ける。以下は恩田さんの話である。》 俳句とはいったい何だろうか。俳句がいま世界中の至るところで作られているのはなぜだろうか。グローバル世界に生きる現代人は俳句のどこに魅かれているのだろうか。
欧米の小学校ではカリキュラムに俳句の実作がある。夏休みの宿題にしているところも多い。
フランスでこの数年間、俳句をめぐる講演を6回行った。フランス人の俳句に対する理解と共感は半端ではない。街の本屋に芭蕉、蕪村、一茶、夏目漱石や山頭火の句集が並んでいる。またEUの前大統領、ヘルマン・ファン=ロンパイさんはベルギー出身だが、俳句に心を通わせ句集を出している。 ここでセザンヌやゴッホなど近代の芸術を支えて来たものは何であったかを思い出してみよう。それは個人の才能だった。作家の個性やその天才性を際立たせるものだった。
一方、俳句は根本の精神が違う。まず俳句には共同体に根づく「季語」がある。その背後には大きな自然が存在する。
自然は近代的な自我を超えたものだ。俳句を作る時、感情を季物に託して広やかで大きなものに自我を解放する。
蛇笏の落葉は、枯れて地べたに落ちて潰えるものという固定観念を破って、一人の人間の道念を支えるものになった。
俳句を作るということは、ささやかでも今までの自分のものの見方、感じ方を破ってゆくものだ。決まり切ったものの見方、パターン認識の縛りから精神が自由になってゆく。 作者が一句の中に生き切った俳句は、切れの余白の中で読み手が新たに生き直すことができる。蛇笏の〈落葉踏む〉の句は六十余年が過ぎて、一人の高校生の胸に飛び込んできた。今も心の底に落葉の踏み心地が感じられるのだ。
俳句は、作者と読者の一人二役を楽しめる興奮の場だ。表現の喜びと共感の喜びがある。
現代は技術革新が加速し、人間疎外どころか人工知能というAIに管理される時代になっている。そうした中で自然と共生し人と共感し合い精神の潤いを求める人たちが増えている。俳句は現代人が星の子としてつながり合うことができる可能性を持っている。
(川面忠男 2019・5・23)
講演の締めくくりに、恩田は自句21句を「俳句パフォーマンス」という形で披露しました。写真スライドを背景に、13句は日本語のみで、8句は日本語とフランス語で。
本抄録でも触れられているように、俳句は韻文であり調べやリズムという音楽性を持つこと、俳句が国際的な広がりを持っていることを、「俳句パフォーマンス」として直接伝える機会となりました。
これだけ多くの若者、しかも俳句に興味がある人ばかりではない講演会は恩田にとってもあまり経験が無いことでした。しかし、高校生の皆さんから「一冊の本を読むような講演会でおもしろかった」「まるで小説を読んでいるかのような感覚」などの感想をいただきました。恩田も、無事に大役を果たすことができたことを安堵しております。
終演後に控室とロビーで1時間半近くも続いた質疑応答や五百通以上の個別の感想をいただき、恩田自身も今後の創作活動に大いに刺激をいただくことができた講演会でした。
開催に向けて一方ならぬご尽力をいただいた静岡高校の志村剛和校長先生、教育講演会を主催した静中・静高同窓会ご担当の三浦俊一先生をはじめとする静岡高校の教職員の皆さまに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

「あなたの橋を架けよう」
第40回静岡高校教育講演会
・日時 2019年5月10日(金)13時30分開演
・会場 静岡市民文化会館 大ホール
・講師 恩田侑布子 恩田の母校・静岡県立静岡高校では、総合学習の一環として毎年各界で活躍する卒業生による講演会を開催しています。
今年は、恩田が講師として選ばれ、全校生徒約千人と保護者・同窓生及び一般参加の市民の方々を前に講演をいたしました。 講演は今回のために新たに作った100枚余のスライドを使い、以下の6章立てで進めました。
1)「辛かった子ども時代」 2)「高校時代に出会った感動の俳句」
(抜粋を掲載します) 3)「世界でなぜ俳句が人気か」
(抜粋を掲載します) 4)「読むという行為」
・AIの時代だからこそ、人間にしかできない
『耕し読解』を深める
・理系や科学者こそ俳句の精神に合う
…現実の直視と固定観念の打破 5)「東洋思想から餞のことば」
・釈尊の原始仏教は『耕し読解』の優れた実例
・自分に執着する心は最後の支えにならない
…原始仏教の教え「空の智慧」
・これから十年間で、生涯を支える精神の骨格
を作る 6)「俳句朗読パフォーマンス」 この講演会に同校OBとして参加された川面忠男様が抄録を作ってくださいました。その中から、第2章・第3章を(上)(下)二回に分けてレポートを掲載させていただきます。川面様、ありがとうございます。 第2章 高校時代に出会った感動の俳句 《静岡高校の生徒であった頃、恩田侑布子さんは中村草田男と飯田蛇笏の俳句に出会い心の救いを得た。恩田さんは教育講演会の第2章を「高校時代に出会った感動の俳句」と題し、あらまし以下の通り語った。》 俳句は定型のリズムと切れの余白によって感情を表現する。
会へば兄弟ひぐらしの声林立す
「兄弟」は「はらから」と読み、この中村草田男の句を歳時記から見つけた瞬間、全身がどこか別の場所に連れて行かれるようだった。 ひぐらしの声は天上から林に降りそそいでいる。それぞれの人生が山と谷をはるばるやって来て今ようやくここで出会った二人はお互いの静かな眼差しの中に憩うのだ。
このはかない苦しい人生にあってカナカナの澄んだ声に二人が包まれている永遠の瞬間だ。寂しくても生きながらえてさえいれば、いつか心を受け止めてくれる人に出会えるかもしれない。 「はらから」、ここに深い切れがある。俳句は切れの余白を味わうところに醍醐味がある。下五の〈林立す〉は詩人ならではの感受性だ。ひぐらしの声が林立し、現か幻か境のない空間に読み手は誘われていく。
兄弟という漢字に「はらから」とルビを振ったのはなぜだろうか。調べやリズムという音楽のためだ。俳句は韻文であり、名句は音楽である。
◇
飯田蛇笏との出会いは次の句だった。
落葉踏んで人道念を全うす
歳時記を読んだ時、目が釘付けになったが、道念という意味がわからなかった。広辞苑には「道を求めること、求道心」とある。蛇笏にとって俳句は仏道と同じなのかと思った。 この落葉に死屍累々という言葉が浮かんだ。落葉は滅び去って行った数知れない人々の思いではないだろうか。生きている自分は病弱な母が産んでくれた命。地球上で生と死が繰り返され、命をつないできてくれたことであろうか。
そう言えば夢中に読んでいる本も死者たちのものだった。図書館の書架の前に立つと死者たちの魂に囲まれているような感じがした。人類も自然の歴史も死屍累々だ。 〈落葉踏んで人道念を全うす〉とつぶやくたびにかわいがってくれた祖父母の仕草が次々に浮かんできた。その思い出は散りたての落葉のようだ。人の一生は死んで終わりではない。落葉を踏み死者を思うとき生きている者は自分の志を全うしようと思うのだ。
一生は自分一人のものではないと思った。その時だ。見たこともない、会ったこともない飯田蛇笏と言う人がまるで我が人生の師のように立ち上がった。俳句という文学の不思議さを痛感していた。
(続く)
(川面忠男 2019・5・21)
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。