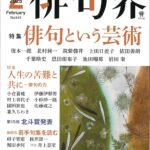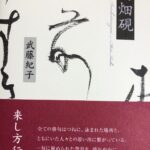2024年11月3日 樸句会報 【第146号】
11月3日の兼題は「釣瓶落し」「蓑虫」でしたが、これまでに例がないほど秀句ばかりが集まり、選句するのが心苦しいほど。特選4句という大変華々しい句会となりました。ところがその反動なのか17日の句会は目立った句がなく、なんと△が最高点、それも1句のみという結果に。「おでん」「帰り花」という身近な兼題であったことが、かえって難しかったのかもしれませんね。
特選4句、入選1句、原石賞1句を紹介します。
◎ 特選
投げ銭の帽子の歪み秋の暮
長倉尚世
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「秋の暮」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
蓑虫や母は父の死忘れゆき
活洲みな子
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「蓑虫」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
帰国便釣瓶落しの祖国かな
小松浩
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「釣瓶落し」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
穭田の真中の墓やははの里
見原万智子
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「穭田」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
柘榴裂き『ルビーの指輪』口遊む
林 彰
【恩田侑布子評】
寺尾聰の「ルビーの指輪」はお洒落でソフィストケートされた大人の恋を思わせる曲でした。昭和歌謡の名曲を引用しながら、この句は曲を超えて、若き日の恋が激しかったことを想像させます。ただでさえ鮮やかな血紅色の果物を、「裂き」とは強烈です。かつて女性の指に輝いていたルビーの指輪が、百も千も噴き出すようです。いまだ癒えない胸の疼きを宥めるように口ずさむ作者は男性に違いないと思わせます。女性なら裂く前に粒つぶを食べてしまうでしょう。
【原石賞】バイバイの声散り釣瓶落としかな
山本綾子
【恩田侑布子評・添削】
原句のままだと、「釣瓶落とし」に暮れたので「バイバイの声」が散っていった、という因果関係になってしまいます。省略を効かせ、調べに注意することで句が一変します。余分な言葉は「声」です。「散らばる」ともできますが、より余白を広げましょう。
【添削例】バイバイのちりぢり釣瓶落しかな
【後記】
俳句の会に人をお誘いするというのは、なかなか難しいものだと近頃痛感します。例えばヨガやピラティスでお付き合いのある方にやんわりと俳句の話を振っても、恐ろしく反応は薄い。体を動かすことではなくて座学のお好きな方なら、と前職の繋がりや語学クラスでご一緒する方たちに話を持っていっても、やはりはかばかしい返事は返ってきません。
ブームだと言われているものの、やはり俳句はそれなりにハードルの高い趣味なのかもしれません。私自身、興味はあっても始めようかどうしようか、ずいぶん逡巡したことを思い出します。俳句の定義や句会とは何かも知らないまま恩田先生の門を叩いた私が少々変わり種であるのは間違いありませんが、それでも作句は心躍るもの。この楽しさを分かち合う仲間が自分の知人の中から見つからないか、現在孤軍奮闘中です。
(成松聡美)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
====================