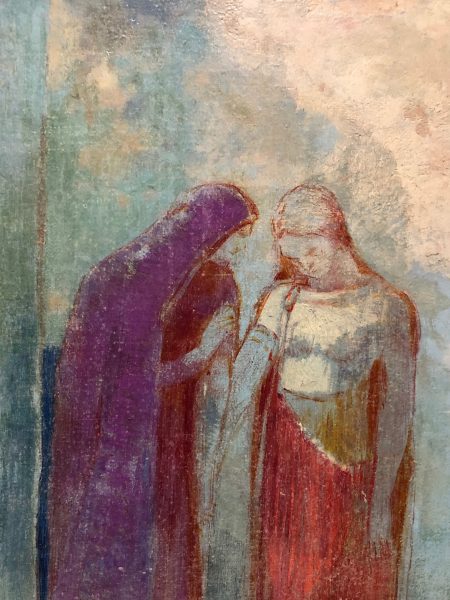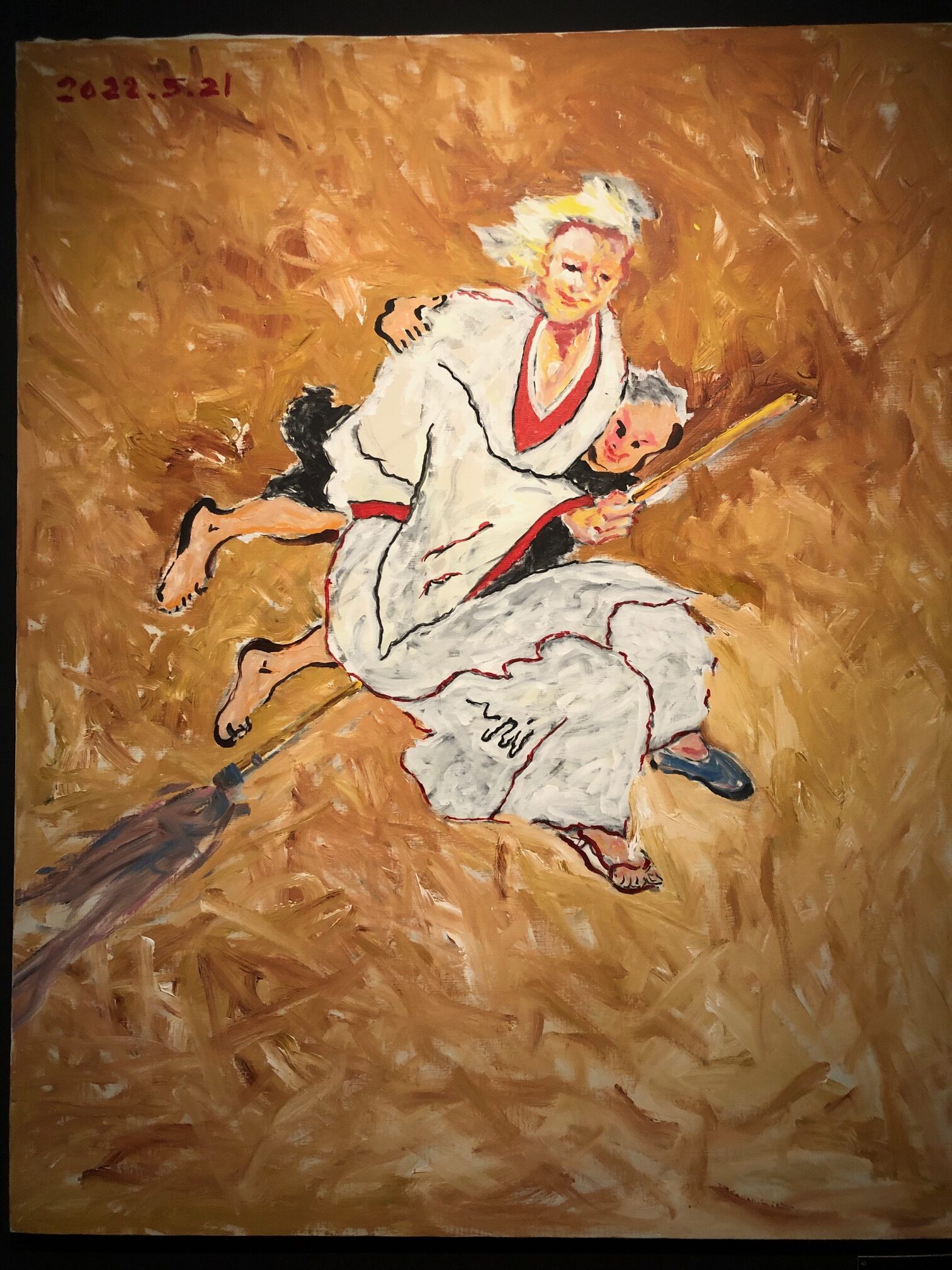
2024年9月15日 樸句会報 【第144号】 9月15日の兼題は「敬老日」「秋思」。心に染み入る俳句が並びました。 先生のご指導で印象的だったのは「俳句は最後の最後は人間性だ」という言葉。 俳句には沢山の決まりごとがあり、そこが楽しみの大きな要素です。決まりごとと向き合いながら、いかに深く正直に…そして最も大切なのは人間性。 俳句は面白い、あらためて確信できる会でした。 入選4句を紹介します。 ○ 入選 色鳥や病室に海照りかへす 古田秀 【恩田侑布子評】 夏の間は生い茂る緑にまぎれて目立たなかったが、秋になると色彩の思わぬ清らかさにハッとする小鳥がいます。折しも病室の窓辺にやってきて、無心に尾を振ります。その向こうにはキラキラと海原がいちめんにかがやいて。秋の空が真っ青なだけに、ここが病室であることが哀しい。見舞いに訪れた作者のまなこに、祖父の終焉の光景が残されました。 ○ 入選 父と遇ふ十七回忌夜半の秋 林 彰 【恩田侑布子評】 父と思いがけない遭遇をしました。しかもそれは父の十七回忌でした。遠忌の法事に、親族や有縁の懐かしい人々が集まってくれ、やがて潮が引くように去り、実家に一人になった秋の夜です。父が他界して十数年も経って、まったく知らなかった父の生前の姿、新たな横顔と向き合うことになったのです。静かなこころのドラマが感じられます。「あふ」には会ふ、逢ふ、遭ふ、もありますが、たまたま遭遇した意味の「遇ふ」を使ったことで、季語「夜半の秋」と交響し、肉親の情に奥行きが生まれました。墓じまいや、散骨が「ブーム」の現在、死者を弔い悼むことは、後ろ向きではなく、遺された人の明日の生につながることを示唆する気品ある俳句です。 ○ 入選 孝足らず過ぎていま悔ゆ敬老日 坂井則之 【恩田侑布子評】 愚直そのまま。飾り気も技巧もあったものではありません。作者の両親、少なくとも片親が他界されているのでしょう。敬老の日に、「ああ、外国旅行に連れてゆくこともなかったなあ」とか、「もっと頻繁に帰って、手厚く介護してあげたかったなあ」とか、様々な思いが胸をよぎります。それが中七の「過ぎていま悔ゆ」です。(孝行のしたい時分に親は無し)という諺にそっくりだと思う人がいるかもしれません。しかし、ここまで朴訥、簡明に俳句に結晶化することは誰にでも出来ることではありません。真率な思いが口をついて出た、鬼貫のいう、まことの俳諧です。 ○ 入選 問診票レ点と秋思にて埋める 成松聡美 【恩田侑布子評】 医者に行って、待合室で出される「問診票」の質問を何も埋めずに空欄にできる人はいたって健康です。この作者はほとんどの質問に「レ点」をつけなければなりません。「マークシートを埋めてゆくんじゃないのよ」。次第に憂鬱な気分に。それを「レ点と秋思にて埋める」と俳味たっぷりに表現した手柄。自己諧謔が効いた大人の俳句です。 【後記】 一年半前、音の数え方もままならぬ中で大胆にも恩田先生の門をたたきました。 日常に彩りをあたえ、何事にも好奇心をかきたて、絡まった過去をほどいてくれる…十七音の力の大きさを実感しています。 作句の面白さに加え、もう一つの楽しみが選句の時間です。同じ兼題で他の方はどんな句を詠んだのか。ずらりと並んだ中からぐっとくるものを見つける喜び、何度も読み返し次第に心が震えだした瞬間の感慨。二週間に一度の大切な時間です。 俳句と過ごした五年後十年後の自分自身の心のありようが今から楽しみです。 (山本綾子) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) ==================== 9月1日 樸俳句会 兼題は梨、蜻蛉。 入選4句を紹介します。 ○ 入選 高原の蜻蛉われらの在らぬごと 猪狩みき 【恩田侑布子評】 見渡す限りの高原を無数の蜻蛉が飛び交っています。「われらの在らぬごと」という措辞は、見つめているわたしたちなど眼中になく、透明な翅を水平に広げて伸び伸びと風に乗る姿をありありと感じさせます。別世界そのものの命のありようは逆に、人間が地球のあちこちで繰り広げている戦争や、分断や、飢餓の現実を照らし出しています。 ○ 入選 剥く音のよこで噛む音長十郎 山本綾子 【恩田侑布子評】 お母さんが梨を小気味よく剥いてくれるそばから、汁いっぱいの歯触りと甘みに夢中になる子ども。シャリリとした歯ごたえと代赭色の皮をもつ、昭和に流行った梨の品種名「長十郎」が効いています。赤褐色の皮がスルスル伸びていく映像の影に、ほんのりベージュがかった白い肌と、健康そのものの咀嚼音が共感覚を響かせ、初秋の清々しさがいっぱいです。 ○ 入選 ラ・フランス初体験の裸婦写生 岸裕之 【恩田侑布子評】 眼前のラ・フランスが呼び起こす記憶。美大生や画家の日常的なドローイングとはわけが違います。なんといっても「裸婦写生」の「初体験」です。ドキドキするうぶな感じと、モデルが期待した若い女性ではなく、腰回りに贅肉がたっぷりついた「ラ・フランス」のような中年女性であったズレたおかしみもにじみます。とはいっても「初体験」。輪郭を描きにくい太り肉(じし)のやわらかな存在感がこそばゆく五感を刺激してきます。 ○ 入選 鬼やんま逃して授業再開す 小松浩 【恩田侑布子評】 教室に突然、鬼やんまが飛び込んできた驚き。蜻蛉の大将は長くまっすぐな竿を持ち、大きな金属質の碧の目玉は、昆虫とは思えない威厳であたりを睥睨します。女の子はキャーキャー。男子は腕の奮いどころと勇み立ったか。先生は授業妨害物に過ぎないそれを窓から事務的に追放し、一言「さあ、教科書に戻って」。新秋の大空をわがものにする鬼やんまの雄勁な擦過力が、四角い箱の教室にいつまでも余韻を残します。