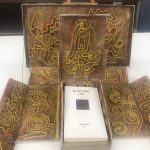-e1655464698250-150x150.jpg)
恩田侑布子「あきつしま」二句を巡って
角川『俳句』2022年6月号特別作品「土の契り」21句より 芹沢雄太郎
あきつしま卵膜ならんよなぐもり
一読、恩田の第四句集『夢洗ひ』所収の一句を思い出す。 あきつしま祓へるさくらふぶきかな
あきつしま(秋津島・秋津洲)とは古事記や日本書紀にも登場する言葉で、大和国、そして日本国の異名である。
古代の人びとにとって、あきつしまは世界にある一つの島国ではなく、全世界そのものであったはずだ。
「さくらふぶき」の句を読むと、そんなあきつしまに生きる人びとが、桜吹雪を眺めているうちに、桜吹雪が神に祈ってけがれや災いを取り除いてくれているのではないかと感じている、そんな光景が浮かび上がってくる。
また一方で、桜前線が次第に北上し、日本全土を次第に浄化していくというイメージは、テレビなどを通して日本を俯瞰して眺められるようになった現代的な光景とも重なる。
古代から現代に続く人びとの営みは大きく変化したかも知れないが、桜吹雪を前にした時の祈りに似た気持ちは、きっと変わらずにいるのだろうと、強く思わせてくれる俳句である。
今回の「よなぐもり」の句は、「さくらふぶき」の句からさらに進んで、日本とそれを取り囲む周辺諸国との関係を感じさせる一句である。
この句の「よなぐもり(=黄砂)」からは周辺諸国からの不穏な足音が聴こえ、それに対する日本のあまりにも無防備な姿は、まるで現代日本の情勢を象徴しているかのようだ。
また「あきつしま」「よなぐもり」というスケールの大きい言葉をぶつけながら、間に「卵膜」という言葉をはさみ、包み込むことで、この句は一気に身体的な実感を帯びはじめる。
時間軸に対する一瞬性と永遠性、空間軸に対する鳥瞰的な空間の広がりと虫瞰的な身体性、そういった相反するものが渾然一体となった恩田侑布子の俳句に、私は強く惹かれている。
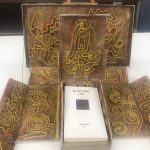
「無音の滝」 ―芹沢銈介美術館を訪ねて― 田村千春 人は美に憧れ、芸術に触れたいと欲する動物です。時には感動を大勢で分かち合い、明日への活力に変えてきました。まさか新型コロナの蔓延を防ぐため、そうした欲求にまで制限がかかる事態となるとは、誰が予想したでしょう。それ以前に俳句という、限られた条件の下、美を見出す極意そのものに出会えていて、つくづく幸運だったと思います。
今、私の手に静岡市立芹沢銈介美術館からのリーフレットが。「日本のかたち」と銘打ち、芹沢の収集した膨大な工芸品の中から日本の絵馬、玩具、やきもの、漆器、木工、家具、染織品等250点を特集し、2021年3月21日まで展示するとの知らせです。こちらを睨んでいるのは「かまど面」の写真――目は真ん丸、胡坐をかいた鼻、きっと結んだ口、異様なインパクト。かまど面とは何? 調べたところ、家を守る神様を土や木でかたどり、竈近くの柱に祀るという風習が東北地方でみられたようです。初めて見たのに懐かしく感じるのは、頑固親父を連想するからかもしれません。
芹沢銈介といえば、紅型の技術をきわめた、親しみやすくも先進的な作風で知られる染色家。世界の工芸品の収集家としても有名です。素朴な土色のお面を好んだとは意外な気がし、興味をそそられました。これは行ってみなければ。なにしろ月に一度は「一人吟行」に出掛けている私です。
いよいよ2020年12月、車で出発。まず登呂公園にあるという立地の良さ。博物館には弥生時代の住居も復元されていて、機織りなど当時の暮らしぶりもしのべます。そこから脈々と受け継がれる名工の系譜に思いを馳せながら、美術館へ。
特筆すべきは白井晟一の設計した建物――「石水館」の名にふさわしく、自然を生かし精神性を重視した造りは、威容を誇るビルディングとは対極にあります。驚いたことに外からは全容が知れないのです。この不思議をぜひとも体験し、館内をめぐる際には指定された品の県名を書き込むクイズにも挑戦してみてください。出来上がった用紙と引き換えに、芹沢による型染の富士山の葉書をいただけます。
着物や漆絵の色彩の妙、木箱や酒樽の洗練ぶり、かまど面の凄まじいまでの表情。これらに囲まれ、潤いある生活を送ってきたのだと気づかされます。芹沢の物を見る目は温かく、誰よりも確かでした。
この慧眼が彼の美の礎となったのでしょう。芹沢自身の作品も60点、どれも明快にして親しみ深いものばかり。紅型のスタッカートが効いており、時代を超え、世界中の人々を元気にするに違いありません。例えば、屏風の考え抜かれたレタリング――「春夏秋冬」――なんと愛らしいこと、あたかもバレエを観るよう。それぞれ羽をすぼませたり、アラセゴンに広げてみせたり。
自然と一体化して産み出された作品には、明るさの中に何とも言えない静けさがあります。例えば1962年作の「御滝図のれん」。生きている滝に胸を打たれ、能狂言に通じる抑制された美にしばし見惚れました。1948年には既にアイディアがあったらしく、制作に取り掛かるのに長い年月を要し、さらに芹沢邸の訪問客で、図案がどんどん変わっていく様を目撃した方もいたのだとか。時間をとことんかけ、人の反応も参考にしながら完璧を求めるとは、謙虚な姿勢に頭が下がります。伝えられる「自分というものなどは、品物のかげにかくれてしまうような仕事をしたい」との言葉にも考えさせられました。これは無我の境地に至った作家だからこそ口にできるのではないでしょうか。幾多の線より正解を選び取れる芹沢でなければ、一条の滝に命を吹き込むという偉業は成し遂げられなかったのですから。
清新なる世界へといざなう暖簾からは、片時も離れたくなくなります。出口に近い特別室と展示室とを、何遍も行ったり来たりしてしまいました。特別室からは硝子越しに坪庭を眺められます。その坪庭は、まさに白井晟一の手による一幅の絵。枝垂梅が一身に日射しを浴び、何だかあたたかそう。身に余る体験をさせていただいた一日を振り返って、一句。
坪庭の枝におもたき冬日かな 住宅街を駐車場へ向かう途中、何軒も芹沢の暖簾を掛けているのを垣間見ました。愛される人間国宝、今も自らの願いを存分に叶えています。日々なにげなく使う品物に愛情を注ぎ、精魂込めてくれた芸術家がいたことに、心から感謝を。コロナ禍で舞台芸術などの開催が難しくなっても、無限の美を手に入れるための鍵ならば、ここに残されていると確信しました。 (たむらちはる 樸俳句会員)
静岡市立芹沢銈介美術館のホームページはこちらです
↑
クリックしてください

韻文への迷路
金森三夢 私の俳句との出会いは、小学校の国語。「万緑の中や吾子の歯はえそむる」という草田男の作品でした。緑と白の瑞々しい対比の素晴らしさに心を奪われました。そして俳句の奥行きの深さを知ったのが、高一の時に習った虚子の「桐一葉日当たりながら落ちにけり」でした。日当たりながらという中七が、秋の日差しの中で桐の葉がゆっくりと落ちていく様子を適確に写生したものと、現国の担任で、かの石原慎太郎と芥川賞を争ったという豪傑・西山民雄先生に教えて戴き感銘を受けました。
俳句は散文的な要素を極端に嫌います。説明的な句は厳格にタブー視されます。私はこれまでほぼ散文一刀流。生まれて初めて活字にしていただいたのが小6の作文。初めて原稿料を戴いて全国の書店に並んだのもエッセイ、初めて印税を戴いたのは小説とすべて散文でした。十年ほど前、呆け防止のためNHKの俳句講座で独学を始め、ビギナーズラックで月刊角川やNHKテキストに四回載せて戴いた俳句も決して満足のいく作品ではありませんでした。独学の限界を感じた昨今、高校の先輩の三木卓氏から恩田侑布子氏を紹介され、講演会で恩田氏のお話を拝聴し感銘を受け、五ケ月前から樸の句会に入会させて戴きました。句会は自らの欠点を見つめ直す素晴らしい道場です。恩田代表から「こんな観念的な句は散文でも書ける。散文では表現できない機微を端的に17音で伝えるのが俳句」とのご指摘を受け、所謂「切れの余白」と「季語の本意」という考え方が朧げながら理解できるようになり、句会出席の楽しみが増して来たこの頃です。
恩田代表のひたむきで、ストイックな俳句への姿勢に驚きながら、自らは俳人の域に達するのは無理でも、一日一句を重ねつつ、日々高みを目指し、出来れば俳句富士山の五合目位まで登れればと念じて藻掻き苦しむ毎日です。 2020年3月 かなもりすりーむ(樸会員)

樸俳句会の新会員・金森三夢さんの投稿をご紹介します。
ペットボトルと野遊び
金森三夢 水ぬるむ季節の到来です。年金生活者の私ですが、貧しき者も富む者も、自然は平等にその魅力を享受させてくれます。私はリュックにでっかい塩むすびをひとつと、ペットボトルに水道水を詰め凍らせスナフキンのカバーに入れ、句帳と歳時記とともに出発します。
自然からの瑞々しい息吹をキャッチし、絵描きさんがスケッチをするように、句帳に季節からのメッセージを自分だけの言の葉でデッサンしてゆきます。色付け(推敲)は帰ってからのお楽しみ。連れ歩くペットボトルはかの伊藤園さんから頂戴した愚生の句の載ったマイボトル。30年ほど前に公募がスタートした「おーいお茶」俳句の第一回に面白半分で投句し佳作の末席に胡坐をかいた
銀杏散る神宮の杜初デート
という迷句以来ご無沙汰していた投句を、呆け防止のためにNHKで句の独学を始めた10年前から再チャレンジ。ペットボトル掲載の確率は130分の1程度ですから、そんなに難しくはありませんね。NHKテキストに投句される方は真剣に俳句に精進されている方々ですが、「お茶」の方は初心者やお遊び気分の方もきっと多いので、掲載の確率はかなり高くなります。
ちなみに愚生の句でこれまでにボトルに載ったのは
また一年頼むぜ祖母の種袋
年金で十八切符山笑う
漂白を海月に習ふ余生かな
以上の3句。いずれもプレバトに出せば凡人第5位程度のものです。佳作特別賞になるとボトル1ケース(24本)がゲットできますので、自分のネーム入りのボトルをお供に彷徨するのも一興ですよ。次回は散文から韻文へをテーマに恩師の詩と俳句をご紹介致したいと存じます。 2020年3月 かなもりすりーむ(樸会員)

砂漠と俳句 8月下旬、中国の「内モンゴル自治区」という所へ行き「植林活動」を体験してきました。砂漠に1mの穴を掘り2メートルのポプラの苗木を植えるのです。炎天下での作業なので、汗まみれ・砂だらけ・・・。
この緑化活動は30年前に日本の一人の学者が取組み初めたのが最初ということでした。鳥取砂丘を農地に変えた経験をもとにして、この地の「緑化」に挑んだのです。葛を植えては羊に食べられ、苗木を植えては幹をかじられ、水の確保に奔走し、苦難の連続を乗り越えて、砂漠を緑の地に変えたのです。もちろん、その過程には多くの日本人の手がありました。
起伏にとんだ砂漠なので、丘の上に立つとさながら「天下人」であり、谷の中に立つと、まさにアリジゴクの様です。ほんの一時訪れる人には「自然の偉大さ」を感じさせますが、ひとたび風や雨になると、すべてを呑み込んでしまう恐ろしさを内包しているのです。砂漠は、そんなところでした。 360度砂に囲まれた地に立って、瑞々しい日本の自然を思いました。寒い冬を耐えた後にやってくる、あの春のうれしさ、沈む夕日を眺め、次第に回りがシルエットになってくもの悲しさ・・
でも、ここでは「みかんの花咲く丘」や「ふるさと」のような曲想は生まれてこないだろうし、俳句のような文化にも縁が無いように感じました。だから、句も「無季」になってしまうのではと思っていました。 〇ポプラ植ゑ流砂止めむと倭人の手
〇人影にジェットエンジンもつトカゲ
〇晩餐のモンゴルの唄白酒干す ・夕食時に、地元の顔役に促されて通訳の人がモンゴルの唄を歌ってくれたのです。
「素晴らしい歌声でした。なんのお礼も出来ませんが、日本の俳句は聞いたことがありますか」
「・・詩のことですか」
「ええ、最も短い詩です」 ・・・ノートに書いて彼に渡したもの・・ でも、ここには砂漠としての自然があるのではないか。少なくも、時候や天文あるいは地理の季語は成立するのではないか・・。
〇秋風や砂地を直に駱駝の背
〇モンゴルの唄に色なき風砂漠
置き去りにされて帰れなくなるのではと心配しながら眺めた星空は魅力的でした。
〇羊追ふ砂漠の民や天の川
〇モンゴルの唄は砂漠へ天の川
貴重な体験の中で思ったことの一端をしたためてみました。
令和元年9月 松井誠司

2017年6月4日の日曜日、独りで車に乗り、桃畑とさくらんぼ畑が広がる甲府盆地を走っていた。
中沢新一さんと小澤實さんの共著『俳句の海に潜る』(※1)で二人が訪れていた、甲州の丸石をこの目で確かめてみたかったからである。同著によると丸石とは道祖神のひとつで、峠や辻、村境などの道端にあって悪霊や疫病などが外から入るのを防ぐ役目を果たしており、甲州に広く分布しているのだそうだ。
その特徴は何といっても石の丸い形にあり、ある美術評論家は「ブランクーシを超えてる」とまで言ったという。
丸石は単独で祀られていたり、複数個が無作為に並べられていたり、基壇の有無や形状も様々である。
また歴史は古く、縄文時代から存在している可能性があり、石の形状は自然に生まれたのか、人工的なものなのか諸説あるという。
現存する丸石を示す地図等がない為、私はカーナビから、直観的に古い道や川、町の境界と思われる所にあたりをつけ車を走らせてみた。
たった2時間の間に6カ所の丸石に出会うことが出来た。
訪ねたのが晴れた夏の午後だった為か、影が真下に落ちた丸石は、眩しさと不思議な静けさを身に纏っていた。
私は丸石に手を触れ、耳を当て、一礼してからスケッチブックにフロッタージュ(※2)を行い、太古の人と風景に思いを巡らせてみた。
すると、この丸石に屋根を架けてあげたいという思いが私の中で沸き起こってきた。
あるいは、かつてここには実際に屋根が架かっていたが、時の流れの中で屋根が風化し、石だけが残ったのではないだろうかと思えてきたのである。
もしそうだとしたら、そこには道行く人が立ち寄り、憩い、祈る場所になっていたのではないか。
中沢新一さんは俳句について「作られた時代は新しいにもかかわらず、本質が古代的」(『俳句の海に潜る』より)と語っている。
自然に対して素直に向き合えば、現代においても、ふさわしい場所へ、ふさわしい石を配置し、新しさと古さとが共存する屋根を架けることが出来るのだと、丸石が語っているような気がした。
(文・芹沢雄太郎) 日盛や擦り出したる石の肌 雄太郎
(※1)中沢新一 小澤實『俳句の海に潜る』
(2016年12月 KADOKAWA刊)
(※2)フロッタージュ:
<摩擦の意>石・木片・織目の粗い布などに紙を当てて木炭・鉛筆などでこすることで絵画的効果を得る方法。(出典:広辞苑)

藤村の「初恋」の詩を愛唱したのは、いつのころだっただろうか。農作業の合間に三本鍬を傍らにおいて父がこの詩を口ずさむのを聞いたことがきっかけだった。七五調の調べは、心地よさを感じさせてくれる。幼少期を決して豊かでない農村で、少しだけ文学に興味を持っていた父のもとで育った私にとっては、七五調は、まさにゆりかごのようなものだった。口にして心地よく、気持ちが「安定」し全身が落ち着くのである。 しかし、数年前に「俳句」に出会い、初めて句を作ってみると、出来たものは安定の中にあり、切れや余白がまったくないものばかりなのである。つまり、説明的になってしまっているのだ。理屈ではなんとなくわかっているように感じてはいるが、いざ句を作ってみると散文調なものになってしまうのである。無意識のうちに俳句の持つ「不安定さ」にしり込みし、ブレーキをかける自分がいるのである。 たとえば、こんな句を作ったことがある。「菅笠や花野の中に見え隠れ」・・先生のご指摘は、菅笠と花野の中に、という言葉の中に「見え隠れ」する様子はふくまれているのだから、これは必要ない言葉である。このように説明的になるのは「心の中に渦まくような思い」がないからである・・とのこと。しかし、当の私にとっては「見え隠れ」としないと、なんともおぼつかなく、気持ちが安定しないのである。 俳句を学ぼうとしたのは、その道の専門家になろうとしたのでは勿論ない。これからの人生を少しでも心豊かに過ごしたいと思ってのことである。やや大げさに言うなら精神の高みを求めてのことである。しかし、自分のある部分を変えるということは、人間の「本性」に属するだけに、ややこしいことなのだ。野球のバットの振り方とか陸上の走り方とかいう「属性」に関することなら、練習次第で改善はできるが、その人そのものに関することは難しいものだ。 わずかでも安定さを打破し、自分自身のものの見方や感じ方などの「ささやかな変化」を求めて、俳句に向き合っていきたいと思う。それが、これからの時間を豊かにしてくれそうだから・・・。(文・松井誠司)

俳句の良い悪いとはなんでしょう?
こんな話をよく句会で議論します。
どんな俳句も読んだ人の好みがあり、一様に「良い・悪い」と言えないものですが、やはり「名句」と思うものは歴然と輝いて見えます。
その違いは何か? 恩田侑布子は、「切れ」にたたみこまれた余白を味わえるのが名句ではないか、とよくいいます。 俳句の「切れ」を読み取ると、正確に主題をつかむことができ、その句の世界が立ち上がります。主題が強靭な句は、ただ単にその世界を眺めて楽しむだけに終わりません。こちらから句の懐に飛び込ませてくれる深さがあり、飛びこんでみると新たな景色を見ることができるのです。そんな句と出会えることが読む楽しさであり、読まれる楽しさだと思います。
が、裏を返せば「主題」が分からなければ何も始まらないのです。〈作者だけに分かる、私だけの主題〉では出来損ないの暗号文になってしまうし、〈誰にでもわかる、ありきたりな主題〉では面白くありません…。つい出来損ないの暗号文を作ってしまいがちな私は、毎回その舵取りに悩みます。
分かってはいるはずなのに、いざ作ると自分の想いとは別のところを「主題」と読まれてしまったり、そもそも「主題」が行方不明になっていたり…。 そんなことを考えていたら、とあるレストランでこんなメニューを見つけました。
『イチゴ揚げアイスパンケーキ』
揚げられているのは〈イチゴ〉か〈アイス〉か…。
それとも〈揚げ豆腐〉が入っている新感覚スイーツか?
一体この食べ物の「主題」はどこに?!
ここまで客の気持ちを惹きつけるとは、商品名として大成功!
お店の人も困惑するお客さんを見てニンマリしていることでしょう。 でもこれが俳句だったらどうでしょう?
読んだ人が困惑する姿をニンマリ見ることは俳句の楽しみ方ではありません。
商品であれば実際に出てくるもので勝負できますが、俳句はその文字が全てなのです。
それがどういう形態で、どんな温度で、どんな味で、どんな感想を抱かせるのか、十七文字で表現しきらなくてはならないのです。
謎のスイーツを通して、自分の句を改めて観察することになろうとは思いもよりませんでしたが、課題がより明確になったのはよい収穫でした。〈誰にでもひらかれた、私だけの主題〉を詠み込めるよう、決意を新たに精進したいと思います。(山田とも恵)
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。
-e1655464698250-150x150.jpg)