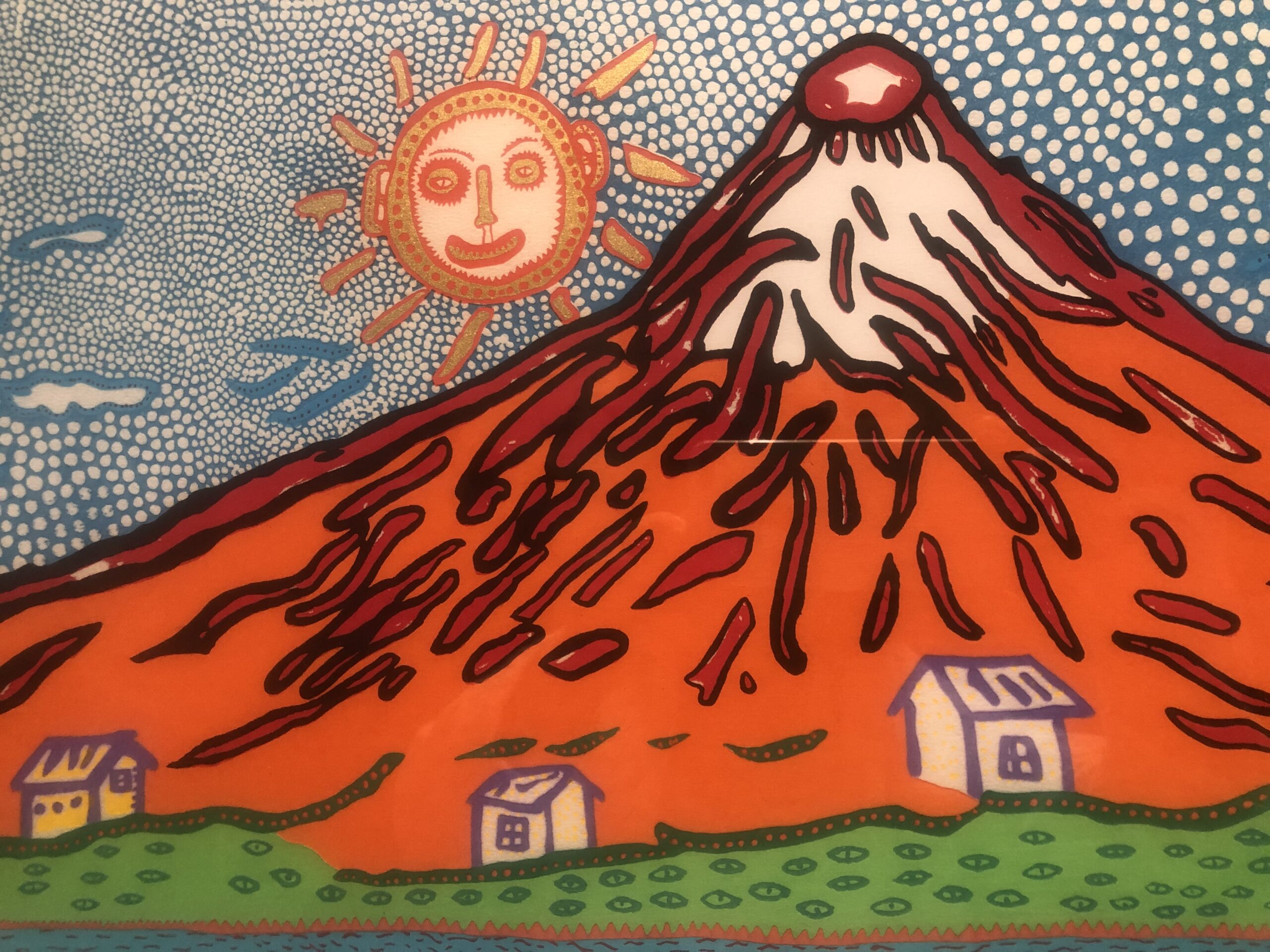2025年7月20日 樸句会報 【第154号】 7月20日はリアル句会だった。通常のzoom句会ではパソコンの画面を通して対峙している面々が静岡市生涯学習センターアイセル21に集合した。久しぶりに顔を合わせれば話したいことは山積みだ。隙間の時間を見つけては話の花が咲いた。
句会の後半は師が講師を務める早稲田大学オープンカレッジでの秀句を鑑賞した。とくに、「夕焼や天には天のゴッホゐて」という名田谷昭二さんのスケールの大きく瑞々しい感性に大いに刺激を受けた。 兼題は「トマト」「サンダル」。入選2句を紹介します。 忘れたし手に白繭を転がして 恩田侑布子(写俳)
○ 入選
白玉や母の話はまた元に
活洲みな子 【恩田侑布子評】 白玉団子を親子で向かいあって掬っています。たわいもない昔話が弾みます。老いた母の記憶はやさしく涼しげにまた元にもどってゆきます。はつらつとしていた頃にくらべ、頭脳の衰えが少しばかり感じられる昨今。白玉のなめらかな舌ざわりに、母の子として育った倖せをしみじみ思う夏の昼下がりです。
○ 入選
満塁や灼くるシンバル灼くれど撲つ
小住英之 【恩田侑布子評】 下五のしつこいリフレインと字余りが効果的です。高校野球の満塁の場面でしょう。満塁は、天も地もひっくり返るかの興奮のるつぼ。応援団やチアガールの汗をかきたてるシンバルが球場に狂乱のように反響します。こんな酷暑の瞬間なら体験してもいい、いえ、ぜひ体験したいと思わせてくれます。
【その他に評価の高かった句は次の三句です。】
下思ひや日へ透かしたるラムネ玉
益田隆久
古書店に雨おしえらる麦茶かな
長倉尚世
揚花火鉄の貴婦人張り合ひし
佐藤麻里子
【後記】
俳句を始めて2年半が経つ。
入会当初に比べれば俳句への理解は大分深まったように思う。そんな中、これまで学んだ内容からはみだしていないことを確認し、リアル句会に投句した。
会員の選はまずまずだ。今日はよい評価がもらえるのではないか、期待が膨らんだ。
ところが師の選には1つも入らなかった。
理由は日記のような句であるから。
また小利口な70点の句を量産しても意味がないとも。
ガツンとハンマーで殴られたような気持ちになった。しばらくしてその言葉の本意が浸透し始める。ハンマーでガツンの次は冷水を浴びて目が覚めた、そんな感覚だ。
ああ、そういうことか…。
無自覚のうちに小手先の技術を覚えたことを師はすっかりお見通しなのだ。
改めて確信した。
俳句は面白い。
そして師恩田侑布子のもとで学ぶ俳句はとても面白い。
俳句作りにゴールはない。学び続け俳句のある人生を謳歌したい。 (山本綾子)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 天心へ発ちてつつまし蟬の穴 恩田侑布子(写俳)
====================
7月6日 樸俳句会
兼題は暑中見舞、合歓の花。
原石賞5句を紹介します。
【原石賞】病む朝を蛾の垂直に羽休め
見原万智子 【恩田侑布子評・添削】 体調が悪いとつい気も滅入ってしまいます。そんな朝、「蛾」が「垂直に羽休め」というのですから、壁にひっそり止まっているのでしょう。「羽休め」では、作者にも蛾にも安堵が感じられ、くつろぎが出てしまいませんか。ここはものいわぬ蛾が「貼付く」陰気さを出したいところです。俳句ではやや使いにくい完了の助動詞「ぬ」が感触的にピッタリきます。夏の朝の作者の鬱陶しさや不安な体調も滲みます。 【添削例】病む朝を蛾の垂直に貼付きぬ
【原石賞】瑠璃釉に暑中見舞の氷見うどん
小住英之 【恩田侑布子評・添削】 細いけれど強いコシと餅のような粘りがある氷見の手延べうどん。実際のおいしさもさることながら、「氷見」という固有名詞がじつに効いていて、氷床に盛られた涼しさを幻覚します。自分で買ったのではなく、暑中見舞いの知友の気遣いのありがたさも。焼物の「瑠璃」も白いうどんの肌との対比が見事。一つ惜しいのは「釉に」です。単なる色彩の対比になってしまうので、「鉢」とし、卓上に氷見うどんが盛られた存在感を表現しましょう。 【添削例】瑠璃鉢に暑中見舞の氷見うどん
【原石賞】なつかしき癖字三行夏見舞
山本綾子 【恩田侑布子評・添削】 中七以降のフレーズ「癖字三行夏見舞」が出色です。それに比べると上五の「なつかしき」は平凡で、答えが出てしまいました。どうしたらいいでしょう。やり方は色々ありますが、一つの方法としては、この暑中見舞葉書を手にした時の質感を浮かび上がらせることです。「手漉き和紙に」とする風流路線もありますが、少しわざとらしくなります。「癖字三行」を書いてきた友だちの豪胆さが出れば、お互い元気に厳しい夏を乗り越えられそうです。。 【添削例】太ペンの癖字三行夏見舞
【原石賞】合歓咲くや七回忌了へ父の夢
活洲みな子 【恩田侑布子評・添削】 全体的にあたたかい気持ちがぼうっと感じられますが、句末の「父の夢」で、すべてが夢幻にすぎないように思われてきます。俳句は、どんなに夢や幻想に飛翔してもいいですが、最後の最後はこの現実に着地しなければなりません。そうすると語順を変える必要があります。父は亡くなったけれど、父が愛して庭に植えた合歓が今夏は咲いている。夢は実現したのだという内容にしましょう。「合歓」の花のやさしい余韻が残る句になります。 【添削例】七回忌了へたる父の合歓咲けり
【原石賞】淵碧き砦裸のピカソかな
佐藤麻里子 【恩田侑布子評・添削】 十九世紀以降、西洋の画家は宗教画から自由になり、自然の中で働き、くつろぎ、遊ぶ市民を画面に主役として描くようになりました。十九世紀後半から二〇世紀後半まで、一世紀近くを生き抜いたピカソの創作の源泉を「淵碧き」と捉えた素晴らしさ。しかし、「砦」は「芸術の砦」を思わせ。やや理に落ちませんか。ピカソはせっかく「裸」なので、碧の淵に遊び、創作のインスピレーションを得る開放感に解き放ちましょう。ピカソの天才を畏敬する秀句になります。 【添削例】碧々と淵に裸のピカソかな
【その他に評価の高かった句は次の二句です。】
向日葵や主治医の胸にアンパンマン
活洲みな子
等間隔警官配置沖縄忌
成松聡美
ラムネ飲むからんころんと月日かな 恩田侑布子(写俳)
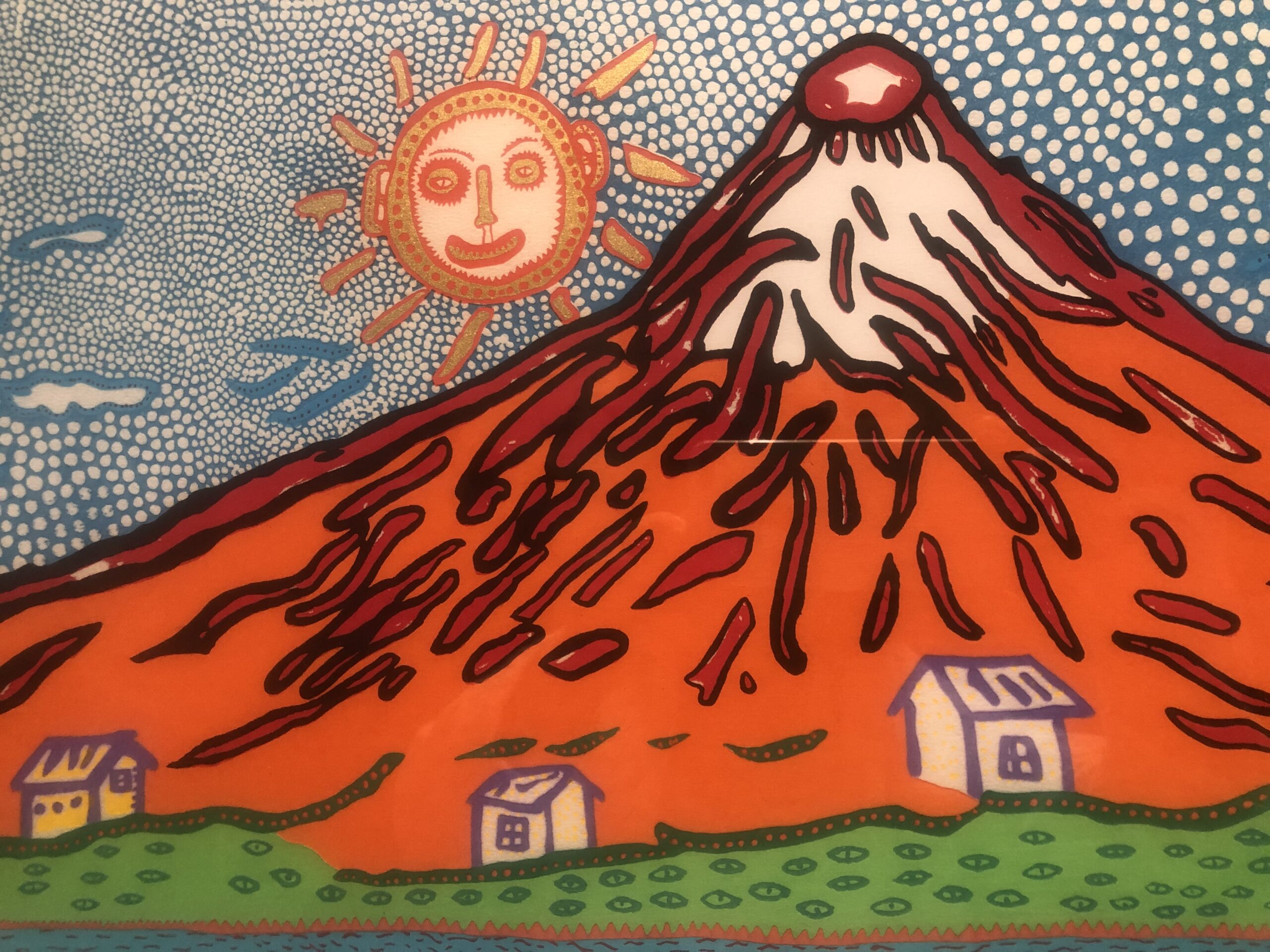
2025年6月15日 樸句会報 【第153号】 六月は一日および十五日にZoom句会を行い、いずれも日本、フランス、アメリカから会員が参加し活発なディスカッションを行いました。樸の仲間である古田秀さんが六月十三日に第15回北斗賞を受賞されたことを記念し、十五日は定例のZoom句会に加え、北斗賞受賞作品から恩田先生が選ばれた珠玉の23句の鑑賞・評価を行いました。初心者に向けた句意の解説から、作句の際に注意していること、おすすめの吟行先など、踏み込んだ議論を交わすことができました。またこの中で恩田先生から古田さんに句集の編み方についてアドバイスされる場面もあり、極めて貴重な俳句談義となりました。 兼題は「短夜」「泉」。特選1句、入選2句を紹介します。 峯雲をあて極冷のプルトップ 恩田侑布子(写俳)
◎ 特選
日盛りの影もたれあふ交差点
小松浩 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「日盛り」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
枇杷たわわ廃車置き場の水たまり
長倉尚世 【恩田侑布子評】 入梅を前に、にわかに、またたわわに色づく枇杷の実が、どこにでもある地方都市の「廃車置き場の水たまり」に逆さに映っています。弛さ、物憂さの感覚が映像に濃厚です。極熱の真夏がやって来る直前の心身のやるせなさ。背負い込んだ暮らしの諸々のやるべきこと、こなすべき雑事のあれこれ。微妙な感覚と感情が「水たまり」に湧きあがっています。
○ 入選
短夜や眸句集とミントティー
山本綾子 【恩田侑布子評】 『岡本眸全句集』に読み耽り、夏の夜がしらじらと明けてしまった作者です。眸句集の持ち味と、文学の特質をよく言い得ています。高名で長寿の俳人でしたが、実人生は順風満帆ではなく、陰の悲哀に包まれた一生でもありました。しかし、その作品はたしかに「ミントティー」のようななつかしさと、すっくと背筋を伸ばした清涼感を湛えています。それは岡本眸という人間の香りであり、文学の芳醇さといってもいいでしょう。
【後記】
仕事の都合で2024年の春に渡米した私は、その冬になぜか俳句を始めました。摩天楼と摩天楼の間にある小さな公園の桜の木、温かな生活排水路のマンホールに寝転んで暖を取るホームレス、そのホームレスの眼前にそびえ立つ真っ白な冬の国連ビル。日々インプットされるこういった異国の景色を、なにかしらアウトプットしたくなったのかもしれません。
俳句を始めて半年ほどたった頃、たまたま古田秀さんの鈴木六林男賞受賞作品「ビバリウム」を目にして、樸俳句会を知ることができたのはまさに僥倖でした。ホームページの「どんなに遠くてもすぐつながれます」の文言に飛びついた私を、樸俳句会はあたたかく迎え入れてくださいました。まだ始めたばかりですが、月二回というハイペースで和気あいあい、かつみっちりと恩田先生のご指導を受け、作句のみならず鑑賞の奥深さ・面白さを学ばせていただいております。これからも楽しく真剣に学んでいきたいと思います。
(小住 英之)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 早桃食ぶ真午しんかんたる山河 恩田侑布子(写俳)
====================
6月1日 樸俳句会
兼題は滴り、ビール。
入選2句、原石賞1句を紹介します。
○ 入選
聖五月ぐさりとキャパのレンズかな
星野光慶 【恩田侑布子評】 季語の「聖五月」に「キャパのレンズ」を配合し、21世紀も4半世紀が過ぎた只今の混迷の世界を照射します。フォト・ジャーナリストのロバート・キャパはスペイン内戦や日本の中国侵略や第二次世界大戦の現場に立って、丸腰で多くの写真を撮りました。副詞「ぐさりと」が「レンズ」にかかり、刃物の鋭さが暗喩されています。七〇年から九〇年も前の戦争や内戦の写真が、少しも古びず、逆に生々しく現代の人類の所業を告発する「聖五月」の無惨さ。
欲を言えば、副詞の「ぐさりと」で修飾しない方向へ推敲ができればさらに大柄の秀句になる可能性を秘めています。
○ 入選
地ビールを二本空港泊の窓
小住英之 【恩田侑布子評】 「空港泊」とは、何らかのアクシデント、あるいは異常気象のために突如欠航になったのでしょうか。夏の季語の「地ビール」が効いています。初めて訪れた遠い土地で、観光もしくは仕事を終え、帰り際に足止めを食らったが、「空港泊の窓」という措辞から、その土地への愛着が生まれたことが伝わってきます。地球の土地土地に根付いた人々の暮らしを愛しみながら、二本の地ビールをゆっくりと味わうコスモポリタンの視線の裕かさ。
【原石賞】神輿胼胝比べあひたるビールかな
古田秀 【恩田侑布子評・添削】 「祭」の季語の中でも「神輿」、それを担ぐ胼胝に着目した素材の発見が面白いです。ただ、「あひたる」でリズムがもたついてしまうのが惜しいです。どの助動詞を選び、活用をどうするかは、俳句の死命を制する大事です。次のようにすれば、夏祭が盛り上がり、主人公の神輿の担ぎ手から解放されたばかりの達成感と安堵感が表現されましょう。 【添削例】神輿胼胝くらべ合ひつつビールかな
足あとのちゞみ初めたる植田かな 恩田侑布子(写俳)

2025年5月18日 樸句会報 【第152号】 「五月」というひびきのよい語感には、新鮮な生命力がある。物憂い晩春から一気にベールを脱ぎ棄てて、初夏へ。「新緑」「風薫る」「若葉風」…と季語にもあるように、大地が緑に染まるさわやかな季節だ。
我が『樸』にも若葉風が吹く。アメリカから、フランスから、新しい会員が加わった。インド在住の会員も含め、日本以外の風土や文化を含んだ風が、『樸』に吹き込んでくることをとても楽しみにしている。
今回の兼題は「薄暑」「蚕豆」。特選1句、入選2句、原石賞1句を紹介します。
息継ぎのなき狂鶯となりゆくも 恩田侑布子(写俳)
◎ 特選
スケートボード蔓薔薇すれすれに蛇行
古田秀 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「薔薇」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
肩書のとれた名刺と空豆と
活洲みな子 【恩田侑布子評】 名刺に立派な肩書きがあればあるほど俗人はうれしく誇らしいかもしれません。しかし作者は「そんなもん、やっと取れた」と清々しく思っています。組織の人間でなくなった自由こそが、晴れて味わう五月の空豆の美味しさです。もちろんビールを片手にして。技法的には、「と」で名詞を並列した句は「たるみ」が出がちですが、この句は逆にその並列が効果を発揮してリアルです。
○ 入選
新快速午睡絶滅皆スマホ
林彰 【恩田侑布子評】 京阪神地域の主要都市を結ぶ快速の車輌風景。昔の夏は、戸外の暑さに疲れた人々が冷房の効いた車内に乗り込むや、ついうつらうつらして船を漕ぎ出したもの。しかし、今ではそんな人は一人もいません。みな小さなスマホの窓を覗き込んで指先で操作しています。名詞を五つ並べた句がビビッドなのは、句頭の「新」と中七の「絶滅」の効果。まず、新しい快速電車が走る午後に昼寝族は「絶滅」したという断定が面白いです。さらに、車両とスマホの相似形も見逃せません。肉体は車両にあり、脳はその縮小相似形のスマホに吸い込まれ、小さな画面から世界大の情報の海に溺れている夏の午後であることよ。「昼寝」の季語を、昼寝しない人らを素材に歌うのも新しい表現。
【原石賞】かたらねど母のかたはら緑さす
前島裕子 【恩田侑布子評・添削】 病床にあって言葉少なくなられたお母さんでしょうか。黙っていても温かく心は通じ合っています。「緑さす」の季語の斡旋が抜群です。この世で許された浄福という感じがします。惜しいのは「かたらねど」の措辞の粘りです。上五を「もだす」という動詞に変えれば、心の通じ合った安らぎが一層感じられるでしょう。 【添削例】黙しゐて母のかたはら緑さす
【後記】
私ごとだが、事情があってこの4月までの半年間、句会を休ませていただいた。「句を作ることを続けないと、句はだめになる」。日ごろの師の教えを胸に、締め切り前にバタバタと投句だけは続けた。
5月から句会に再び参加。久しぶりの句会は…これがなかなか面白いのだ。Zoomの窓が開き、親しい人と目が合って思わず目礼。新入会員の紹介や会員の授賞式のお知らせには、小さな拍手があちらこちらから起こる。画面の窓は小さいけれど、恩田先生は相変わらずエネルギッシュだ。
仲間の句を推す会員相互の熱弁(?)も、師から質問されて一斉に下を向く姿も、画面を通して息遣いまで感じられる。以前の私は断然リアル句会派だったが、会員の幅が広がり、パソコン操作にも少しだけ慣れた今、Zoom句会ならではの面白さを楽しんでいる。
とはいえ、句会に参加できなかった期間に投句だけは続けることができたのは、句会後のお疲れも厭わずに全句講評をお送りくださった師の励ましの言葉や、句会の様子をそっと知らせてくれた句友たちとの繋がりがあったからこそ。俳句は座の文学だと言われるが、心と血が通ってこその座であると、しみじみ感じている。
(活洲みな子)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 宙ゆらぐ前に帰らん夏の闇 恩田侑布子(写俳)
====================
5月4日 樸俳句会
兼題はゴールデンウィーク、若葉。
特選2句、入選3句、原石賞1句を紹介します。
◎ 特選
吾の歌に母の輪唱桜の実
活洲みな子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「桜の実」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
天上の母はすこやか樟若葉
活洲みな子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「樟若葉」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
死にたまふゆびのささくれ夏みかん
見原万智子 【恩田侑布子評】 「死にたまふ」と、胸底に敬語で呼びかける人はどなたでしょう。ささくれた指から肌の乾燥し痩せ細った高齢の母を思います。母とは幼い日から夏みかんの厚い皮をむきあって、数限りない睦まじい時間を過ごしてきました。自分を産み育て、年老い、弱っていった愛しいその指はもう、くすっとも動いてくれません。しぶきのように迸る黄金の果汁に、ともに指先を濡らすこともありません。ややぶっきらぼうに投げ出された三段切れは茫然たる悲しみです。陽の色をした夏みかんの丸々した重量に、死者の指先の蒼ざめた硬直が哀切です。
○ 入選
母がりは永遠の緑陰なりにけり
益田隆久 【恩田侑布子評】 母はいつでも作者の憂悩を癒し、励ましてくれたやさしい方なのでしょう、まるで涼やかな緑陰のように。今も木陰を通り抜ける気持ちのいい風にくつろいでいると、ありありと母が甦ります。永遠に失われた肉体が、緑陰となって作者を待ってくれているようです。句末の「なりにけり」には文語のよさが発揮されています。ただ、「母がりは」はどうでしょう。上代は、母+接尾語「がり」で、母のもとへ、母のところへ、の意ですが、中古以降は助詞「の」を介し、「母がりの半日あまり桐の花 細川加賀」、「母許の廂の古りぬゑんど飯 永田耕衣」 などの先行句があります。「の」を介さない単独の名詞としての使用にはやや違和感があります。
○ 入選
木香薔薇あふれんばかり死者の庭
成松聡美 【恩田侑布子評】 一挙に咲き誇って、あたりを異様なまでの明るさにする木香薔薇の黄色のはんらんが、かえって死者の庭に合っています。「霊園」や「墓地」という言葉を使わなかったことで普遍性を獲得しました。その静寂に包まれて佇むことの不思議さ。初夏のひかりが迫ってきます。
【原石賞】夕若葉マーマレードの煮詰まるる
長倉尚世 【恩田侑布子評・添削】 庭若葉にはまだ充分に日があるのに、時計の針はすでに夕刻をさしています。作者はたぶん夏みかんのマーマレードでも煮ているのでしょう。柑橘類の香りが厨いっぱいに広がります。日永は春の季語ですが、実際には夏至が最も日が長いので、夕方でも暗くならない若葉の和らいだ色と、ジャムの黄味とが響き合います。ただし句末の文法は誤りです。助動詞「る」は「詰まる」に接続しません。鍋の中に焦点を絞れば実感が出ます。 【添削例】夕若葉マーマレードの煮詰まり来(く)
卯の花の谷幾すぢや死者と逢ひ 恩田侑布子(写俳)

2025年4月13日 樸句会報 【第151号】 2025年春の吟行は、恩田代表が「恩田侑布子の名句鑑賞」を連載し、会員の毎月の佳句が恩田の鑑賞付きで掲載されているご縁から、SNSアプリ「俳句てふてふ」代表兼編集長 今井竜様のご後援を得て、芭蕉がこよなく愛した近江(大津市)へ、泊まりがけで出かけました。
琵琶湖線膳所駅に集合し、最初に参詣したのは木曾義仲の胴塚と芭蕉の墓所が並ぶ義仲寺。池から上がってきた石亀が駘蕩と歩む姿が、これから始まる旅の案内役のように見えました。
近江野菜をふんだんに使ったランチを大急ぎで戴いてから堅田へ移動。出迎えてくださった今井様に、若き日の一休和尚が修養を積んだ祥瑞寺、琵琶湖に臨む満月寺浮御堂等をご案内頂きました。
この日は次第に風雨が強まり肌寒いほどでしたが、湖畔のカフェで身も心も温まり、かつて水上交通の要衝として栄えた街並みの散策を続けました。そして国指定の名勝 居初氏庭園へ。滋賀県観光協会の特別なお取り計らいで、園内の書院 天然図画亭の茶室で句会が催されました。素早くメモを取る恩田代表や観察に集中する連衆の熱意に力をもらい、吟行2回目の筆者も何とか五句出句という課題をクリアしました。
夕方からは比叡山の麓にある生源寺日吉大社・山王祭を拝観しました。大津在住の連衆が「今夜の神輿振りは見逃せませんよ」と教えてくれたとおり、豪壮な神事に魅了されました。
興奮冷めやらぬまま下山した我々を、今井様がご自宅へ迎え入れてくださり、湖岸に打ち寄せる波音を聞きながら夕餉を囲むという贅沢この上ない一夜を過ごしました。
打って変わって快晴の二日目。漁船に乗り込み、雁の群れ飛ぶ琵琶湖クルーズを満喫し、解散後は各自思い思いの名所旧跡へ足を伸ばしました。
連衆の一人が「素材がありすぎてかえって急には俳句が読めない」と呟いた今回の旅。感動はしばし醸成され、27日のzoom句会でも近江を詠んだ句がたくさん出されました。
旅程の企画、二日間のご案内役、さらに宴のご準備までもお世話になった今井様に、参加者一同厚く御礼申し上げます。
特選1句、入選3句を紹介します。
花の雲あの世の人ともやひつゝ 恩田侑布子(写俳)
◎ 特選
亀鳴くや巴御前の吐息のせ
金森三夢 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「亀鳴く」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
どうだんの衣広げり巴塚
見原万智子 【恩田侑布子評】 満天星の花が咲けば春もたけなわです。義仲寺の木曾義仲の宝篋印塔の傍には小さな自然石の巴塚があり、その上に満天星が覆いかぶさるように枝を広げ、ほころびかけていました。まどやかに剪定された植栽を巴の「衣」と見立てたあでやかさ。小袖を涼やかに広げた巴の颯爽たる風姿が浮かび、最高点句でした。作者は、「満天星」の漢字は、勇猛な巴御前には艶やかすぎると思ったのでしょう。ただ、「どうだんの花」なら間違いなく季語ですが、「どうだん」では「同団の衣」と読まれる心配もあり曖昧です。吟行句の難しいところ。
○ 入選
走り根へ春愁の雨たたきけり
益田隆久 【恩田侑布子評】 京都駅から膳所までは傘要らずでしたが、堅田は雨。町並みの落ち着いた水郷のたたずまいを傘越しに眺めて歩きます。満開の桜が雨に散りそめ、内湖にはちらほらと花筏。若き日の一休の修行寺を足早やに、浮御堂へ松の緑をくぐった後、「俳句てふてふ」代表の今井竜さんのご厚意で天然図画亭の庭園を散策し、茶室にて句会を。どこの何の木かわからなくても、仲間同士、次の場所へとはやる心に、まさに「春愁の雨たたきけり」。黒々とした走り根が見えてきます。
○ 入選
花冷や芭蕉に男色のうはさ
古田秀 【恩田侑布子評】 芭蕉は名古屋の若い米穀商だった杜国を終生愛し、その夭折を惜しみました。晩年の『嵯峨日記』でも、夢に見て「涕泣して覚ム」といい、みずからそれを性的妄想の「念夢」と名づけています。拙著『渾沌の恋人 北斎の波 芭蕉の興』冒頭にあるので、膳所駅近くのイタリアンでも、芭蕉のホモセクシャルが皆の話題になりました。合評では「噂に止まらないでしょ」という声が聞こえました。一理ありますが、俳句では「花冷や」が一句全体に響くため、「うはさ」くらいに措辞を抑えるほうが美しいのです。
【後記】
今回、帰りの新幹線の中ですぐにでもまた旅に出たいと思っている自分に気づきました。出不精だった筆者にもようやく「道祖神の招き」が届いたようです。
恩田代表から、筆者の句は吟行の場を離れるとやや映像を喚起しないかも、という指導を受けました。対照的に、今日の吟行で我々が見たものとしてはこの表現しかない、と評価された、他の連衆の句もありました。その吟行を離れても普遍的な説得力を持つと評されたのが特選句「亀鳴く」です。
家からどのくらい離れたら旅と言い得るのでしょうか? 旅に出れば作句の骨法その一「グリップ力」が強化され、いつか普遍性を持つ句を詠めるでしょうか? あぁ、そう言えば……窓外の夜景が明るさを増し、ずいぶん武蔵国へ戻ってきたと感じながら、筆者は『星を見る人』の一節を思い出していました。 人生は歩行だ。舞踊でも飛翔でもない。ましてや湯につかることでもない。駅へいつもの道を歩く。川のほとりを散歩する。見知らぬ遠い町を旅して歩く。そのとき、現実の風景と同時に感情の風景のなかもいっしょに歩いている。わたしたちの人生の同伴者はつねに感情である。(恩田侑布子著『星を見る人 日本語、どん底からの反転』p8、2023年 春秋社) (見原万智子)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) ふところは天上大風やまざくら 恩田侑布子(写俳)
====================
4月27日 樸俳句会
兼題は凧、藤。
入選1句、原石賞3句を紹介します。 ○ 入選
国境無き空へ帰らむいかのぼり
益田隆久 【恩田侑布子評】 「国境無き」の措辞からは「国境なき医師団」が連想されると同時に、世界各地の戦乱が思われてきます。前者は、一九七一年にフランスの医師やジャーナリストが設立し、一九九九年にノーベル平和賞を受賞した国際的な医療団体です。後者の戦火はやむどころか激しさを増しています。ロシアはウクライナの首都キーウまで爆撃し、イスラエルはガザで、罪もない子どもを17400人以上も殺しています。この句は、なぜ人は国境線を引き、領土のために人を殺すのかと問いかけます。「国境無き空へ帰」ろうとする凧は、純真な童心をもつ生身の作者の顔を想像させます。
【原石賞】畳みたる帆を花過の枕とす
古田秀 【恩田侑布子評・添削】 帆を畳んで枕にできるのは、きっとヨットを持っているおしゃれな作者でしょう。それを「花過の枕とす」るとは、ますますロマンチックです。ただ、七五五の頭でっかちなリズムが気になります。五七五の定型のうつくしい調べこそ、一句の内容に相応しいはずです。次のように語順を変えれば、花時に乗ったヨットの残像が、今なお胸の底の海か湖を、水脈を引いてすうっと滑っていくようではありませんか。 【添削例】花過のたたみたる帆を枕とす
【原石賞】天の凧追う子のわれも風となる
馬場先智明 【恩田侑布子評・添削】 子どもの凧が大空高く舞い上がりました、風に乗ってぐいぐい引っ張る「天の凧」をおさな子が一心に追いかけてゆくのを、父であるわれも追ってゆきます。その時、ああ私は「風」だと思う瞬間のなんたる気持ちの良さ。気宇の大きな俳句です。惜しいのは「追う子のわれも」の中七のまだるっこさです。この句は真っ二つにスパッと真ん中に切れを入れた方が良くなります。切ることで、親子の関係がイキイキした秀句になります。 【添削例】天の凧追ふ吾子われも風となる
【原石賞】薄茶汲むゆがむ玻璃ごし花吹雪
前島裕子 【恩田侑布子評・添削】 「薄茶」といっているので、「濃茶」と対になった、茶の湯の場面を思います。しかし「湯を汲む」といい「薄茶点つ」はいっても、「薄茶汲む」とは耳なれません。「ゆがむ玻璃ごし花吹雪」の十二音のフレーズは、あたかも谷崎潤一郎の『細雪』のように美しいシーンです。いまの工場生産ではない、明治か大正の板硝子は、わずかに景色の歪むところに味わいがあります。そのレトロな硝子を透かしてみる「花吹雪」だからたまりません。広間で茶筅を静かに振る気張らないシーンにすれば、いっそう優美さが匂います。 【添削例】お薄点てゆがむ玻璃ごし花吹雪
天心のふかさなりけり松の芯 恩田侑布子(写俳)

2025年3月9日 樸句会報 【第150号】 3月最初の句会、今治西高校2年の野村颯万さんが参加して下さった。第27回神奈川大学全国高校生俳句大賞・恩田侑布子賞受賞の高校生である。
YouTubeで、受賞句「早梅や連綿線の長き脈」を確認。素晴らしいと思った。書道技法講座『関戸本古今集 伝藤原行成』を改めて開いて確認する。長き脈を一気に引いた後、まるで梅を咲かせる如くゆっくりひらがなを咲かす。しかも早梅である。恩田先生が「早梅が動かない」と仰ったことに完全に同意。「梅」だけでも絵が浮かぶが、「早梅」とすることで、筆の動きと馥郁とした香りまで漂ってくる。脈から思い通りに文字を咲かせた時の喜び、満足感まで共感する。『関戸本』を習う時、野村さんの俳句を思い出すだろう。
今日の句会はあと3時間ぐらい欲しいと思ったほど。野村さんに感謝したい。句会に出した野村さんの俳句は、恩田先生の特選、そして最高得点句であった。 3月9日の兼題は「春の水」、「囀」。
特選2句、入選2句、原石賞1句を紹介します。 閃きはつばめの腹にこそあらめ 恩田侑布子(写俳)
◎ 特選
春水のつぶれぬやうに墨を磨る
野村颯(そう)万(ま) 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「春の水」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
パレットへ囀りの色溶きにけり
益田隆久 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「囀」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
囀りや石窯で焼く手ごねパン
岸裕之 【恩田侑布子評】 パンを「石窯で焼く」とは本格的。しかもパン練り機ではなく「手ごね」とは。
「囀りや」の切れから、木立ちの豊かなイタリア地方都市の朝が、映画のように浮かんできます。いかにも美味しそうです。
○ 入選
水茎のあの人らしさ花なづな
益田隆久 【恩田侑布子評】 「花なづな」の白い小さな花から、手紙なのか一筆箋なのか、恥ずかしげなやさしい初々しい筆跡が目に浮かびます。作者が好ましく思っていることも伝わってきます。「あの人らしさ」なので、まだそんなに間柄が深くなさそうなことも。花言葉は「あなたにわたしのすべてを捧げます」。作者の弁から、恋とは違う大切な旧友とわかりました。こんな同級生がおられるのは幸せです。
【原石賞】海賊の連歌一巻花月夜
野村颯万 【恩田侑布子評・添削】 勇壮な春の俳句です。中世には長連歌が流行りました。これはその二条良基の周辺で活躍した連歌師たちの高尚な連歌ではありません。「海賊の」といいます。そこが俳諧精神躍如たるところ。ただし、俳句という詩の表現を完成させるにはたんに意味だけでなく、言葉それ自体の質感が大切になります。「海賊」の措辞はバイキングを思わせやや乱暴で内容にそぐわないように思います。村上水軍や九鬼水軍が活躍した時代を彷彿させましょう。上五の質感を変えるだけで、さらに格調高い大柄句になります。 【添削例】水軍の連歌一巻花月夜
【後記】
巻尺を伸ばしてゆけば源五郎 ( 波多野爽波 『骰子』) 巻尺は、自分の価値観、そして表現すべき言葉。自分の巻尺には限界があり、自在に動き回る源五郎には届かない。初めて樸俳句会に出た頃、古田秀さんの俳句の良さがほとんどわからなかった。つまり、私の巻尺では届かない俳句に出会った。それが、自在に動き回る源五郎であろう。
自分の価値観、手持ちの言葉を超える俳句に句会で出会い、衝撃を受ける。恩田先生から、何十回とダメ出しをもらう。そのような、殴られるような経験を句会で積み重ねることで、自分の巻尺の可動範囲が拡がってゆく。一人でやっていたら、やがて言葉が枯渇する。
本を100冊読む以上に句会で鍛えられる方が、枯渇した言葉がまた充填される。これが、句会でしか経験出来ない醍醐味である。
(益田隆久)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 野遊びのつひに没日の海へかな 恩田侑布子(写俳)
====================
3月23日 樸俳句会
兼題は龍天に登る、たらの芽。
入選1句、原石賞4句を紹介します。 ○ 入選
春の暮真子の煮つけは反り返る
成松聡美 【恩田侑布子評】 真子は魚の卵巣で腹子ともいいます。ちなみに白子は雄の魚の腹にある精巣。たしかに卵塊は、包んでいる薄皮と収縮率がちがうせいか、煮ると反り返ったり破れたりします。これは鋭い着眼です。反り返って破れた袋から無数の魚卵の粒がはみ出す様まで想像させ、春の夕暮にふさわしい気怠い懊悩までも感じさせます。
【原石賞】龍天の涙壺より溢るるか
小松浩 【恩田侑布子評・添削】 「龍天に」までいえば季語になりますが、「龍天の」では季語になりません。ただ独特な発想が斬新です。「涙壺」から龍が飛び立つというふうにはっきりと表現すると、現代の戦乱の絶えない世界を象徴するみごとな現代俳句になります。 【添削例】涙壺より龍天に登りけり
【原石賞】多羅の芽の眼下鵜(う)山(やま)の七(なな)曲(まが)り
活洲みな子 【恩田侑布子評・添削】 近景の春の山菜と、中景から遠景へ伸び広がる景色の対比が効いています。大井川の蛇行のさまを一望する雄大な景勝地「鵜(う)山(やま)の七(なな)曲(まが)り」の地名をよく生かし切った句です。漢字がごちゃごちゃしているので季語はひらきましょう。「眼下」の措辞よりも身体感覚に響く「足下」を持ってくると、川底に向かう斜面から俯瞰した奥行きも出ます。 【添削例】たらの芽の足下鵜(う)山(やま)の七(なな)曲(まが)り
【原石賞】龍天に昇り昼夜は真半分
坂井則之 【恩田侑布子評・添削】 発想がユニーク。着眼の独自性に感心します。が、それを十分に生かしきれていないのが残念です。原句のままでは「龍天に昇り昼間と夜間がちょうど真半分になった」と、春分の時候の説明臭が残ります。俳句には謎が必要です。次のようにすれば、いま現在の酷い世界の闇の部分まで浮き上がりましょう。 【添削例】龍天に昇る昼夜を真つ二つ
【原石賞】龍天に登る柏槇の突兀
益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 柏槇は寿命の長い常緑針葉高木です。沼津の大(お)瀬(せ)崎(ざき)の柏槇樹林は樹齢千年ともいわれる国の天然記念物で、鎌倉には建長寺、円覚寺、浄智寺など、柏槇の大樹のある寺が多いです。中国では真柏(しんぱく)と呼ばれ、山東省曲阜市の孔子廟を訪ねた時にも、真柏が亭々と天に聳えていました。「突兀」の措辞によって、ねじれ曲がる複雑な樹肌が彷彿とします。その天へ伸び上がる大樹の勢いを活かし、「龍天に」で言い納めると大柄句になります。 【添削例】柏槇の突兀として龍天に
閼伽水にうかぶ白蛾や春の昼 恩田侑布子(写俳)

2025年2月23日 樸句会報 【第149号】 2月2回目の句会23日は、最長の寒波が日本列島を覆い、日本海側、北日本の屋根の雪おろし、めったに雪の降らない九州でも雪掻きをしている様子が、テレビに映し出されている。普段暖かい静岡でも北風が吹き寒い。
しかし私たちは、zoomというありがたいシステムがあるおかげで、北風の吹く中暖かい部屋で句会を開くことができるのです。
兼題は「春光」「辛夷」です。特選1句、入選2句、原石賞3句を紹介します。 雪解野や胸板は風鳴るところ 恩田侑布子(写俳)
◎ 特選
暮れてなほ弾む句会や花こぶし
益田隆久 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「辛夷」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
見はるかす白馬三山花こぶし
岸裕之 【恩田侑布子評】 名峰白馬岳は・杓子岳・白馬槍ヶ岳へと尾根を縦走する登山者も多く、白馬三山と総称されます。三〇〇〇メーロルに迫る北アルプスの高峰で高山植物の宝庫です。途中には大雪渓があったり、山頂からは日本海が見えたり、白馬槍には徒歩のみで行ける温泉があったり、登山家の聖地です。作者はかつて白馬三山を踏破したことがあったかもしれません。あるいは私のように、永遠の憧れの高嶺なのかも。とまれ、清らかなこぶしの花越しに望む、その名もうるわしい白馬三山の雄峰は早春の絶景です。「見はるかす」の措辞が盤石。
○ 入選
青空に挑むじやんけん花こぶし
活洲みな子 【恩田侑布子評】 肌寒い早春の青空に向かって、真っ白いこぶしの花がじやんけんを挑んでいるよ。グーもパーもチョキもあるよ。こぶしの花に向かう童心が躍っています。いや、ほとんど花こぶしの気持ちになりきっているといっていいでしょう。作者の周りはこれからきっと、明るい気持ちの良い日々になるに違いありません。
【原石賞】こぶし咲く「れ」の字空へと散りばめて
長倉尚世 【恩田侑布子評・添削】 写生眼が素晴らしいです。そういわれてみればたしかにこぶしの花が「れ」の字に見えてきます。句の弱点は中七にある「へと」。ここで急に説明臭くなってしまいます。一字を入れ替えるだけで、にわかに句の景色が明るくなりませんか。余談ですが、子どもに白木蓮とこぶしの花の見分け方を聞かれたら「れの字に見えるほうがこぶしの花で、見えないのが白木蓮だよ」と、自信を」もって教えてあげられそうです。 【添削例】こぶし咲く「れ」の字を空へ散りばめて
【原石賞】踏まれるも下萌の香の高くあり
益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 春先に萌え出たばかりの下草を踏んでゆきます。そのとき、目には留まらないが、独特の香りをもつものがあるなあと、素直に思ったのです。目のつけどころが素晴らしい俳句です。これは、発想の契機とも、俳句のグリップ力ともいう、一句の根をなす作者の心位であり、教えて教えられるものではありません。各人が精神を涵養しなければ把握できないものです。あとは、句作の最終段階である表現の問題になります。たった二字を変えるだけで格調の高い素晴らしい俳句として完成します。 【添削例】踏まれたる下萌の香の高くあり
【原石賞】春光を睨み返さむ天井絵
岸裕之 【恩田侑布子評・添削】 面白い句ですが、肝心の主体が抜けています。作者自身には「龍」が睨んでいることが自明なのでしょうが、読者はそうはいきません。八方睨みの龍の絵は京都の天龍寺や妙心寺や、枚挙にいとまないですが、変わったところでは北斎晩年の、小布施の祭屋台天井絵もあります。しっかりと「龍」の主体を打ち出し、「睨むや」と切字で余白を大きくしましょう。春光に今にも龍が躍り出しそうになりませんか。 【添削例】春光を睨むや龍の天井絵
【後記】
今回もいろいろな意見、疑問、質問がとびかい白熱した句会となりました。
その中で、兼題の「辛夷」の句に、「辛夷は咲いていない。実物を見ていない。それは机上の句ではないか。それでもいいのか。」というような質問が出された。確かに私もあちこち辛夷を探したのですが、咲いていなかった。
それに対して先生は「過去もふくんだ今を一句の中にとけあわせる」とおっしゃった。ふむ。ふむ。
森澄雄の句に、「ぼうたんの百のゆるるは湯のやうに」がある。牡丹はあらかた散っていたという。
「(略)見てないから、牡丹がみえて、そのふくらみまで見えてくるんでしようね」と澄雄は言っている。( 『新版現代俳句下』山本健吉著、1990年 角川)
この句を句会の最中に思い出しました。
句会は句作のヒントがたくさん。まだまだヒントがあったように思いますが、まずは今回の先生の講評を読み句会を振り返ってみようと思います。
(前島裕子)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 死にかはり逢ふ白梅の日と翳と 恩田侑布子(写俳)
====================
2月9日 樸俳句会
兼題は猫の恋、ヒヤシンスでした。
入選3句、原石賞1句を紹介します。 ○ 入選
吾の術日母には告げず風信子
活洲みな子 【恩田侑布子評】 手術を控えた身はなにかと不安なもの。子ども時代ならば両親がすべて心配してくれ甘えられたのに、いまは立場が逆。老いた母をこちらが心配する番です。といっても、母親に五体満足で産み育ててもらった身体に、初めてメスが入ることを本当は打ち明けたいのです。昔のように母からひとことでいいから慰め励まされたい。とまどい疼く思いが風信子のうすむらさきの春光に揺らいでいます。
○ 入選
ヒヤシンス手付かずの明日ありし窓
益田隆久 【恩田侑布子評】 小学校三年生でしたか。「水耕栽培」を習った驚きはいまも新鮮です。げんげもチューリップもマーガレットも、花はみな土の上に咲くと信じていましたから。教室の大きな窓際にクラスメイトの名札をつけたヒヤシンスのガラス瓶がずらあっと並んだ日。ほんとに咲くかしら、どんな色かしらと友だちと想像し合ったよろこび。そこにはみんなに平等な「手付かずの明日」がたしかにありました。「明日ありし窓」と過去の記憶なのに、「ヒヤシンス手付かずの」という上半句によって、触れ得ぬみずみずしい未来が、水中を透過する光の感触とともに伝わってきます。
○ 入選
立春や逆さ葵の菓子を買ふ
長倉尚世 【恩田侑布子評】 徳川家康の御紋章は三つ葉葵ですが、東照宮の拝殿垂木には逆さ葵がわざわざ金泥で描かれています。ネット上では「建物をわざと未完成にするため」で、仏教思想由来と説明されますが、本来は老荘思想でしょう。先日、イチローが殿堂入りした折に、満票でなく一票欠けたことを、「さらに努力し続けるのが好きだから嬉しい」とコメントした立派な人柄も思い合わされます。『老子第四十一章』には「上徳は谷の如く、大白は辱(はじ)の如く、廣徳は足らざるが如し」があり、「大器晩成」という四字熟語につながってゆきます。『荘子』斉物論にも「其の成るや毀(こわ)るるなり」の言葉があります。家康は幼少期に臨済寺で漢籍の素養を深く積んだ人でした。
【原石賞】ヒヤシンス登校しない子の鉢も
見原万智子 【恩田侑布子評・添削】 クラス全員に一株ずつヒヤシンスの球根が与えられ、育てています。「不登校」でなく「登校しない子」とやさしくいったことで、どうしてだろう、病気で入院しているのかしら、不登校なのかしらと、いろんな想像がふくらみます。「鉢も」だと土植えですが、「瓶も」とすれば、音韻に春の寒さが加わり、ヒヤシンスの繊い根がガラスの水底へ伸びてゆく姿も浮かび、顔の見えない子を思いやる淋しさが余韻となって残ります。 【添削例】ヒヤシンス登校しない子の瓶も
夜の梅さかさ睫毛を抜かれつつ 恩田侑布子(写俳)

2025年1月26日 樸句会報 【第148号】 1月2回目の句会は静岡市内での対面句会となりました。雪化粧の富士山を窓の端に置きながら、普段のZoom句会とは違う刺激に、鑑賞も議論も心なしかヒートアップしていました。聞くところによるとZoomと対面のコミュニケーションでは刺激を受ける脳の部位が異なるそうです。
兼題は「氷柱」「冬菫」です。特選1句、原石賞2句を紹介します。
白鳥の胸裹(つつ)まむとうるし闇 恩田侑布子(写俳)
◎ 特選
寒声や師匠口ぐせ「間は魔なり」
岸裕之 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「寒声」をご覧ください。
↑
クリックしてください
【原石賞】空と吾が語らふさんぽ冬菫
山本綾子 【恩田侑布子評・添削】 「ソラトアガ」または「ソラトワレガ」と訓ませるのでしょうか。内容にふさわしいリズムにするにはギクシャクした「ガ」を外して内容の繊細さを生かしましょう。一音の違いで雰囲気が一変し、冬青空がさあっとひろがります。 【添削例】空と吾の語らふさんぽ冬菫
【原石賞】なりゆきのままに一世や大つらら
活洲みな子 【恩田侑布子評・添削】 ユニークな把握を買います。上半分はズボラっぽい生き方。ところが、つもり積もってというか、垂れしたたってというか、結果は「大つらら」になりました。変身ぶりに驚かされます。せっかく句の捻りに力があるので、ひらがなでやさしく流してしまわないで、漢字表記でキリッと納めればおおらかな作者の存在感が出て出色の句になります。 【添削例】なりゆきのままに一世や大氷柱
【後記】
句会のあとは懇親会。持ち寄りの紹興酒や世界一周旅行のお土産つき抽選会を楽しみながら、俳句談議に花を咲かせます。年齢も性別もバラバラで、芸能や流行の話は通じ得なくても俳句の話は延々としていられます。個人的なことですが、北斗賞受賞の祝賀会を兼ねた場でもあり、「俳人の価値は現世の俳壇スター的活躍ではなく、どんな句集、どんな一句を遺せたかがすべて。死後読み返される俳人にならないと」との言葉に思わず背筋が伸びました。マンネリズムや自己模倣に陥らないよう、新しさとシビアさをもって今の時代を書いていきたいです。
(古田秀)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 金平糖角の頂冬うらら 恩田侑布子(写俳)
====================
1月12日 樸俳句会
兼題は食積、初詣でした。
特選1句、入選2句、原石賞1句を紹介します。 ◎ 特選
ほそき手の床より賀状たのまるる
長倉尚世 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「賀状」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○ 入選
床の間に祖母てづくりの手毬かな
前島裕子 【恩田侑布子評】 彩とりどりの絹糸で手毬をつくられるとは、誠実に生きて年を重ねられた祖母の端正な佇まいを彷彿とさせます。そのおばあちゃんの丹精こめた手毬を家のいちばん大事な床の間に飾る家族じゅうの敬愛の情。品格あふれる新年詠です。
○ 入選
紅白なます太箸の棹さすごとし
古田秀 【恩田侑布子評】 紅白膾を豊かな海波に見立てた意外性。しかも新年の、柳箸とも祝箸ともいう「太箸」を「棹さすごとし」とみた大胆な直喩の面白さ。蛋白質主体のご馳走責めの中で、大根とにんじんを細く切った清らかな酢の物はさっぱりとして、箸が進みます。気持ちの良い食欲と相まって健やかな新年詠です。上五の字余り七音と中七の句またがりにクセがありますが、それも作者のいい意味の個性が出たおおらかさでしょう。
【原石賞】三方は杉の香潔く鏡餅
林彰 【恩田侑布子評・添削】 杉の香りは檜の香りとまた一段違います。上質な杉の白太でできた古式ゆかしい三方でしょう。ただ、潔いは、美しい、淋しい、悲しいと同じく、感想を「謂い応せ」てしまった感があります。また「潔く」は形容詞の連用形で鏡餅を修飾してつながるので、中七に切れが欲しいです。修飾語ではなく動詞にすると歯切れも良く、格調も高くなります。 【添削例】杉の香のたつ三方や鏡餅
わが視野の外から外へ冬かもめ 恩田侑布子(写俳)

2024年12月22日 樸句会報 【第147号】 12月22日の兼題は「ボーナス(年末賞与)」と「鰤」。ボーナス体験は個々人でまさに悲喜交々。「悲喜」どちらを詠んでも、詠み手の想いが伝わってくる句ばかりだが、私などどちらかといえば縁なき者の哀感を詠んだ句に共感してしまうのは、先生同様、その恩恵に浴することのない半生だったからだろう。「鰤」では、季節感を多彩に詠みこんだ多くの句が並んだ。この兼題では詠めなかった私自身の食生活の貧困(無知)を深く恥じると同時に、季語が包みこむ日本人の生活感に疎いのはかなりまずいと反省した。会の後半には、武藤紀子さんの句集『雨畑硯』より先生抄出の15句についてそれぞれ感想を求められた。「どう思いますか」と鋭い刃を突きつけられたように問われ、一同しばし沈黙。私自身言葉が出ない。先生が三行で書かれている評言が全てを尽くしている。それを超える言い方などできようはずもない。鑑賞の言葉(も)鍛えねばならないと切に思った。
入選2句、原石賞1句を紹介します。
○ 入選
聖夜来るマッチ知らない子供らに
成松聡美 【恩田侑布子評】 アンデルセンの童話「マッチ売りの少女」を連想します。少女は貧しさから、年の瀬の雪の中、マッチを売ってくるよう言いつけられ、売り物である小さな火に幻想を見ようとして、すべてを擦って死んでゆきました。
掲句の「マッチ」は、現実のマッチであるとともに、ひと時代前の日用品の隠喩でしょう。現代は手紙の代わりにSNSが、本や新聞の代わりにネット情報が、図書館で調べものをする代わりにチャットGPTが、なんでも教えてくれます。こうした文明批評が底にあることが句柄を大きくしています。はるかな時間の流れの中では、現代人といっても、次から次へ物質文明の奔流をわたり漂う「マッチ知らない子供ら」のように思えてくるのです。二千年前に降誕した聖夜のキリストが、子供たち、即ちわたしたちをひとしなみに見つめています。
○ 入選
煎餅を添へてボーナス渡さるる
長倉尚世 【恩田侑布子評】 この「ボーナス」の袋はそんなに厚くはなさそうです。袋の上から手で触れて、万札のおおよその厚みがわかった昭和の時代の情景です。夫は「少ないボーナスでわるいね」という代わりに、妻の好物であるに違いないカリッパリッと歯ごたえのいい厚焼きせんべいのふっくらした袋を添えて手渡してくれたのです。なんとやさしい夫婦の暮らしぶりでしょう。心温まる俳句です。
【原石賞】花八つ手顔より声を想い出す
成松聡美 【恩田侑布子評・添削】 八手は地味な花。冬日の玄関の脇や、トイレの窓の外にひっそりと白ばんだ花を咲かせます。よく見れば、ベージュがかったやさしいボンボンを思わせますが、ハッと目を引くところはどこにもありません。ただその花がものかげに佇んでいるのを見ると、好きだった人の声を思い出してしまうのです。目鼻立ちはもうぼうっと定かではないのに、声の静かな温もりだけがありありと耳の底に聞こえるのです。原句は「想い出す」で終わり、存在感が弱まります。座五を「花八手」にすることで、その人のかけがえのない声音が印象されましょう。 【添削例】顔よりもこゑおもひだす花八手
【後記】
今句会で一際目立ったのが、成松さん句の高評価。3句すべてに先生の「入選」「原石」「サンカク」が付けられ、メダル独占の様相だった。ただ私はこの3句には全く感応せず、先生の講評を聞いてのち、ようやく自分の読みの浅さに気づいた次第。作者の意図を超えて深読みさせたくなるような句を、いつか私も詠んでみたいと心に誓う。先生の講評は毎回一言ひとこと俳句初心者の私の頭と胸に沁み入る。しかし今回は染み入る猶予もなくいきなりグサッと突き刺さった言葉があった。「“他人事” 俳句ではダメ! 最後は自分の足元に着地させること」。ああ痛い! そもそも樸入会のきっかけともなった『星を見る人』に魅了されたのも、行間から同じトーンの叱声が聴こえたからだ。私の中で生活習慣病の如く巣食っている “他人事” ことばの使用。後半生の残り時間で、どこまで矯正できるか……。樸俳句会という虎の穴に足を踏み入れたことは今年一番の収穫だと思っています。
(馬場先智明)
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
====================
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。