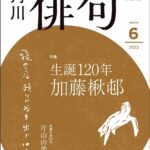
恩田侑布子は、これから先もずっと、守りに入ることはないでしょう。 ささやかな営みが描かれていると思いきや、ふいに大きな決意を目の当たりにしたかのような。『俳句』6月号掲載の「八風」は、これまでの恩田作品にも見られた重層性がいちだんと際立つ、AIには決して読み解けないであろうと思わせる21句です。 五感のすべてで受け止めぜひ感じてください、いのちの色、音、匂い、味、そして痛みを。 『俳句』2025年6月号のご購入はこちらから
樸俳句会からの新着情報をお知らせします!

(YouTube「俳句の百科事典 ハイクロペディア」より) 夢のような「酔眼朦朧湯煙句会」に遊び、俳句の楽しさに酔い痴れた若き日。その句会で詠んだ「ジーンズに腰骨入るる薄暑かな」をはじめ、半生を振り返ったとき、忘れ得ない句がいくつもあるという。そのうちから十句を厳選し、語り尽くした「恩田侑布子自選十句」。春の一夕、名聞き役の蜂谷一人氏(元NHK俳句ディレクター)を自宅にお迎えして収録したものをご厚意に甘え当会HPにても公開いたします。 蜂谷一人氏を江戸期の古民家である自宅にお迎えして YouTube ハイクロペディア「恩田侑布子自選十句」より 1 ジーンズ 2 茅の輪振る 3 銀の鱗 4 月の川なりに 5 河童の皿 6 ぼんくらの恋 7 長城に白シャツ 8 告げざる愛 9 天のたゆたふ 10 初富士 --*--*--*--*--*--*-- 蜂谷一人氏の暖かいお人柄に触れ、少女のような饒舌さで自句を語る恩田侑布子ですが、樸俳句会での指導においても、その熱量は何ら変わりません。圧倒的な知識と天衣無縫な想像力が産み出す恩田の鑑賞は、時として作り手の意図を超える次元へ一句を引き上げます。樸会員になると、あなたの俳句に恩田侑布子の鑑賞がコラボするトキメキが味わえます。 樸の活動は月2回のZoom句会がメイン。これから俳句を始めたい方大歓迎のアットホームな会です。無料体験はこちらから
古田秀、第15回北斗賞受賞!
このたび、樸会員の最若手古田秀さんが、株式会社文學の森主催の北斗賞(40歳までの作品150句を対象)にかがやきました。『月刊 俳句界』2025年2月号に自選30句と受賞の言葉が掲載されています。
選考にあたられた野中亮介先生、堀田季何先生、阪西敦子先生に、樸一同深く感謝申し上げます。秀さん、今までの弛まない努力が実り、おめでとうございます。
なお、本号の巻頭特集「俳句という芸術」に、恩田侑布子が拙稿を寄せておりますので、併せてご高覧いただければ幸いです。
受 賞 の こ と ば
ずっと目標にしてきた北斗賞に、4回目の挑戦で手が届きました。時期尚早か、満を持してか、どちらの気持ちもありますが、句集出版に向けて全力を尽くしたいです。コロナ禍の直前に滑り込むように樸の門を叩き、どんなときも正直で率直で容赦のない恩田先生の審美眼を頼りに俳句を続けて来られたこと、本当に幸運だったと思います。恩田先生、樸俳句会の皆さま、本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
古田 秀(ふるた・しゅう)
1990年北海道札幌市生まれ。
2020年樸入会。
22年全国俳誌協会第4回新人賞。
24年第3回鈴木六林男賞受賞。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
我が国を代表する仏教学者 末木文美士先生(東京大学名誉教授・国際日本文化研究センター名誉教授)が、恩田侑布子の近著『星を見る人 日本語、どん底からの反転』(春秋社、二〇二三年)へのご書評「俳句は近代を超える」をお書きくださいました。
俳句は近代を超える 末木文美士
恩田侑布子は俳句の実作者として意欲的な句集を次々と上梓しているが、その一方で力の籠った評論活動もまた、評価が高い。『渾沌の恋人(ラマン) 北斎の波、芭蕉の興』(春秋社、二〇二二年)は、卓抜の芭蕉論を含め、ぐいぐいと引き込むような力強い文章で、俳句論からスケールの大きな文明論にまで展開していった。それに対して、今回の『星を見る人』は、様々な機会に書かれた比較的短い文章が、文字通り星のように並べられ、煌めいている。それだけに前著の雄大な構図に力負けした読者でも、読みやすく、楽しめる内容になっている。
短編の集成と言っても、無秩序に並べられているわけではなく、しっかりした構成をもって一冊が筋の通った作品となっている。最初(Ⅰ)は石牟礼道子。本書の幕開けであると同時に、そこに本書のエッセンスがギュッと詰まっている。
「いま・ここ・われ」は、近現代俳句の合い言葉であった。みっちんの俳句はそこからなんという遠い地平、なんという広やかな海と山のあいだに湛えられていることであろうか。(本書、一八頁)
石牟礼論のこの最後の一文は、本書全体のテーマということができる。それは、著者が俳句の実作者として目指してきたものでもある。石牟礼に託して、「いま・ここ・われ」という近代を超えようとする著者自身の営みが端的に要約されている。
石牟礼論に続いて、Ⅱでは草間彌生と荒川洋治が取り上げられる。その中で、著者が詩歌の本質とする「興」が論じられる。この古典的な詩論の用語が、単なる技法としての隠喩に留まらず、まさしく近代を超える根本の秘法として甦る。それは具体的にどのようなことであろうか。
ここで、この章で表面的な主題として掲げられていないもう一人の影の主役に注目したい。それは、早逝した同時代の俳人攝津幸彦である。本書で取り上げられた数多くの俳句の中で、私にとって最高の一句との出会いがここにあった。
紙の世のかの夜の華のかのまらや
恩田の的確な鑑賞にもう一言加えるならば、ここに江戸の春画を重層させてもよいだろう。二次元の紙の世界に、不自然なまでに誇張された性器を結合したまま永遠に固定された男女。それは乱歩の「押絵と旅する男」とも重なるかもしれない。恩田の言う「興」の典型をここに見るのは間違いとは言えまい。
Ⅲ以下が、いわば本書の本論である現代俳句論であり、多数の現代俳人の作品が次々と取り上げられる。俳句に疎い私などにとって、まったく知らなかったこんな絢爛たる世界があったことに驚かされ、次々と供されるご馳走をお腹いっぱい味わわせてもらう。いわば「恩田侑布子的現代俳句入門」とも言ってよさそうだ。だがその際、Ⅰ・Ⅱが前提となっていることを忘れてはならない。恩田の目は、近代の延長としての「現代俳句」ではなく、「いま・ここ・われ」の近現代を超える俳句の可能性に向けられている。著名な俳人たちが取り上げられても、その目の付け所は一貫している。
例えば、Ⅲの久保田万太郎。岩波文庫の『久保田万太郎俳句集』を頂戴した時、恩田と万太郎がどこで結びつくのかと、驚きを禁じ得なかった。そして、その解説の周到で充実した筆致に再度驚くことになった。古臭い江戸趣味の忘れられた劇作家万太郎は、恩田の手で近代を超える俳句作者として甦った。本書のⅢは、その解説で書ききれなかった鬱憤を晴らすかのように、万太郎の俳句に縦横にあらゆる方向から光を当てていく。今はその詳細に立ち入る余裕はないが、漱石の「低徊趣味」や虚子の「客観写生・花鳥諷詠」が批判され、芥川の「歎かひ」の俳句という万太郎評価を覆す、と言えば、その方向は明瞭であろう。
本書の中心となるⅣからⅧまでの俳人論・俳句論をあえて一気に飛ばして、結びとも言うべきⅨ以下に移ることにしたい。何とも乱暴な書評をお許しいただきたいが、理由がないわけでもない。Ⅰ・Ⅱで本書の主題が提起されたのに対して、Ⅸ以下では、ここまで取り上げられた現代俳句の世界を、さらに大きな視座で見ていくための道具立てが開示される。
Ⅸは、近代俳句の巨匠とされる中村草田男を、成功者となった頂点の時期を否定し、芭蕉とニーチェに霊感を得た初期に戻ることで見直しを図る。それはそのまま近代が失ったものの再発見である。そこからⅪの芭蕉の『笈の小文』の再読につながる。
著者自身「新説」と呼ぶように、『笈の小文』を杜国との濃密な愛の紀行として読みなおすのは、『渾沌の恋人』の目玉でもあった。それを改めて本書の結びに据える。著者は『おくのほそ道』のみを称賛する芭蕉観を「近代の理性偏重からもたらされたもの」(本書、二四四頁)と切って捨て、『笈の小文』を「コクのあるゆたかな感情の復権を告げる俳句紀行として、まったく新しいステージに立っているように思える」(同)と評価する。それは、芭蕉観の転換であるとともに、近代を超えて次に向かおうとする著者が、感情という古くかつ新しい武器を手に入れたことの宣言でもある。
順序が逆になるが、Ⅹの井筒俊彦論は、本書の中で唯一抽象的な哲学論に立ち入る。それは、次の芭蕉論の感情の再発見につながるという位置に立つ。井筒のマーヒーヤとフウィーヤという二つの本質論は、私も最近注目している。文学でもそうだが、宗教でも結局のところ、自己の奥にどこまで深く食い込めるかというフウィーヤ的な探求以外には道はない。ただ、それが内なる本質としてのフウィーヤで止まって固定化されてしまうとしたら、行き止まりの袋小路に過ぎない。その袋小路の底が破れるとき、どうなるのか。著者はそれを「無」と表現するが、それは再び近代の陥穽に陥る危険がないだろうか。むしろ私たちがその底で出会うのは未知なる他者ではないのか。私たちは外ではなく、内で真の他者と出会うのではないだろうか。
書評を超えて勝手な私見に入り込んでしまったが、もうひとつ著者が否定する方向の可能性を考えてみたい。それは、草田男や芭蕉の月並み化の問題である。芭蕉と言えば「古池」と「蛙」。その陳腐な通俗化が、芭蕉をつまらなくしたのは事実だが、それが意外にも日本人の感性の底に沈んで古層化したとも言えるのではないだろうか。古典とはそういうものだが、とりわけ覚えやすい短詩である俳句はそれが著しい。前衛化と通俗化の両極から俳句という文芸を考えていくことができそうだ。
※『神奈川大学評論 第105号』より転載。
末木先生から思索を促す洞察に満ちたご高文を賜りましたこと、感謝の念に堪えません。
転載をお許しいただいた神奈川大学 企画政策部広報課様にも、厚く御礼申し上げます。
(樸俳句会一同)
『星を見る人』の最終章で恩田は、芭蕉の『笈の小文』が宗達作『扇面散屏風』の形式を構想して書かれた可能性について触れています(XI、p236)。本書全体の構成が、こだわりなくたくさんの扇面(俳句作品)を散らしたようにも見え、俳句を鑑賞する楽しみを味わえる評論集という印象を受けます。
しかしそこには「絵巻のよう」と激賞された前著『渾沌の恋人(ラマン)』から一貫する主張があり、恩田があるものを希求し続けた闘いの記録、という見方もできるでしょう。さらに、自己探究の手がかりを与えてくれる書でもある…(編集委員・見原万智子)
初めての楽しい俳句講座 古今の名句鑑賞とともに 〜秋〜〈午前クラス〉 | 恩田 侑布子 |[公開講座] 早稲田大学エクステンションセンター
初めての楽しい俳句講座 古今の名句鑑賞とともに 〜秋〜〈午後クラス〉 | 恩田 侑布子 |[公開講座] 早稲田大学エクステンションセンター
7月11日(木)〜
恩田侑布子「初めての楽しい俳句講座」開講