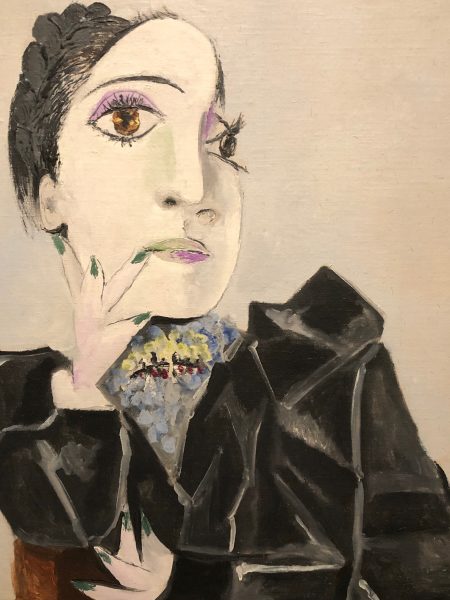2024年3月3日 樸句会特選句 書き込みに若き日のわれ朧月 小松浩
書架から久しぶりに取り出した本を開くと、余白のところどころに、忘れていた書き込みがあります。思わず目が吸われて読んでしまいます。あれ、こんなこと考えていたのか。若き日の自分の心を覗いて、当時の暮らしまで朧月のようにぼうっと蘇るのです。季語が季節感を超えて、一句全体に浸透していることが秀逸。それが「若き日のわれ」のいのちと響き合います。昔の自分が春月のように虚空にまどかに浮かんで、いまの「われ」を見つめています。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2024年1月27日 樸句会報 【第136号】 2024年は、能登半島地震の発生に始まり、正月だからといって平穏ではないという自然の厳しさを突きつけられた気がします。
安否を気遣う、支援に協力するといったことの他に、忘れずにいるということも私たちにできることの一つ。俳句という表現を借りて、今の想いを心に留め置くことも必要なことだと感じています。
1月27日の句会は静岡市でのリアル句会となりました。参加者からも欠席投句からも力作が寄せられました。
兼題は「春待つ」「鯛焼」「笹鳴」、特選1句、入選4句を紹介します。
◎ 特選
鯛焼のしつぽの温みほどの恋
小松浩 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「鯛焼」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
文具屋に桃色多し春を待つ
星野光慶 【恩田侑布子評】 「文具屋に桃色多し」は端的かつ印象鮮明です。書店と同じように、街の文房具屋もいつの間にかめっきり減ってしまいました。そんなご時世でも、この文房具屋さんはがんばっています。明るい桃色のポップ手書きがそこここに貼ってあったり、立っていたりします。自然の中ではなく、都会の中で見つけた待春の情景が生き生きしています。調べも上品です。
○入選
抱きしめるだけの介護や春を待つ
活洲みな子 【恩田侑布子評】 病床にある肉親でしょう。抱きしめてやることだけしかできない介護。切ないですね。でも、介護される方にとっては、きっとそれ以上安心できるひとときはないでしょう。春が来れば、車椅子でも外に連れ出してあげられそう。早く春の暖かな日がやって来ますように。心を合わせて待っている二人の姿が彷彿とします。
○入選
テトラポッドひとつに一羽冬鷗
長倉尚世 【恩田侑布子評】 冬の真っ青な海原を背景に消波ブロックが突兀と横たわっています。よく見るとその一つ一つのツノに冬鷗が止まっているではありませんか。はっきりと目に見えてくる映像です。かつての白砂青松が失われて久しい、渚の痩せた日本の浜辺の、乾いた冬の抒情です。
○入選
山里のリハビリ棟や雪笹子
都築しづ子 【恩田侑布子評】 山里にある静かなリハビリ専門の病棟です。長期入院者、あるいは長期通院者が多く、身体機能の回復訓練をする患者さんの地道な努力の暮らしが営まれています。「雪笹子」の季語が美しく効いています。夜来の雪に薄化粧をした裏藪からチャッチャッチャッと、足踏みするような笹鳴が聞こえてくるのです。すこしさみしいけれどやさしい、山里のたしかな応援歌です。
【後記】
樸では3ヶ月に一度リアル句会を行っています。今回は静岡市の小料理屋を会場に新年の句会が開かれました。一人二人と会場に集まる毎に自然と会話が生まれ、掘り炬燵に足を入れての句会は和気あいあいと始まりました。
今回の兼題「笹鳴」は、街中ではなかなか体験することの少ないお題です。難しかったという参加者の多い中、「ビル風の奥底に聴く笹鳴よ」と詠まれた方がいらして、師の目にとまりました。東京の中心地にお勤めの方の句で、お話を伺っていると、摩天楼のような都会の景色の中にふと私にまで笹鳴が聞こえてきそうな感覚になりました。
樸には少しずつ遠方の会員が増え、詠まれる景色も広がっています。いつか一堂に会して句会が開けたら楽しいなあと思っています。 (活洲みな子) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
==================== 1月13日 樸俳句会
兼題は「叔気」「初暦」「獅子舞」です。
入選2句、原石賞5句を紹介します。
○入選
獅子舞に噛まれしと児のよくしやべる
活洲みな子 【恩田侑布子評】 瞬時に、獅子舞に噛まれて興奮冷めやらないおさな児の姿が浮かび上がります。去年なら、ただ泣き叫ぶばかりだったかもしれません。怖かったのに泣かずにその時のことを伝える成長ぶりに親は目を細めます。ふだんは訥弁の子が、今、自分の知っている最大限の言葉を使って、食われるほど大きく感じた獅子の金歯を、その硬さを、夢中で両親や祖父母に訴えている微笑ましさ、めでたさ。
○入選
倒壊の家にもありし初暦
天野智美 【恩田侑布子評】 二〇二四年は震度七の能登半島地震で明けたようなものです。画面に流れる家屋倒壊と、大火災、津波の映像に胸を潰しました。作者はそこに今まで穏やかな日常を営んでいた人々の暮らしを思いやっています。梁や屋根に押し潰された居間にかかっていたに違いない初暦が何と生々しく無残に感じられることか。一瞬にして断たれた平穏な暮らしの象徴としての「初暦」です。
将来句集を編むときには、「二〇二四年を迎ふ」という前書きがあるとなお良いでしょう。
久能山東照宮
【原石賞】千百段昇りきりたる淑気かな
活洲みな子
【恩田侑布子評・添削】 他県から来る観光客は久能山東照宮を参拝するのに、よく日本平からロープウェイに乗ります。地元の作者は久能の有度浜側から九十九折の石段を上ったのでしょう。「いちいちごくろうさん」と覚えられている一一五九段を「千百段」とすっきり省略したのも手柄です。ロープウェイではなく自分の足で社殿まで行けた初詣のよろこびをさらに躍らせるには、「きりたる」の固い文語表現を、「きつたる」という弾む息遣いにしましょう。俳句は韻文なので、気息が大事です。内容はおなじでも迫力が変わります。 【添削例】千百段昇りきつたる淑気かな
【原石賞】 義母 ははとゐて母を思ふる初明り
山本綾子
【恩田侑布子評・添削】 古語の「思ふ」は「はひふふへへ」と活用しますから「思ふる」は誤り、正しくは「思ふ初明り」です。
連れ合いのお母さんと一つ屋根の下で新年を迎え、自分の母とではないことをしみじみと実感します。自分を産み育ててくれたこの世でたった一人の女性を恋う思いが泉のように胸をひたすのは、清らかな「初明り」のなせるわざでしょう。 【添削例】義母ははとゐて母を思ひぬ初明り
【原石賞】玉砂利を靴底に聞く淑気かな
島田淳
【恩田侑布子評・添削】 神社の境内を神籬ひもろぎといい、拝殿までよく玉砂利が敷かれています。その美しい小石を踏み鳴らす瞬間を「靴底に聞く淑気」と捉えた感性は見事です。ただ微妙なことを申すと、もったいなさがあります。原句ではまず「玉砂利」が出て次に「靴底」となるので、せっかくの玉砂利の明るい清らかさが濁ってしまうのです。そこで、まず「ふみゆける」と、足元に神経を集中させ、次に「玉砂利」の白さを出し、畳み掛けるように細石の鳴る音を「聞」けば、まさに淑気が四囲に響きわたるではありませんか。 【添削例】ふみゆける玉砂利を聞く淑気かな
【原石賞】その人は赤のカシミアその淑気
林彰
【恩田侑布子評・添削】 意外な場面の淑気。句に鮮度があります。ただし、「その」「その」のリフレインはたどたどしい。なんといってもこれは恋の句。「赤のカシミアの」映える女性の佇まいに「淑気」まで覚える作者です。非の打ちようもない美しさに圧倒されているのです。いつも胸の底に住まう人であることも暗示して「かの」とするだけで、何もいわなくても、しじまに情熱は燃え上がります。 【添削例】かの人は赤のカシミアその淑気
【原石賞】獅子舞に灘の菰樽噛ませおり
金森三夢
【恩田侑布子評・添削】 「おり」の正しい歴史的仮名遣いは「をり」です。
新年詠ならではのめでたい光景です。原句は、そのままの状態を表す「をり」を使っています。獅子舞の活発な動きの面白さ、噛んだ瞬間の感動を一句に定着させるには「噛ませたものだよ」という詠嘆の「けり」がよりふさわしいでしょう。一字のちがいで、「獅子舞」の嚙む「灘の菰樽」に御神酒の霊気があふれ、今年の吉兆をここに集う人々と会全体に呼び寄せる切れ味のいい句になります。 【添削例】獅子舞に灘の菰樽噛ませけり

2024年1月27日 樸句会特選句 鯛焼のしつぽの温みほどの恋 小松浩
「はらわたほどの恋」ではなく、「しつぽの温みほどの恋」がなんとも可憐です。あるかないか。すぐに冷めてしまいそう。でも、ゆっくりと味わっていると、熱いホカホカのお腹のあんこからほわあんとした「温み」が伝わってきます。いまは「しっぽ」だけれど、これからいよいよ本丸のはらわたに攻め入るのかもしれません。そぞろにものを思わせる力のある、楽しく愛くるしい俳句です。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年12月23日 樸句会報 【第135号】 暖かな日が続いていた後にやってきた寒波で、空気がピンと張った冬晴れの日。今年最後の句会がありました。
兼題は「数へ日」「鍋焼」「熊」。
特選2句、入選4句、△4句、レ4句、・8句。高点句と高評価の句があまり重ならなかったことから、それぞれの読みをめぐって活発に意見が交わされました。「鍋焼」の食べ方談義も楽しい時間でした。
◎ 特選
斎場のチラシかしまし冬の朝
林彰 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「冬の朝」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
警笛に長き尾ひれや熊渡る
小松浩 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「熊」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
数へ日やかき抱きたき犬のなし
天野智美 【恩田侑布子評】 「かき抱きたき人」ではなく「かき抱きたき犬」で、とたんに俳諧になった。いつも一緒にいた小柄なお座敷犬が想像される。その愛らしかった瞳やら毛並みやら。もう一緒に迎えるお正月は来ない。「数へ日」が切実である。
○入選
星なき夜熊よりも身を寄せ合はす
見原万智子 【恩田侑布子評】 「星なき夜」でなければならない。一粒でも星が瞬けば童話になってしまうから。月もない真っ暗な夜。希望もない。声もない。が、「身を寄せ合はす」人がいる。飢えかけているときに一番食べものが美味しいように、絶望しかけている時ほど、愛する人がいる幸せを感じる。居ないはずの熊を感じるのは、作者が熊になりかわっているから。
○入選
数へ日の日毎重たくなりにけり
海野二美 【恩田侑布子評】 毎日は二十四時間で変化がないはずなのに、年が詰まり、あとわずかになると、言われるように一日が沈殿するように「重たくなる」。あれもしていない。こっちの片付けもまだ何もやっていない。どうしよう。日数が足りない。途方に暮れても、時間の流れは容赦ない。省略が効いていて、覚えやすい良さもある句。
○入選
鍋焼吹く映画の話そっちのけ
成松聡美 【恩田侑布子評】 映画の帰りに店に寄ったのだろう。今まで夢中で主人公や脇役の話をしていたのに、「鍋焼」が湯気を立てて運ばれてきた途端、もう映画なぞ「そっちのけ」。ふーふー。ずるずる。アッチッチと言ったかどうか知らないが、美味しく楽しく夜はふけてゆく。
【後記】
年末のあわただしい気分がありながら、句会の間は別の時間が流れているような気持ちにもなりました。
「“発見”が大事といつも言っているけれども、それは“知”“頭だけ”での発見ではなくて“知・情・意”があるものでなければ」との恩田先生の言葉に、詩的な発見のための構えについてあらためて感じるところがありました。また、「情、気持ちの切実さは十分に持ちつつそれに耽溺せず表現するのが俳句」との言葉も。難しい、ですが、その難しさを楽しむ気持ちで新年に向かえたらと思っています。 (猪狩みき) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
==================== 12月12日 樸俳句会
兼題は「冬ざれ」「山眠る」「枇杷の花」です。
特選2句、入選3句を紹介します。
◎ 特選
テレビとは嵌め殺し窓ガザの冬
古田秀 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「冬」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
枇杷の花サクソフォーンの貝ボタン
益田隆久 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「枇杷の花」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
枇杷の花いつか一人となる家族
活洲みな子 【恩田侑布子評】 枇杷はしめやかな花。半日陰を好むようで、遠目にはそれと知れない。トーンの低い冬の日差しに似合う。大きな濃緑の葉影に静まって地味に群れ咲く。「いつか一人となる家族」。この感慨にこれほどピッタリと収まる花は他にはないだろうと思わせる。
○入選
磔の案山子の頭ココナッツ
芹沢雄太郎 【恩田侑布子評】 案山子は秋の季語。ココナッツの頭はエキゾチック。作者は南インド在住の芹沢さんと想定して入選に。
まず案山子を「磔」とみたことに驚かされる。今まで衣紋掛けは連想しても、キリストの磔刑など、夢にも想わなかった。言われてみれば、案山子が痩せこけた磔刑像のキッチュなポップアートのように思えてくる。そこら辺のココナッツで無造作に頭を代用しているとなればなおさら。インドの原色の服装も見えてくる。名詞をつないで勢いのある面白い俳句だ。
○入選
きれぎれに防災無線山眠る
成松聡美 【恩田侑布子評】 よくある山村が目に浮かぶ。限界集落ともいわれる山間地の寒村だろう。「きれぎれに」の措辞がリアル。谷住まいの評者も日々経験しているが、山や木や風に遮られて明瞭には聞こえてこないもの。ばかばかしいほどゆっくりとした広報の声が風に乗って、だいたい何を伝えたいかだけはわかる、あいまいの国、日本。「空気が乾燥しているので火の元に気をつけましょう」とか。大したことは言っていなそう。山は安堵して眠りについている。

2023年12月23日 樸句会特選句 警笛に長き尾ひれや熊渡る 小松浩
警笛の音を魚類のような「長き尾ひれ」と捉えた感性が抜群。にわかに北国の冷たい空気が迫ってくる。しかも句末の「熊渡る」と響いて、人間界を尻目に、熊が悠々と北の大地を歩いてゆく姿が髣髴とする。なんという夜の寒さか。熊が、アイヌの人たちにとって、神の使いであることも納得されるのである。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年12月23日 樸句会特選句 斎場のチラシかしまし冬の朝 林彰
新聞の折込チラシに、最近とみに増えたものといえば、斎場や墓の宣伝広告。ものを言わないただのチラシに「かしまし」の措辞が出色だ。つややかな上質紙の色刷りの存在感はスーパーのチラシの比ではない。姦しい商業広告と、人間の生理的な死との対比。面白いが、やがてしんみりする。誰にも訪れ、やがて私にも訪れる静かな死を思う「冬の朝」。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)
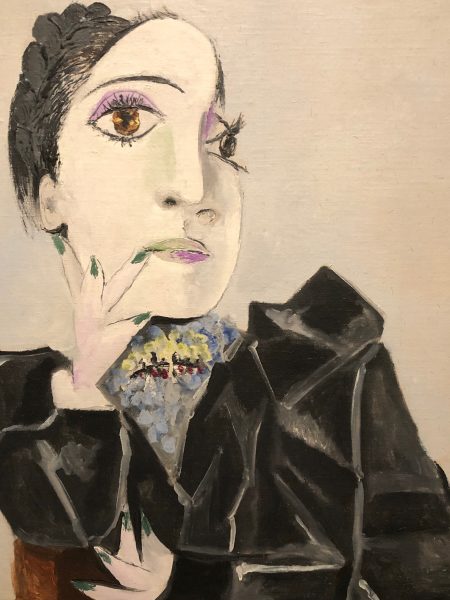
2023年12月9日 樸句会特選句 枇杷の花サクソフォーンの貝ボタン 益田隆久
サックスとも俗にいう楽器は、木管楽器と金管楽器が溶け合うような柔らかな安らぎの音を響かせる。それを枇杷の花に取り合わせた感性が素晴らしい。しかも「サクソフォーンの貝ボタン」と、ゆるやかなリズムでキーボタンの指貝に焦点を絞って終わる。冬日に枇杷の花と乳白色にうすぐもる貝の艶のコレスポンダンスも洒落ている。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年12月9日 樸句会特選句 テレビとは嵌め殺し窓ガザの冬 古田秀
テレビはなんでも写す。親し気に見知らぬ人が出てくるものと思っていた。でも、今度ばかりは違った。ハマスの200人殺人に対して、イスラエルがガザの人々を16000人も早や殺戮してしまった。しかも封鎖された狭い空間に押し込められたパレスチナ人は、飢渇させられ、子どもまで数千人も殺されている。まさか、今世紀にこのような非人道的なことが、という切迫した思いが溢れる。テレビはなんでも見えるようで、1ミリも開かない窓だったのだ。「嵌め殺し」という詩の発見の措辞が、現実に起こっている殺戮現場につながり、心胆を寒からしめる。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。