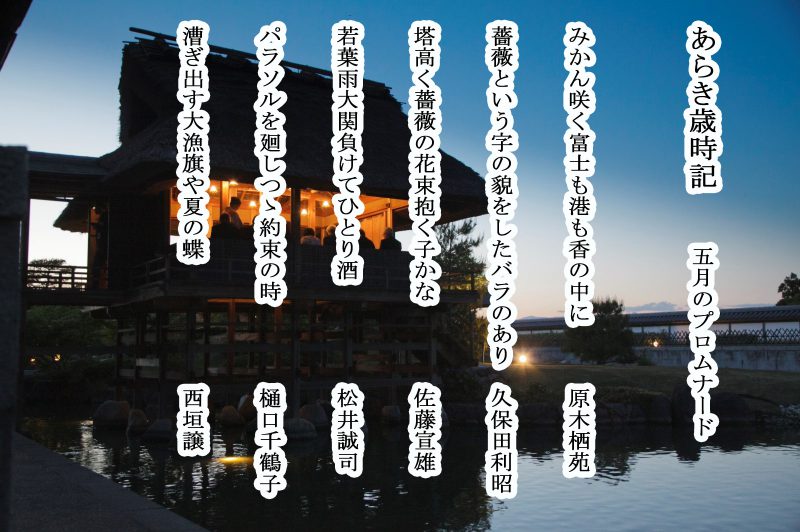令和2年3月1日 樸俳句会特選句
なまくらな出刃で指切る日永かな 天野智美 「なまくらな出刃」が出色。俳味がある。切れ味が鈍っているのに面倒で研いでもいない出刃包丁は、同時に自虐に重なってくる。「私はなまくらものだわ」というつぶやきが聞こえてきそう。じっさい切れ味の鈍くなった包丁ほど指を切りやすいものはない。変に力が入るからだろう。「イタッ」。左手の中指の甲に血が滲んで、突如包丁が不器用な自分の生き方に重なって感じられたのである。中七の「指切る」にわずかな切れがある。なまくらな出刃で指を切ってしまうような、そういう日永なんだよ〜と詠嘆している。「にぶい包丁でだらしのない指切っちゃあ世話あねーよ」、という話なのだが、座五の「日永かな」の付け味がいい。人生の日永に作者はいる。さて、春日遅々とはいえ、ゆっくりと日は傾いてきている。これからどうしようかな、と思う。季語で俳句がにわかに大きくなった句である。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

樸の九月の佳句を恩田侑布子が鑑賞していきます。
それぞれの心にある実りの秋をお楽しみください。(山田とも恵) ≪選句・鑑賞 恩田侑布子≫
磔刑を見てきたやうな蜻蛉の眼
山本正幸 この眼は鬼やんまに違いない。透きとおる碧の不必要なほど大きなあのガラス玉。その眼がイエス・キリストのはりつけをたった今見て来たとはおだやかではない。人類の原罪を一人であがなってくれたと聴いても、アジアの民は痛ましく思うばかり。蜻蛉はさてどう思ったのか。まっすぐやって来て小枝の先に止まった。その眼は蒼穹(そうきゅう)を隈(くま)なくうつして静まる。泉のような金のひかりを奥に嵌(はら)めて、また明るい野道をついーとまっすぐ行ってしまった。 ※ 磔刑=たっけい カフェテラスただ居座つて星月夜
久保田利昭
一読、ゴッホの名作『夜のカフェ・テラス』を思い出す。インディゴブルーの夜空に花のよう降る星屑。裏通りのやわらかそうな甃(しきがわら)に漏れるカフェの鮮黄色のひかり。画面の一角に孤独を愉しむ男がいたらそれが作者。中七の「ただ居座って」の口語調が新鮮で、男気と存在感がある。もしかしたら絵の中に紛れ込んだのではなくて、本当に駿河湾にそそり立つ大崩海岸の白亜のカフェにいるのかもしれない。だとしたら、星明りは深海にまで降りそそぎ、このテラスは宇宙の中心になるだろう。 きちきちは海へとジャンプ捕まらず
原木栖苑
ばった、螇蚚、はたはた、精霊ばった。季語の傍題はいろいろあるが、この「きちきち」は選び抜かれて動かない。イ音の鋭い連続から乾いた叢(くさむら)の茂みと砂地が浮かぶ。目の前には青い海しかない。この世のどんなものも手が出せない。ジャンプあるのみ。秋の爽やかな大きな海原の空間が充満している。

樸の八月の佳句を恩田侑布子が鑑賞していきます。
夏から秋にかけての刹那的な熱がほとばしる季節をお楽しみください。(山田とも恵) ≪選句・鑑賞 恩田侑布子≫
胡瓜もみ昨日も今日も明日もかな
樋口千鶴子
子どものころ「今日もコロッケ、明日もコロッケ」という歌がよく流れていた。コロッケは冬季の季語にふさわしいが、こちらは火を使わない夏の定番料理、胡瓜もみ。ひらがなのなかに「胡瓜」、「昨日」、「今日」、「明日」と漢字がとびとびに埋まっていて、あたかも日めくりの暦をめくるよう。めくってもめくってもそこに現れるのは胡瓜の塩もみ。透明な翡翠色の食卓が永遠につづくような気がする。素手素足で生きる涼しさ。こんな滑稽はわるくない。 原爆忌父の命日でもありき
佐藤宣雄
父は長い戦後を生き抜いてぼくらを育ててくれた。その命日が八月六日。まさに原爆忌であった。一個のいのちを喪った悲しみすら言い尽くせないのに、原爆の死者を一口に14万とも35万人ともいう。だが、アメリカ人の多くは「原爆は戦争終結に役立った」と今も考える。そこに日本が加害者として戦争を始めた根深さがある。「戦争を日本人自身の手で終わらせることができなかったことの意味は今後もこの国に長く尾を引くでしょう」と鶴見俊輔は問いかけた。掲句も座五の「でもありき」が不断に問いかけて来る。社会や歴史に、わたしたちはかけがえのない個として切実に向き合ってゆくしかない。父の無言の遺言が聴こえる。
揚花火老い知らぬまま華のまま
海野二美
夏の夜空を焦がす大輪の花火。その炸裂音。花火は老いを知らない。衰える前に消える。この句は、華のまま美しく別れましょうというせつない恋の句であろうか。生涯をかたむける一夜限りの逢瀬は、時を闇に発光させる花火さながら。しかし、声に出して口遊んでみると意外にもふっくらとやわらかなリズムに包まれる。次々に揚がる花火のように、うつくしく華やかに生きたいわという夢みる女ごころかもしれない。

(画像をクリックすると拡大します) 樸の七月の佳句を恩田侑布子が鑑賞していきます。
生命力が立ち昇るかのような夏空を、思い浮かべて楽しんでいただければ幸いです。(山田とも恵) ≪選句・鑑賞 恩田侑布子≫
かき氷食べて君等はまた魚
伊藤重之 不謹慎にも井上陽水の「リバーサイドホテル」を思い出してしまった。「ベッドの中で魚になったあと川に浮かんだプールでひと泳ぎ」というあの頽廃(たいはい)的な歌詞を。だがこの句は、昭和のスノビズムを揶揄した陽水とは対照的な若い健康さを持ち味とする。まだ脂肪がどこにもついていない十歳前後の少女たちはほっそりした魚のよう。かき氷を食べた後も平っちゃらで泳ぐ。少女らのさざめく笑いがいまにも聴こえそう。ぴちぴちした身体が享受する夏のよろこびが清潔にいいとめられている。K音の五つの響きが、澄んだ水とはじけるような肌にマッチして、この上ない清涼感をもたらすのである。 雲の峰登山者のごと君や逝く
藤田まゆみ
一読、衝撃の句。雲の峰も登山も夏の季語だが、前者が季語として盤石の存在感を示す。雲の峰を登攀(とうはん)するように「君」、すなわち愛する伴侶はこの世を旅立った。壮絶な最期だった。生前、山男であった夫君に連れられ、作者も不承不承ながら山によく登ったという。そのとき尾根の上にオブジェのような夏雲がかがやいていたに違いない。頑健そのものの人が、まさか六〇になったばかりで逝ってしまうとは。雲の峰を登って羽化登仙してほしいという願いをにじませつつ、この句のよさは何といっても虚実の迫真的な混交にあろう。あの日の登山が壮年の真夏の死の床にフラッシュバックする。あなたは死んだんじゃない。巨大な雲の峰を登りおおせたのよ。「君や逝く」にこもる妻の慟哭は、山男の天晴れな生き方を永遠に讃えている。 言ひたきこと口には出でず遠花火
戸田聰子
いちばん思っていることは、特に好きな人を前にすると口にしづらい。頭上に炸裂する花火ならば、音に紛れて目くばせもできよう。だが作者は、遠花火の眺められる場所に、その人とゆくりなくも居合わせたにすぎなかった。大切なことばは「いつも忘れていませんわ」であっただろうか。「夢でお会いしますわ」であっただろうか。中七が「口には出さず」であれば凡句だが、「口には出でず」で、にわかに秀句の気品を備えた。遠い甍(いらか)の上に音もなくはじける花火を、抑え続けた情念がいっそう鮮やかに切なく彩り浮かびあがらせるのである。ぎこちない沈黙の意味を、その人は果たして受け取ってくれたであろうか。

(画像をクリックすると拡大します)
樸の六月の佳句を鑑賞していきます。梅雨のもとでしっとりとした存在感を増していくものたちを、ご一緒にゆっくり味わいましょう!
(大井佐久矢) 鑑賞 恩田侑布子 河明りまだ花合歓の眠らざる
西垣譲 六月下旬、梅雨時の山裾にゆくと、大きな合歓(ねむ)の木が、夢のようにほおっと咲いていることがある。夕闇が迫り、川はしろがねから銀ねず色になるところだ。すべてを見守るように、合歓が樹上たかく、白とピンクの長い睫毛のような花を咲かせている。見る人もない夏の夕べ。山の向こうに日は隠れ、すこし涼しくなってきた。作者は、川ほとりにある菜園から自転車をこいで帰ろうとしているのか。河明りに花合歓明りが重なり、無何有(むかゆう)の郷がひととき姿を現したかのよう。 蛍飛ぶあの日あのこと追ふ如し
秋山久美江
とぶ蛍になり切り、感情がそのまま調べになった句。作者は螢をみながら、次第に過去の時間にタイムスリップしていったのだろう。ぼんやりと過去をなつかしむのではなく、「あの日あのこと」と畳み掛け、しかも「追う如し」と言いきって、切れを響かせた。繚乱と舞うほたるの光の条(すじ)と、追いかけてゆく自分との境は、もはや見定めがたく、今の時間と過去の時間も入り乱れて分かちがたい。こころの叫びが一句になった。 黒南風や港に海月置き去りて
杉山雅子 黒南風(くろはえ)は梅雨初めのみなみかぜ。海月はくらげと読む。「浜」ではなく「港」で、にわかに詩になった。埠頭のコンクリートの上に、置き去られ、乾いてゆく海月の姿が見えてくる。海月は本来、海中では幻想的で美しい生きもの。その生きていた時間の妖しさと神秘の尾をひきながら、無残にも黒南風のうっとうしい曇天の下に死骸をさらすことになった海月。岸壁の灰色と海月の白濁するクリーム色が、黒っぽい海風に溶け込んで、いのちの果てる陰惨さをにじませる。その一方で、どこか凄愴な美しさもある。感覚のいい句である。
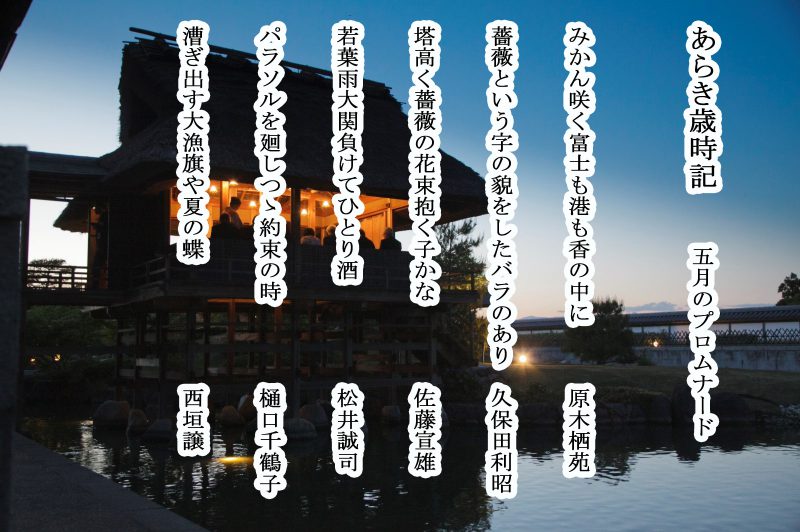
(画像をクリックすると拡大します)
樸の五月の佳句を、季節のうつろいにあわせた並び順で鑑賞していきます。薫る風を胸いっぱい呼吸しながら散歩するように、楽しんでいただけましたら幸いです。
なお樸では、仮名遣いの新旧をめぐる作者の選択を尊重しております。仮名遣いや音の印象をふくめて、作品を絵画としても音楽としてもどうぞ自由におうけとりくださいませ(大井佐久矢)。 鑑賞 恩田侑布子 みかん咲く富士も港も香の中に
原木栖苑
静岡は香りの国。五月は新茶の芽吹とともに、蜜柑の花の香に里山が満たされる。ことに山窪は甘い清純な香りの坩堝と化し、壺中の天地のよう。作者ははじけるような白い花かげから富士を仰ぎ、清水港を見下ろす。そのとき、まるで円光に抱き取られているかのように、富士も港も、シトラスの芳香のなかにあることを確信した。柑橘のケラチン質の葉の緑。富士の頂と山腹の白と青。港の彼方にひろがる駿河湾のきらめき。地貌俳句にして、北斎の富嶽三六景さながらの大柄俳句といえよう。蜜柑の清楚な花が、極大の海山を包み込んでしまうところに一句のダイナミズムがある。さりながら、読み心地は蜜柑の花のように、あくまで可憐。 薔薇という字の貌をしたバラのあり
久保田利昭
飄逸。笑える。名は体を表すどころか、字は体を表すという。ドライな見方はあんがい薔薇の美を言い当てている。薔薇をバラとカタカナ表記し、顔を貌としたことで、気品ある薔薇のかなたに、気位の高い絢爛たる女性の姿が揺曳する。A音七音と口語調が明るい開放的な夏の陽光を感じさせ、内容の現代性にマッチしている。大胆な機知が光るこんな句を読むと、俳句文芸には、理系文系の垣根がないことがわかる。湿度がないのがいい。 塔高く薔薇の花束抱く子かな
佐藤宣雄
文句なく美しい句。フランスやイタリアの田舎にある教会で行われる結婚式の光景だろうか。塔の下に、天使のように盛装した子どもが赤や白の薔薇の花束を抱いて、新婦が来るのを待っている。結婚式と限らなくても、何かお祝いの式が始まるのだろう。その予兆のように、句の調べにも胸の高鳴りがある。塔の上からカリヨンが聞こえてきそう。 若葉雨大関負けてひとり酒
松井誠司 「若葉雨」と「大関負けて」の措辞が音楽性ゆたかに響きあう。横綱ではこうはいかない。判官贔屓の人の胸の内にはいつも清らかな流れがある。若葉雨もきっとそこに流れ入るのだろう。若葉色の雨しづくが、やわらかでなつかしく、ひとり酒のしめやかさに明るさがある。作者はまだ日のあるうちからきこしめしている。高級酒ではなさそうなところもいい。 パラソルを廻しつゝ約束の時
樋口千鶴子
日傘を肩にくるくる回しながら好きなひとを待つ。可憐で初々しいしぐさにドラマが仕込まれている。句跨りのリズムの屈折が絶妙なのである。そこから胸のときめきと、かすかな不安が同時に伝わり、こちらまでドキドキさせられる。これからどうなるのだろう。二人は、わたしたちは。ここにあるのは有無をいわせぬ若さである。二度と帰らない若き日のはじけるような日差しの純白。 漕ぎ出す大漁旗や夏の蝶
西垣譲
小さな漁港から色鮮やかな大漁旗を掲げて出港する漁船。可憐な春の蝶とはちがって力強い生命力に溢れた夏蝶が、船に競うように海上をついてくる。波の青々したうねりまでみえるようだ。緑の山が漁村の低い甍に迫る日本の津々浦々の風景が浮かぶ。掲句は、西伊豆海岸にある漁港の祭り風景かもしれない。「出す」がいい。「出づる」ではよそ事になり、「出しし」では、たんなる風景になる。「いだす」で勢いがつき、海の男たちと夏蝶の双方に、いのちの体重がかかった。
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。