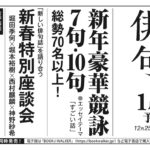2025 樸・珠玉作品集 (入会日の新しい順) たたまるる初富士の縞君がほほ 恩田侑布子(写俳) - 巻頭言 - 21世紀のクォーターを迎えた樸は一国主義の風潮の逆をゆけました。 日本とインド二拠点の従来のズーム句会に、ニューヨークとパリから新人が参加してくれたのです。二、三十代の若者たちの頼もしい笑顔も弾けています。私は仲間との出会いに感謝し、掌のなかのすべてをお伝えしたいと願っています。 樸ズーム句会は自宅の暮らしの場から即座に四カ国の句友と繋がれます。匿名で選句し、句会で作者がわかれば、特性に添ったアドバイスを差し上げます。句会あとの第二部は、芭蕉の紀行文を学んだり、俳句時評をしたりする文化サロンです。目標の三十三観音の会はいまだしですが、熱意と質の高さは揺るぎません。こぢんまりした文藝コミュニティーは純粋で自由闊達な俳句談義ができる場です。言葉のふたときの晩餐会のよろこびは国境を超えます。 一方で、国際秩序や人権理念は崩壊に拍車がかかっています。進歩は兵器テクノロジーにのみあざやか。武器大国は目の前の人参を追って、地球の未来を食い潰し、ジェノサイドを恥じません。ホモサピエンスは凶暴化しています。 現実から目を逸らさず、自分にできることは何か。人間とは何なのか。三百六十度開かれた微塵の俳句から大きな世界に向き合いましょう。今年も新たな出会いを求めて、一息の詩に共感し合いましょう。 樸代表 恩田侑布子 小南善彦 旅先で我がふる里のお湯自慢 冬晴れの歩道にはずむランドセル 嵐去り川滔々と花筏 時空を超えて五感に迫る俳句の世界 写真と俳句の違いは、想像の余白の広さではないでしょうか。 写真から受けとる感動は、瞬間を捉えた感動です。それに対して俳句は、場所や時間を自由に行き来し、光や音、匂いや温度、さらには目に見えない気配までも、読み手一人一人に感じさせてくれます。17文字の楽しさと苦しさ(笑)を、これからたっぷり味わってゆきたいと思います。 川崎拓音 精霊飛蝗追ひかけた父も母も 人はひとわすれてあゆむ芒原 冬夕焼旅びと還す比叡山 文學の地、文藝の空 入会してまだ間もないころの句会。どうしても都合があわず遅れての参加になった。それでおずおずと申しでて、句会の終わりに先生に<補習>をしていただいた。個別指導できもちがおおきくなっていたのか、なりゆきで先生と文學談義をした。 「最終的には自分の文學を極めたいです!」とわたし。 「いいじゃん!」と先生。 言い尽くせないよろこびがあった。きもちがおおきくなりながら、実は、文學という言葉を口にすることにすこし緊張していたからだ。 読む者の心を動かす何らかのしくみを具えた記述——そのしくみを解き明かそうとする営みが「文學」であると大学時代にならった。文學の地から見あげる文藝の空は、あまりにも自由でおおきかった。かたや、文學者たらんとする自分自身の心を動かす記述を、自分自身で残してもみたかった。文學と文藝の果てしない往還は、空気がやけに薄く感じる。寒さに羽を震わせどうしたものかと立ち往生していた矢先、恩田侑布子という師に出会えた。こころからうれしくおもう。 橋本辰美 雲の峰貴方の居所捜し当つ 稲妻のつながり落つる河口かな 南蛮や未知より無知の懐かしき 清見潟 23年3月に「楽しい俳句」を、また戻ってくるつもりで退室して以来、3年ぶりの出戻り新人として、晴れてzoom句会主体の樸に入会できたことが小さくない体験でした。一回一回の句会を大切にしながら、師匠と連衆に認めてもらえるように句作に励み、批評性と情趣の間を揺れながらも自句を追求していけるように努めていきたいと思います。 佐藤麻里子 白ビール迷はぬ女同志なり 淵碧き砦裸のピカソかな 揚花火鉄の貴婦人張り合ひし 自己の更新としての俳句 2014年、ドゥマゴ文学賞受賞作『余白の祭』が著者・恩田侑布子をフランスに送り出したことが、私の俳人との出会いだった。全くの門外漢の私は会食の拙い通訳でご一緒し、著書にノックアウトされ、その後パリや静岡で再会し親しくさせていただいた。ただそれ以外俳句とは無縁のまま、11年を経た今年、ようやく機が熟したのだ。 句会の合間の先生のおしゃべりはヒントに満ちている。先日独り言のように、「俳句は難しいので油断するとちょっと前の自分に戻ってしまう」。先生でさえも!?「日々新しい自分にしていかなければ」と。 自己の更新。それが私も七転八倒してもやり続けたいこと。 「ささやかでも、おのれの殻や、時代の旧態を破ろうとする、日々更新の自由なこころこそ、本来の俳句のはず」(『余白の祭』p.115)。 それはきっと俳句だけでなく、芸術とは本来そういうこと。 さて、来年は時間不足を言い訳にせず、いかに自由な心で作句に励み、自己を更新し再生しつづけられるか。 小住英之 地ビールを二本空港泊の窓 満塁や灼くるシンバル灼くれど撲つ 病室の鎖骨に月のありあまり 癖 なにか大事なことを決めるとき、「あまり検討しない」癖が私にはあります。しかし私は不思議とこの癖に助けられてきました。 例えば、大学生のとき座学だけで「皮膚科医になろう」と決めた私は、その研究室にすぐに通い始めました。九年後、私はその研究でなんとか博士号を取得し、今の職を得ました。あのとき実習・研修開始を待たずに皮膚科に決めてよかったと思います。 俳句を始めて半年で古田秀さんの「大学」を読み、樸俳句会を知りました。ホームページを見て、ある種直感的に樸で勉強したいと思い、仲間に迎えていただきました。あのとき樸に飛び込まなければ、ここまで俳句に熱中することもなかったように思います。 これからも一歩ずつ、俳句の道を学んでいきたいと思います。今後もご指導お願いいたします。 馬場先智明 ⼩春⽇や部屋にやすらふ⺟の⾻ ⼋⼗年焼⿃の串抜くやうに 仮名千年語り万年寒昴 「似て非なるもの」に魅せられて 「俳句と編集とは、似て⾮なるものです」と、恩⽥先⽣はキッパリ。編集の世界に半世紀近く棲息してきた⾝には沁み⼊るような⾔葉でした。句歴⼀年で感じたのは、俳句には「達⼈」や「極意」という⾔い⽅がよく似合うなぁ…ということ。芸や美の道を極めることに魂を注いで倦むことのない⼈たちの世界。武芸、茶道、将棋…のような型や厳格なルールに則った世界。極めてこそ⾒えてくるものを追い求める少数者が泰然と⾝を寄せ合う世界。芭蕉から恩⽥先⽣はもちろん近現代俳⼈までの句を渉猟しては嘆息する⽇々でした。⽚や私のかかずらってきた編集の世界。⾔葉(⽇本語)を道具⽴てとする点は同じですが、あくまでも⾔葉は「情報」。編集者の仕事は、外から掻き集めた情報の順列組合せを専らとして新奇を創出する知的作業。⾔葉はいつでも外からやってくるものでした。⾔葉を道具として扱ってしまうのは、編集者の宿痾みたいなものです。対して⽂学(俳句)の⾔葉は、⾝体の内側から時間をかけてゆっくり滲み出てくるもの。この⼀年の成果は、その宿痾を⾃覚できたことかもしれません。来年はその⾃覚から出発して「⾮なる」俳句の奥深さに少しでも近づいていきたいと願っています。樸連衆の皆様には、編集(+短歌)という「似て⾮なる」お隣から珍獣が⼀匹迷い込んできたと、広い⼼で⾒守っていただければ幸いです。 山本綾子 餅つきの空つく音あり郷の庭 羊水のたしかな鼓動しゅろの花 短夜や眸句集とミントティー 俳句のある暮らし 恩田先生に師事して三年目の今年。そろそろ「初心者だから」の常套句は通用しなくなってきた。 そんな中、俳句に触れる時間を少しでも増やせればと、樸句会投句の他に先生が選者を務める静岡新聞読者文芸への投句を自分に課した。 毎月最終火曜日。家まで待てずコンビニの駐車場で、購入した新聞を広げる。そんな自分を、少し離れたところからもう一人の自分が面白がって眺めている。 日々の忙しさ、日常の平坦さ、過去に負った傷さえも、俳句をつくることで、より豊かなものとなっていく。自分を支える「俳句」という柱は年々太く育っている。 星野光慶 聖五月ぐさりとキャパのレンズかな 「源氏供養」闇に佇む冬の星 まろき背にとどめし秋や無著像 浮かび上がる時間 ロバート・キャパという人物はいない。アンドレ・フリードマンとゲルダ・タローが撮影したそれぞれの作品をこの架空の写真家に託したにすぎない。 作品を見る側は、アンドレとゲルダのどちらが撮影したものか見分けることは難しいだろう。しかし、もし撮影者が明かされたら、両者の世界の見かたの違いがぼんやりと浮かび上がってくるのではないか。 ひとつの作品には匿名と個がせめぎあっている。 俳句もこれに似ている。無名の句が私の前に並び、作者が種明かしされると「人柄が出ている」と妙に納得してしまう。そのひとが見た景色が、ことばというレンズ越しに立ち上がる。 無名性と有名性が反転する有機的な時間が句会だとしたら。そのあとには、寂しく賑やかな無名の作品が残される。 長倉尚世 ほそき手の床より賀状たのまるる 枇杷たわわ廃車置き場の水たまり 柊の花や卒寿の退院す 伝えたいこと 今年五年も迷っていた声帯の手術をした。 きっかけは母の耳である。話しかけてもスッと前を素通りして行くのに驚いた。聞こえていないんだ……そう云えば、孫との会話にも、あまり入って来なくなっている。 元々私は話すのが苦手。自分の思っていることを伝えるのが下手くそで、母ともそんなにおしゃべりをしてこなかったが、このまま話ができなくなるのは寂しいと思ったから。 手術後一週間は声を出すことを禁じられた。その間筆談をしていたが、そのもどかしさの中で、ふと手話を覚えようと思った。そして退院後、早速手話サークルに入会。 日常のささやかな場面で、誰かの役に立てたらいいと思う。 成松聡美 春の暮真子の煮つけは反り返る 木香薔薇あふれんばかり死者の庭 猟銃等講習会場泥長靴 神主のいないお社 この拙文を書いているのは年の暮、新年拝賀式準備の最中だ。榊や神饌、振舞い用の酒や汁物の手配で忙しい。私の住む村の小さなお社には神官がいない。拝賀式の一切は氏子総代と当番組の組長たる我が家が差配する。この一年、負担の重さに怒りが治まらない夜もあったし、地域を盛り上げるとは何か議論になる場面もあった。だがご近所と協力して御神燈を張替えたり、紙垂や御飾りを手作りしたりと楽しい経験も少なくなかった。当然これらは俳句の種となり、習作帳には神事や神の字が入る季語が多くなった。神社のお世話は来年も続く。神主のいないお社の句は、もう少し増えそうだ。 坂井則之 龍天に昇る昼夜を真つ二つ 白菜を割る音絶えて十余年 庖丁の切れ味試しトマト切る 初の句は3月に先生の添削を頂戴した後のものです。句の勢いがこんなに改善されるかと、つくづく思いました。 あと二つは[シルシ]程度。2句目は当人の含意と先生の鑑賞とが異なりました。叙述の拙さの表れです。 新聞記事が本拠だった私は、意図を明瞭に伝えるという意識が先に立ちます。そこに、理に落ちてはいけないという何度も頂戴したご教示を思い出し。散文人間は苦戦しています。 今の私は、たとえFBへの投稿でも幾らでも推敲を考えます。新聞紙面を読んで気になることがあれば校閲の後輩に指摘して、検討を依頼しています。ですが、自分の五七五では突き詰めるまで考えることができない己。韻文としての良否の判断ができないのです。 そもそもこの道に入って良かったのかと思いつつ、ウロウロの日がずっと続いています。 生きてゐるたれも初乗り地球船 恩田侑布子(写俳) 岸裕之 寒声や師匠口ぐせ「間は魔なり」 春光を睨むや龍の天井絵 見はるかす白馬三山花こぶし 来年の目標 今年を振り返ると、正月の句会でいきなり特選をいただき、続いて春先は、なんとか入選を何句かいただきました。そこで、気をよくして、今年から始まった町内の年寄り90代一人、80代二人、70代一人メンバーによる麻雀に力を注ごうと思い立ちました。というのは、麻雀は50年やそこら、やって無かったので、すっかりやり方を忘れていたせいか、勝てません。麻雀には実力の他、運という要素もありますが、勝てません。やはり負けるのは悔しい。で、PC麻雀ゲームなどを使って訓練しました。そのせいか、なんとか勝てるようになってきました。ところが、夏から秋にかけて俳句においては、無点句のオンパレードでした。だから今年の三句は前半のものだけです。私は句集を作ろうとか、賞を貰おうなど思いません。気のおけない仲間と俳句談義したり、そこに酒が入ればなお良い程度のスタンスです。従って来年の目標は年間バランス良く選をいただくにとどめます。 小松浩 夏蝶の影轢くサイクリングロード 日盛りの影もたれあふ交差点 人類に聖なる夜と聖戦と むずかしいことをやさしく 樸のメンバーも20人を超えて賑やかになった。句会というのはやはり素晴らしい場だ。投句作品からは、歩んできた道のりや、どんなことに喜びや悲しみを感じる人なのかが、くっきり浮かんでくる。共通しているのは、一人一人の他者への目線の優しさ、誠実な暮らしぶりである。 俳句は、それぞれの人生観や価値観を、理屈ではなくモノを通して、17音に乗せることに魅力があると思う。できれば、今の時代や社会に対して感じていることを、五七五に託して表現してみたい。それも、日常生活で使っている普通の言葉で、「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく」と言っていた井上ひさしさんのように。 活洲みな子 吾の歌に母の輪唱桜の実 天上の母はすこやか樟若葉 青空に挑むじやんけん花こぶし 日向ぼこ付箋だらけの句集抱き ミニマリストではないけれど、ホテルのようにシンプルな生活空間に憧れる。退職後、仕事がらみの大量の本をまずは処分し、好きだった小説や全集も手放した。ホテルライクな生活にあと一歩(?)というところで、句集を手にする愉しみと出会ってしまった。おかげで棚はまた本で溢れ始めている。 好きな句集は付箋だらけだ。世界観がわからず付箋のつかない句集もある。けれども一句一句に俳人の心が宿っているので、大切に扱っている。年末に加わった三冊の句集。陽だまりでのんびり愉しむ時間が…あるといいなあ。 益田隆久 暮れてなほ弾む句会や花こぶし パレットへ囀りの色溶きにけり 踏まれたる下萌の香の高くあり 句友の秀句への共感 樸の仲間の俳句の中で、自分の一部にすらなっていて瞬間的に言える特別な俳句が三つある。 (1)八橋にかかるしらなみ半夏生 前島裕子 (2)父母は芽花流しの向かう岸 活洲みな子 (3)花すゝき欠航に日の差し来たる 古田秀 (1)前島さんの俳句は、恩田先生と自分の特選が初めて一致した句で非常に嬉しかった。「目で見て美しく声に出して美しい俳句。」と感想を書いた覚えがある。今でも自分の理想とする俳句だ。 (2)活洲さんの俳句は、年月が経つとともにじわじわとその良さが増していく燻銀のような俳句だと思う。そこには、時間というものへの愛おしささへ感じることができる。 (3)古田さんの俳句。この透明感はどこから来るのだろう?余計な修飾を付けたしたくなりがちだが、この句にはそのような自我が無い。雑味が無く透明感と清々しさが気持ちよい。 このような俳句に出会い誦する時、この句会を選んで良かったと思う。 古田秀 スケートボード蔓薔薇すれすれに蛇行 露の世の薬局あかりジムあかり クリスマスツリーの蔭や守衛室 グーグルマップはすごい 昔から地図を見るのが好きで、油断しているといつまでも眺めてしまう。実験の合間の待ち時間など、他にやることはたくさんあるがついついグーグルマップをひらいて仮想旅行をしてしまう。最近はグーグルマップの精度があがり、ユーザーの興味のありそうな施設を優先して表示するようになった。地点間の所要時間の計算も正確で、渋滞の起きやすい時間帯なども表示してくれる。2025年は日帰りドライブ吟行や二泊三日のドライブ旅行を何回か計画し友人を巻きこんだが、そのときのスケジュールもほとんどグーグルマップのみで作成した。もはや仕事中にグーグルマップを眺めていれば、頭の中で旅程が勝手に組み上がるレベルになっている。まだまだ行きたいところがたくさんあるので、2026年もグーグルマップを眺めて過ごしたい。 金森三夢 亀鳴くや巴御前の吐息のせ 滴りや手拭浸し首に巻く 肌寒や鉄錆びあまた歩道橋 ケガの功名 年男の今年。まさか一年の三分の一を病院のベッド上で過ごすとは…… 「滴り」と云う季語を求め山道を彷徨っての不首尾。古稀を迎え三年で二度の全身麻酔のオペはきつかった。腎臓癌、世界一周クルーズ、そして圧迫骨折。一年おきの天国と地獄。死を見つめ、異郷での悦楽、痺れと激痛との格闘、いつも人生の良き伴侶である俳句と愚妻が寄り添ってくれた。 たび重なる入院と病院食のおかげで体重は学生時代に戻り、血糖値は正常値。糖尿の担当医に「ケガの功名」と大笑いされた。 さて来年はどんな年になるのだろう?!人生は甘渋苦。来年こそ休会なしで呆け防止の句会に励みたいものである。 前島裕子 床の間に祖母てづくりの手毬かな お薄点てゆがむ玻璃ごし花吹雪 黙しゐて母のかたはら緑さす 年には勝てぬ 今年も残すところわずか、振り返らざるをえない年でした。 身体には自信があったのですが、後期高齢者を前にして、帯状疱疹、歯の根元の炎症から唇がはれあがってしまった。どちらも大事にはいたらず、春の吟行会には参加できたのですが医者通いを余儀なくされた。 寝込むことはなかったのですが、身体がすっきりせず完治まで半年ぐらいかかった。年には勝てぬことを痛感。 来年は身体に充分留意し、自分に納得できる句が一句でもできるよう学んでいきたい。 見原万智子 ヒヤシンス登校しない子の瓶も どうだんの衣広げり巴塚 クリスマス会話ロボット待たせをり おあいにく おさとはたいそうな器量よしで、小学校もろくに行っていないが夫の古い教科書で漢字を覚え、両手足の指を使って鶴亀算ができたという。 昔のこととて婚家側の一方的な理由で離縁され、二年。島田の帯祭りの時分でもあったろうか、大井川の橋の真ん中でばったり元の夫に再会してしまった。 ひとこと「…どうだ、元気か?…」と男は聞いてきた。 ややあって「ふんっ、これから佳い人に会いにいくところだよっ」と言うが早いか、おさとはその場を走り去った。決して振り返るまい。 それからほどなく、おさとは再婚した。 後年、私は何度となくこの話を母から聞かされた。そのたびに「ひいおばあちゃんはデートの約束なんか無くて、会いたかったのは目の前にいた元のご亭主だよね?」と私が言い、母は満足げに頷くのだった。おさとに顔立ちも性格もそっくりだった母は、「いい女はツンで通さなければ。デレるなどもっての外」と信じ込んでいたふしがある。 あいにく私はすべてにおいて父親似。ツンデレすら気恥ずかしい。いつもデレデレで、しのいできた。 猪狩みき 雪華積むフロントグラス小さき首都 縦横に鳥の動線冬木立 地形図の尾根と谷なり白菜買ふ ことば 新聞でみかけた本のタイトル『群れから逸れて生きるための自学自習法』に惹かれ、向坂くじらという人を知った。詩人で小説家で自身で国語塾もしている人だという。「ことば」の捉え方、感覚がおもしろく、その作品を追っているところ。といって、彼女の「詩」はよくわからず、エッセイと小説を楽しんでいる。私はたいてい「詩」がわからない。「詩がある(ない)」ということが句会で話題になるたびにびくっとしている。 海野二美 船渡の山火事鎮圧 待ちわびし山林消火龍天に 飛機乱気流掌中の林檎の香 樸の未来 樸の構成員もずいぶん変わってまいりました。若き才能、またパリにニューヨークとワールドワイドに……。少数精鋭ではありますが、樸のこれからは楽しみですね。また私の大好きな文学講座も始まり、学生気分で勉強させていただけるのでありがたいです。編集や会計、また幹事等に惜しみなく励んでくださる皆様、本当にありがとうございます。樸の会員の方々のことは盟友と思っております。 俳句文学における絆は強し! 恩田侑布子万歳! AIの無性生殖去年今年 恩田侑布子(写俳)