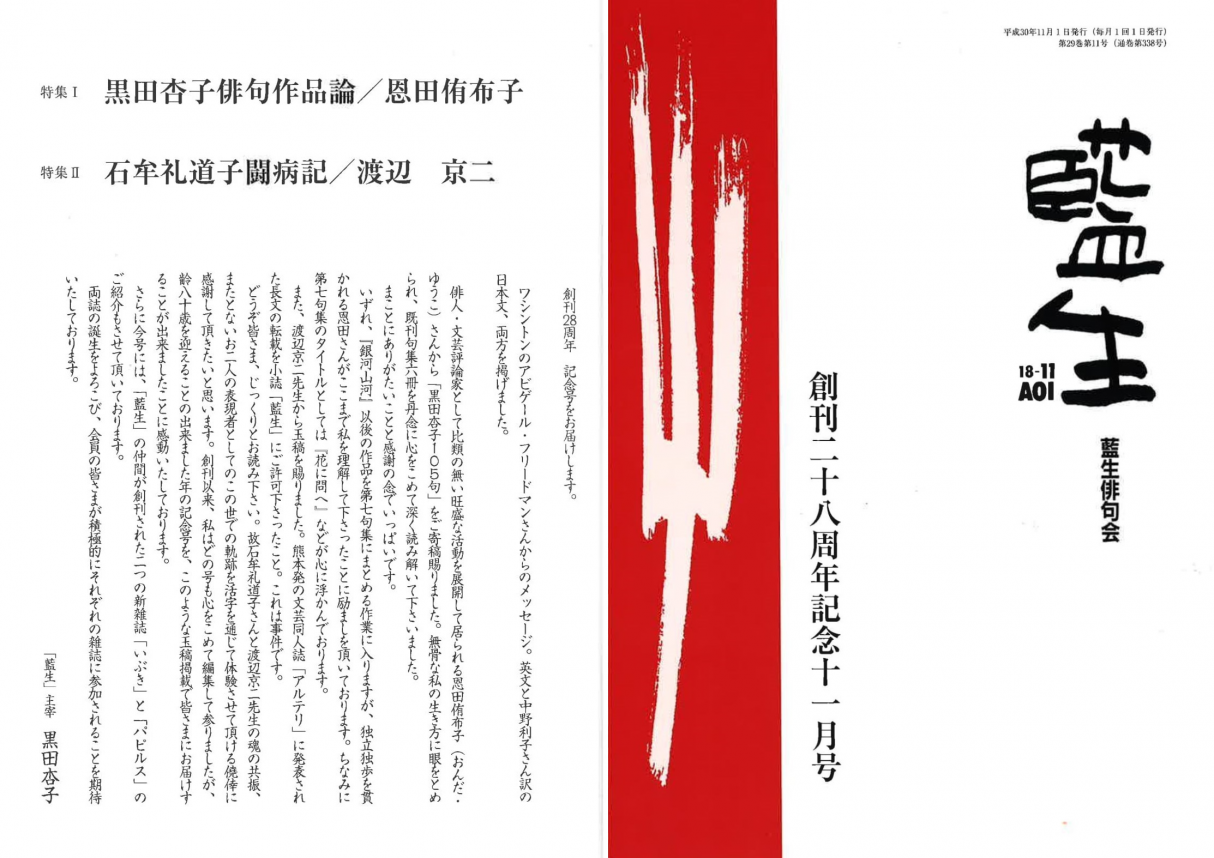俳句討論会「クローデルの日本―『百扇帖』をめぐって」が パリ日本文化会館で開催され、樸代表の恩田侑布子もシンポジストとして登壇しました。 ポール・クローデル(1868-1955)が、日本大使として勤務した最後の年にまとめたフランス語の句集『百扇帖』(Cent Phrases pour Évantails, 1927)について、フランス、アメリカの俳人/俳句研究者と現代日本の俳人、比較文学者が討論しました。
記
俳句討論会「クローデルの日本―『百扇帖』をめぐって」
日時:2019年2月5日(火)18時~
場所:パリ日本文化会館小ホール
座長:杉浦 勉(日本文化会館館長)
シンポジスト:芳賀徹、夏石番矢、
金子美都子、恩田侑布子、
アビゲール・フリードマン(米)
アラン・ケルベール(仏) ↓ クリックすると拡大します (撮影 佐藤麻里子)
俳句討論会「クローデルの日本―『百扇帖』をめぐって」が パリ日本文化会館で開催されます。樸代表の恩田侑布子もシンポジストとして登壇します。 ポール・クローデル(1868-1955)が、日本大使として勤務した最後の年にまとめたフランス語の句集『百扇帖』(Cent Phrases pour Évantails, 1927)について、フランス、アメリカの俳人/俳句研究者と現代日本の俳人、比較文学者の視点から捉え直します。
記
俳句討論会「クローデルの日本―『百扇帖』をめぐって」
日時:2019年2月5日(火)18時~
場所:パリ日本文化会館小ホール
Maison de la Culture du Japon à Paris
101 bis, Quai Branly, 75015 Paris
座長:中條忍
シンポジスト:芳賀徹、恩田侑布子ほか
ポール・クローデル『百扇帖』恩田侑布子訳 33作品抄出についてはこちら ※ 『俳句あるふぁ』2019年冬号にも『百扇帖』恩田訳の俳句47句、短歌21首、短詩10篇が掲載されていますのでどうぞご高覧ください。
「俳壇」一月号に掲載にされた恩田侑布子作品「青女」から二句を、樸俳句会で句座をともにする海野二美が鑑賞しました。 「青女」に寄せて
海野 二美 句歴十年にも満たず、選句眼も養い途上ではありますが、感銘を受けた二句について・・・ よく枯れて小判の色になりゐたり
新玉のあたまのなかをやはらかく 最近知人に亡くなる方が多く、死に様に人品が表れるものと感じる機会もあり、死が身近に思える事が多くなってまいりました。若者の言葉に耳を傾け、依怙地にならず、小判色に枯れて行けますよう、この二句を道標に生きて行きたいと思います。行く末に光が見出せた思いです。ありがとうございました。
川面忠男様がブログの転載をご了承くださいましたので、掲載させていただきます。川面様、いつもありがとうございます。 「俳壇」の恩田侑布子さん特別作品
俳人・文芸評論家で「樸」の代表、恩田侑布子さんから過日メールをいただき、月刊「俳壇」1月号に恩田さんの特別作品30句が載ることを知った。発売日の15日、最寄りの書店で「俳壇」を求めて読んでみた。恩田さんの言う余白がある句であり、どの句も味わい深いと思ったが、とりわけ以下の10句を選び私なりに鑑賞してみた。
琅玕の背戸や青女の来ます夜 一読して惹きつけられる句だ。琅玕は「ろうかん」と読み、ここでは「美しい竹」という意味になろう。青女は「せいじょ」で「霜・雪を降らすという女神。転じて、霜の別名」(広辞苑)だが、私は雪と思いたい。そうすると、青女という女神が雪女のイメージに重なり、「来ます夜」という措辞が幻想的な世界を伝える。青女は特別作品の題になっており、恩田さんも掲句を30句の代表と思っているのであろう。
霜ふらば降れ一休の忌なりけり 恩田さんは静岡高校の生徒であった頃、仏教書を読みふけったという。ウイキペディアによると、一休は「洞山三頓の棒」という公案に対し、「有漏路(うろぢ)より無漏路(むろぢ)へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」と答えて一休の道号を授かったという。有漏路とは迷う「煩悩」の世界、無漏路は「悟り」を意味する。 絶壁の寒晴どんと来いと云ふ これは30句を締める句。〈どんと来いと云ふ〉という措辞は〈霜ふらば降れ〉という恩田さんの心境と同じなのではないか。雪や霜が降ろうが、晴れようが、絶壁という煩悩は常に立ちふさがっている。それに立ち向かおうという心の鼓舞が伝わってくるような句である。 宝船手ぶらで来いと云はれけり 土産を持たずに行って宝を貰って帰る、ということではなかろう。手ぶらは心に何も持たずに来い、つまり心を無にして来いということではないか。そうすれば悩みはなくなり煩悩から解脱できよう。作者が恩田さんだと、私にはそのように感じられる。 群峯は羅漢ならずや冬茜 阿羅漢は仏教修行の最高段階に達した聖者。それらの表情はさまざまだ。冬の夕焼けに黒い影を見せる西の峰々に託して羅漢の修行を思うのであろうか。恩田さんも仏の境地に近づきたいと願っているのではないか。 淡交をあの世この世に年暮るる 君子の交わりは淡きこと水のごとく、の淡交である。この世の人との淡交は誰にもありうるが、相手があの世の人となると、どうであろうか。しかし、恩田さんが相手のあの世の人は芭蕉であったり、故人になった俳句仲間であったり、詩を介して自在に交流できるのであろう。
直近の俳人では金子兜太が思い浮かぶ。恩田さんは今年2月26日付け朝日新聞の「俳句時評」で「土の人」と題して兜太の〈よく眠る夢の枯野が青むまで〉を挙げ、次のように書いている。「芭蕉の〈旅に病で夢は枯野をかけ廻る〉への唱和であろう。芭蕉の夢はどこまで行っても藁色と金の条」と。藁色は草鞋を履いての行脚をイメージできるが、金の条(すじ)は金科玉条の条であろうか。 よく枯れて小判の色になりゐたり 枯葉は夕陽をあびて小判の色、つまり金色に光る。西方浄土の金色に通じる感じがする。冬の枯木はそんな世界に変わる。飛躍して言えば、人間も枯れれば仏に近づき金色の世界が見えてくるであろう。 まばたきに混じる金粉三ヶ日 正月には金粉入りの酒を飲む。それを〈まばたきに混じる〉と詩的に表現したのであろうか。恩田さんの俳句は、趣味の域を出ない拙句などと違ってなかなか答えが出ない。それだけ読者としては想像を楽しむことができる。 初富士を仰ぐ一生の光源を 〈一生〉は「ひとよ」と読ませる。静岡に暮らす恩田さんにとって富士山はしばしば眺める山であろう。喜怒哀楽それぞれの日に。人生は富士とともにあったと言っても過言ではないだろう。
私的なことだが、思い出すことがある。私が5歳の時、静岡の空襲で焼け出され、静岡育ちの母と二人で父の故郷である志摩半島の小さな町(現・三重県志摩市大王町波切)に疎開した。母は朝早く起きて伊勢湾の彼方にある富士山を見ようとした。そうして故郷を懐かしんだ。「見えた」と喜んだ母の声を憶えている。富士山は小さな紫の影だったが、母には生きる力の光源であった。 たまゆらは永遠に似て日向ぼこ 〈たまゆら〉は一瞬のことだ。それが〈永遠に似て〉と詠う。そういう心境と〈日向ぼこ〉という季語が合う。
ここで思い出すのは、曹洞宗開祖の道元の時間観だ。「時は飛去するとの解会すべからず、飛去は時の能力とのみ学すべからず」(正法眼蔵)、つまり時間は過去から現在、未来へと流れるだけではないと言う。恩田さんが芭蕉を思う一瞬、芭蕉は恩田さんの心の中で生き返る。過去が現在になる。それが永遠に似るということであろう。
以上10句について勝手な鑑賞をして楽しんだ。
川面忠男(2018・12・21)
◎『俳壇』一月号:特別作品「青女」三十句。 ◎『俳句あるふぁ』冬号:ポール・クローデル『百扇帖』18頁の大特集
・「仏詩人大使の生涯」恩田侑布子講演より
・『百扇帖』俳句・短歌・詩(恩田侑布子訳)
・芳賀徹先生と恩田侑布子の対談
等類がない俳句。それが石牟礼道子の俳句の最大の特徴である。現代俳人の句はどこか似通っていて、おうおうにして既視感につきまとわれる。一方、石牟礼の自前の感性と自前のことばは空恐ろしい。恐ろしいはずである。なぜなら、その自前は、個性などというものにもとづくのではなく、何万年とも「齢のわからない」精霊と風土を背負いこんだものであるのだから 。 「ふみはずす近代」 恩田侑布子
(『藍生』2019年2月号「石牟礼道子追悼特集」より) ↓ クリックすると拡大します
俳誌『藍生』(黒田杏子主宰)2018年11月号に恩田侑布子が「黒田杏子俳句作品論」を寄稿しています。
主宰のご承諾をいただきここに転載させていただきます。
黒田先生ありがとうございます。
↓ クリックすると拡大します
認定NPO法人丸子まちづくり協議会主催の俳句朗読&講演会に恩田侑布子が登壇します。 根っからの静岡人なので、地元での講演の機会に感謝しております。
東海道五三次で一番小さなまりこの宿。その大きな魅力を、ポール・クローデルの表現した日本の美から見つめ直してみませんか。とろろ汁の「待月楼」でお待ちいたします。
恩田侑布子 ↑
クリックすると拡大します ↑
クリックすると拡大します
投稿ナビゲーション
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。