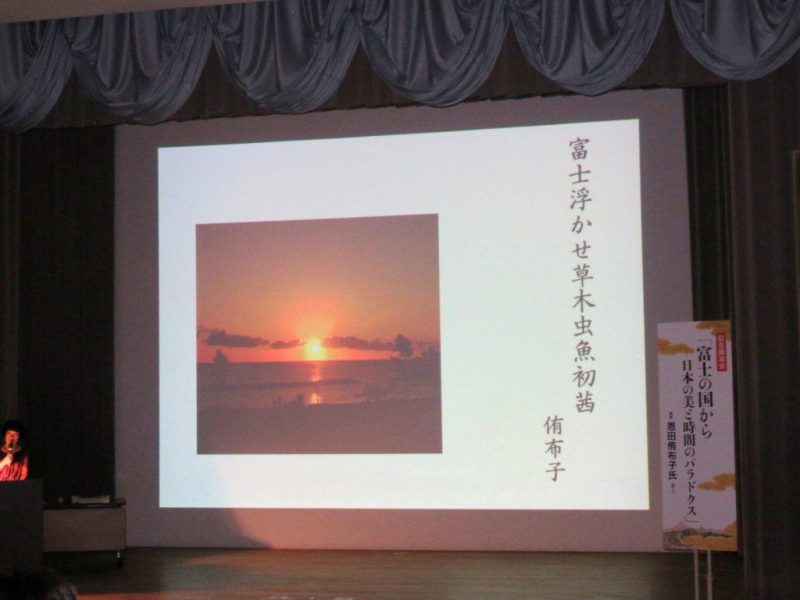平成30年1月19日 樸句会報【第41号】 新年2回目の句会です。入選4句、△1句、シルシ3句、・3句という結果でした。 兼題は「新年の季語を使って」です。 なお、1月7日分は特選、入選いずれもなかったため句会報はお休みさせていただきました。 今回の入選句を紹介します。(◎ 特選 〇 入選 【原】原石 △ 入選とシルシの中間 ゝシルシ ・ シルシと無印の中間) 〇初詣卯杖確たる師の歩み 杉山雅子 合評では、 「難しい言葉を使った、格調のある句」 「共感します。元気な師匠と一緒に初詣に来た。おめでたい情景」 「先生の人となりまで想像される。頑固な怖い先生だったのかな?でもそういう先生こそ慕われる」 「書道や技藝の先生でしょうか?」 「俳優の笠智衆を思いました」 などの共感の声がありました。 恩田侑布子は、 「うづゑは、卯の杖、初卯杖ともいう新年の季語。元は、正月初卯の日に地面をたたいて悪鬼をはらう呪術的なもので、大舎人寮から天皇へ献上した杖というが、今は初卯に魔除として用いる杖で、柊・棗・梅・桃などで作る。大阪の住吉大社、伊勢神宮、賀茂神社、太宰府天満宮の祭儀が有名です。静岡ではあまり馴染みがない難しい季語を使って、格調のある新年詠になった。正月の挨拶句として素晴らしい。こんな一句を弟子からもらえたら、先生はさぞかし嬉しいでしょう。確たるというところ、地面を叩く呪術的な祈りがリアルに感じられる。畳み掛けた季語も讃仰の気持ちと取ればいいのでは」 と講評しました。 〇初茜山呼応して立ち上がる 杉山雅子 この句は恩田侑布子のみ採りました。 恩田侑布子は、 「作者は元朝の幽暗に身を置いているのでしょう。初日の出を今かいまかと待っている。東の空がうす茜に染まり始めたと思うと、背後の山々がまるで呼び合うようにして、闇の中から初茜に立体感をもって浮き上がってくる。元朝の厳かな時間が捉えられている。二句とも杉山雅子さんの俳句で気迫がある。昭和四年生まれでいらっしゃるのに素晴らしい気力の充実です。今年も益々お健やかにいい俳句が生まれますね」 と評しました。 作者のお住まいは山に囲まれていて、そこから竜爪山(りゅうそうざん)(静岡市葵区にある標高1000m程の山)に登る人や下ってくる人をよく見かけるそうです。 〇光ごと口に含みし初手水 石原あゆみ 本日の最高点句でした。 合評では、 「上五から中七への措辞がうまい」 「情景がよく分かる。初日が射してきた。輝く水を口に含んだ。すらりと詠んで嫌味がない」 「新年のおめでたい感じがよく出ている」 「光ごと杓子で汲んだところを捉え、快感さえ感じます」 「素直にできているが、類句がないだろうか」 「うまいがゆえに既視感がある」 との感想が聞かれました。 恩田侑布子は、 「元旦に神社へ初詣したのだろう。御手洗で手をゆすいだあと、口に含む清らかな水が、ひかりと一体に感じられた。その一瞬を捉えて淑気あふれる句。過不足なく上手い。あまり巧みなので、類句類想がないかちょっと心配。なければいいですね」 と講評しました。 〇婿殿と赤子をあてに年酒酌む 萩倉 誠 この句を採ったのは恩田侑布子のみ。 合評では、 「あまりにも幸せな光景。うらやましさが先に立ってしまって・・・(採れませんでした)」 「おめでたすぎるのでは?“孫俳句”の亜流のような気がする」 などの感想がありました。 恩田侑布子は、 「“あてに”が巧み。酒の肴、 つま(・・)にという意味。まことにめでたい光景。この世の春。“婿殿”の措辞にすこし照れがにじみかわいい。似た素材の句に、皆川盤水に〈年酒酌む赤子のつむり撫でながら〉がある。でも、こちらは婿殿と三者の関係なので違いますね。ちょっとごたついているので、“酌む”の動詞は省略したらどうでしょう。 →“婿殿と赤子をあてに年酒かな”でいいじゃないですか」 と評しました。 [後記] 本日配布されたプリントに恩田侑布子は次のように書いています。 「新年詠は、ふだんなかなか出来ない大らかな命や大地の讃歌を」 大方の連衆が納得する中で、「新年をおめでたく感じない人もいる。自分も強制されたくない」と異議が呈されました。このような“異論”が遠慮なく提出され、議論に発展していくのも樸句会の良いところではないでしょうか。 恩田は「『“新年詠”のない句集は物足りない』とある書店の社長さんがおっしゃっていました。人生は、悲しいこと、苦しいことのあることが常態ですが、“新年詠”が一句あると句集が豊かになり、拡がりを持ちます」と述べました。 次回兼題は、「息白し」「スケート」「新年雑詠」です。 ※ 今回の句会報から通し番号を記すことといたします。(山本正幸)