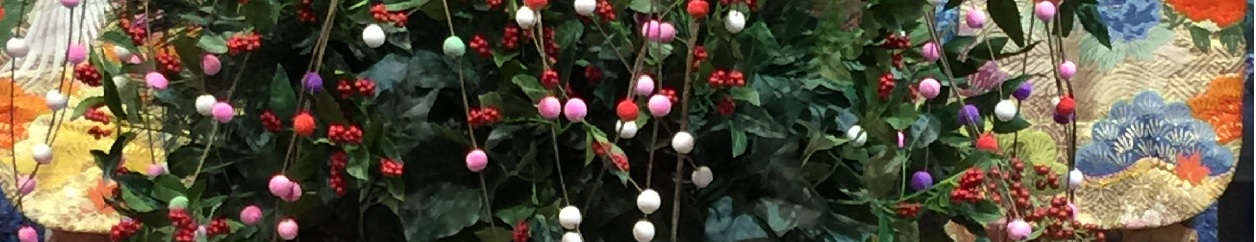令和7年11月3日(祝) 於:東京上野・東天紅 現代俳句協会大会 第八〇回協会賞受賞者への祝詞 恩田侑布子 ◎ 現代俳句協会賞 大井恒行様 『水月伝』祝詞 みなさまこんにちは。静岡の山の中から参りました恩田侑布子と申します。過分なことに本賞の選考を八年間務めさせて頂きました。 本年は昭和百年、戦後八〇年。同じく協会賞も第八〇回です。この伝統の節目に選考委員長を拝命しましたことを深く感謝いたします。そして記念すべき年を目覚ましい句集で飾って頂いたご受賞のお三方に、心からお祝いの詞(ことば)を申し上げます。 本年は水準の高い心を打つ句集が目白押しのまさに豊年満作でした。逆にいうと選考委員としては優れた句集にも涙をのまなければなりませんでした。並み居る競豪を押しのけ、満票を獲得し、堂々たる受賞を射止められたのが、大井恒行さんの『水月伝』です。 大井さんは、世の中に発することの叶わない声なき声、死者たちへの共感能力が並外れておいでの方です。そのやさしさをそのまま柔和なかたちにしないところに、すごみがあります。 私事で恐縮ですが、運動神経は3Bのくせに山歩きが大好きです。3Bはニビーなんてもんじゃない。ま、それはともかく、山登りは、緑豊かな樹林帯を抜けて、森林限界も越えて、ガレ場になりますね。大井さんの俳句は、その亜高山帯に立ち上がる、まるで五丈岩やオベリスクのような重量感を持っています。ゴツゴツした巌のような句です。例えば、 凍てぬため足ふみ足ふむ朕の軍隊 除染また移染にしかず冬の旅 ずしーんと来ます。『水月伝』は酸素の薄いところに咲く巌の花です。このやさしいお顔の作者の本質です。「花も紅葉もなかりけり」の岩場の花といえば、無季俳句です。無季は本協会の歴代の猛者たちが、志し、ゆき倒れになった俳句文芸の一つの気高い牙城です。その高みへの登攀の歳月が『水月伝』なんです。 さらに、本句集の奥深さは、亡き俳句の先達に捧げる追悼句に一章が設けられていることです。一昨年東北で客死された澤好摩さんを悼む句は、 極彩のみちのくあれば幸せしあわせ 澤好摩さんの肉声が聞こえてくるようです。俳句表現史という険難な道を歩き、行き倒れになった行者たちへの、この畏敬に満ちた鎮魂の章は胸に迫ります。巌の重量に深い共感が溶け込んでいます。山上の巌と地上の情(こころ)との融和に大井さんの男気を感じます。畏敬する兄と呼ばせてください。恒行アニい!、ご受賞おめでとうございます。 ◎ 現代俳句協会賞特別賞 武藤紀子様 『雨畑硯』祝詞 武藤紀子さんの俳人としての大成はひとえに師の宇佐美魚目と出逢われた運命にあったと拝察します。大きな俳句の遺産を私たちに与えてくれた魚目は、生前は俳壇的にも現代俳句協会員としても不遇でした。 しかし、そのいくつかの名句はすでに古典の風格をもっています。死後ますます声価の高い俳人です。武藤さんの俳句は魚目の心眼を継承しておられます。平易で無駄のない措辞はまるで武家屋敷の式台のように清らかです。言葉の空気感を手垢のつかないかたちで表現できる数少ない俳人の一人です。『雨畑硯』には近年にはめずらしいおおどかな心地よい時間が流れています。 春の雨舌一枚をしまひけり 棺の中に白桃のやうなひと 老成が枯れる方へはゆかず、自我を天地に解放する広やかな方向へ歩き出しています。近作を篩にかけた百句の厳選も潔いです。句集は見開きの右に俳句一句、左に短文という余白たっぷりの構成です。句集の新しいかたちといっていいでしょう。短文には俳文の香りがあります。俳文は子規たちの山会ですね。。句の説明に終わらず、自分にベタでもありません。はつらつとしています。無欲な文体から作者の愛すべき人柄が立ち上がってきます。 泉下の宇佐美魚目先生もさぞかしおよろこびでしょう。武藤紀子さん、良いご供養をなさいましたね。誠におめでとうございます。 ◎ 現代俳句協会賞特別賞 董振華様 『静涵』祝詞 北京のお生まれ、五三才という若さの董振華さんは越境文学のパイオニアです。散文にも長じられ、いま現在も『語りたい俳人』(コールサック社)という敬愛する物故俳人を俳人が語る聞き書きにも取り組んでおられます。 句集『静涵』は、俳句と漢俳を並列していて、それだけでも驚かされます。しかも日本語の俳句と漢俳は、どちらかを直訳したものではありません。日本語と中国語の二つの言語の根っこから、地べたから、二本の樹木のように立ち上がり、詩歌文学のゆたかな緑の葉を茂らせ合っています。これはまさに特別賞に相応しい新たなフォルムの句集の出現です。 路地裏に父の激励梅雨の月 北京の路地に梅雨時の満月がにじんでお父さんの励ましてくれる声。その空間に擬似的に潜り込んでしまいます。 人間錆びて真冬のまこと崩れそう 屈原を憶(おも)えば夏の月満ちて 繊細でいながら、悠然とした大河のような呼吸が流れています。大陸で涵養された気宇の大きさでしょう。壮観です。前途洋々、これからの俳壇の牽引者となられる大才の登場を心から喜びたいと思います。董振華さん。世界広しといえども貴方にしか書けない句集です。ご受賞、ほんとうにおめでとうございます。 最後に一言。お三方には共通点があります。ふふ。なんだかおわかりですか。俳句で煮染めた顔じゃない。煮染めたお顔をされていらっしゃらない。俳諧自由!です。誠におめでとうございます。拙い祝詞をお聞き頂き、ありがとうございます。 式典会場の末席から 編集委員 馬場先智明 報告というよりも、気ままな印象記という態で、当日、私の記憶に残ったお話や大会風景をいくつか、書き残しておきたいと思います。 まずは高野ムツオ会長、佐怒賀正美副会長らによる開会の辞に続き、現代俳句大賞を受賞された中村和弘さん(現代俳句協会・前会長)のご挨拶がありました。そのお話の枕だったと思いますが、「今日、大会が始まる前、会場の東天紅の前の不忍池を一回りしました。池を一面に覆う敗荷(やれはす)の風情もいいもんだなぁ…と思いました」と、さりげなく季語を入れて話を始められたのです。俳人の挨拶とはかくあるべきものかと、思わず心に留め置きました。 このあと恩田侑布子が〈現代俳句協会賞〉選考委員長として登壇。受賞者3人に熱いエールを贈ります。お話の内容は、いただいたスピーチ原稿を上に掲載しましたので、お読みください。 私たち樸の連衆にはすでにお馴染みですが、虚を衝くような意外性を孕みつつ決して的を外さない比喩表現は健在。そして受賞者とその作品への共感力に満ちた言祝ぎは、ユーモアを交え、跳ねるように楽しげに、若々しい。その口調は、会の重鎮の方々の俳的 “渋み” の良さとはまた対照的で、目が覚めるようでした。 しっかり覚えておこうと心したのも束の間、スピーチの最後、会場を埋める人々に放った謎かけ「このお三方に共通するものはなんだかお分かりになりますか?」に、頭のメモも吹き飛んでしまいました(前掲のスピーチ原稿があって助かりました)。 「俳句で煮染めた顔じゃない。俳諧自由! です」という、私の想像力をはみ出した回答。これには正直驚きました。旧体制に叛旗を翻さんとする革命家の宣言…ではもちろんありませんが、そんなインパクトを感じたのは私だけでしょうか。明るく楽しげに言われたので、これって恩田侑布子独特のちょっと刺激強い系のユーモア文体か、と会場の皆さんも受け取られたとは思いますが……。 それにしても「俳句で煮染めた顔」という卓抜な比喩。ひと昔前の文学青年は、「生きるとは何か…文学には何ができるのか…」と眉間に深い皺を寄せて、まさに(文学で)煮染めた顔をしていましたね。それはともかく、この会場にそのような顔をした方がいはしないだろうかと、ほんの少しヒヤッとしたのでした。 このあとに、評論賞、作品賞、新人賞など各賞の受賞者表彰が続きます。 特に新人賞では、俳句甲子園に出場された若手もいて、ある意味、俳句の世界にもエリートコースができているのかな、とおもしろく思いました。 受賞者のスピーチでは、何人か、似たコメントをされていて、そのいずれも心に残るものでした。曰く「日常のささやかな瞬間を捉えたい、移ろいゆく日々に対する愛しい気持ちを俳句にしたい」。彼らの清新な志は、わが老体の胸にもジーンと沁み入りました。 式典の最後は、高野ムツオ・現代俳句協会会長による記念講演「わたしの昭和俳句」。 昭和22年生まれの高野ムツオが、師との出会いを求めて彷徨した若き日のお話、とても印象的でした。 どの俳人に師事しようか、と考えた時、高柳重信、飯田龍太、金子兜太の3人が候補に上がったそうです。 まずは高柳重信。「カッコよかったなぁ…」と昔日を思い返してか、壇上で何度も繰り返されました。短歌の世界では、塚本邦雄を、まさに同じ言葉で回顧していた歌人(永田和宏さん)がいましたが、旧来の型を破壊する革新的な詠み方は、「カッコいい」という少年言葉でしか言いようがないほど素敵で衝撃的なものだったのでしょう。高野さんは直接、高柳重信に会いに行ったそうです。そんな会見の中で、忘れられないエピソードについても話されました。当時、『富澤赤黄男全句集』が欲しくてたまらず相談したら、「そんなに欲しいなら、自分で作ればいい」と突き放されたと。赤黄男の句を全部収集して、自分の手で一冊の句集を作ればいいじゃないかと言われたそうです。 次に飯田龍太。龍太の句には、そこに住んでいる人の息吹を感じて強く惹かれたが、敬するあまり、逆に近づくことができなかった、と。 そして金子兜太。友人から「金子兜太は、自宅ではいつも裸らしいぞ」というので、まさかと思いながら訪ねると、本当に褌一丁で出てきたのでびっくりしたと言います。結局、のちに師事することになったのが金子兜太ですが、何が決め手になったのかといえば、兜太の中に「俳句の原点を見たから」ということでした。それは、ひと言で言えば “知的野性” だと。この相反する概念の結合、私は初めて聞いたような気がしますが、それが金子兜太なのですね。 あれこれ楽しいエピソードをご披露くださいましたが、演題にもなっている「私の昭和俳句」についての最後のお話は、とりわけ記憶に残るものでした。 「昭和の俳句で一句を選べと言われたら…」と切り出されたので、グイッと身を乗り出しました。 戦争が廊下の奥に立つてゐた という渡辺白泉の一句でした。 昭和の一句に “無季” の句を選んだわけです。どれを選ぼうかと悩み抜いた挙句、選んでしまうのは、どうしても無季の句なんですね……と、やや苦渋を浮かべた表情で言われたのは、とても印象的でした。ほかにも、 切り株はじいんじいんと ひびくなり 富澤赤黄男 を挙げて、やっぱり無季を選んでしまうご自分の中の揺らぎを扱いかねているふうにも見えました。私には非常に興味深いお話でした。 うろ覚えの記憶に頼って書いたので、きっとスキマだらけですが、いずれどこかの俳誌に掲載されるかもしれません。ご興味があれば、そこで改めて正式版をお読みいただければと思います。 2025.11.10 記