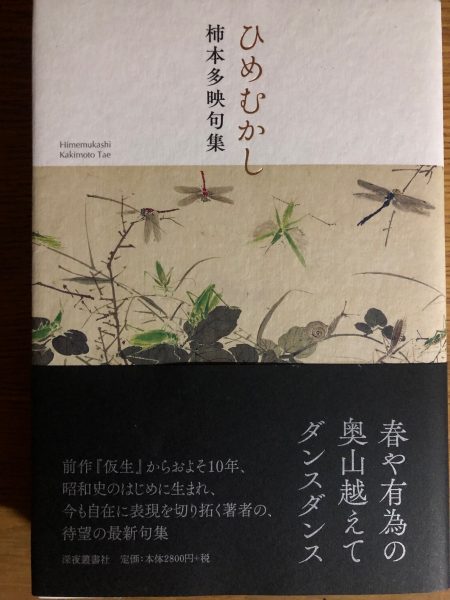
悠々たる自在境。発想がこの世を三尺離れている。イマジネーションの飛躍は柔らかみと鋭さを併せ持ち、独特の娑婆っ気がスパイスを添える。蛇笏賞受賞から三年後の、おん年九十二歳。幻視者としての俳人・柿本多映が屹立する句集である。 (恩田侑布子・謹選評) ↑ クリックすると拡大します

恩田侑布子の「竹百畳」を読んで 角川『俳句』2023年9月号特別作品21句 上村正明 恩田侑布子の俳句は、難しい言葉が少なく、リズミカルなので読みやすい。駆け出しの私にも「優しい」句が多い。それに引き換え、俳句誌の巻頭部を飾る、多分高名な諸先生の俳句は「字余り」や「字足らず」、難しい言葉が多用されていて、極めて読みづらい。こういう句を見ていると、盆栽展に並んでいる、やたらと曲がりくねる古色蒼然とした盆栽を思い出してしまう。 たまたま購入した、角川俳句・2023年3月号に掲載されていた先生の「はだかむし 自選20句抄」に遭遇し、これらの句が比較的容易に理解できたことが、樸俳句会の門をたたくきっかけとなった。 結ひあぐる黒髪真夜の瀑となれ 普段、女は、男の前では、受動的スタイルを崩さない。男はそれを見て、女をそう理解しがちである。このような男の一人である私は、この句を読んで、女もやはりそうなのかと安心した。 男、女といっても、性さがには強弱があり、異質のものまである。この句に詠まれている男、女の性さがはきっと強いに違いない。 走つても/\土手ちゝろ蟲 この句を見れば、駆け出しの私だって、山頭火の代表作を思い浮かべ、それと比較したい誘惑にかられる。先生の意図されているところであろう。「走っても」が「分け入っても」に、「ちゝろ蟲」が「青い山」に対応している。「土手」を省略すれば、字足らずの句ともいえるが、立派な自由律句だ。 山頭火の句と並置しても、二つは、存在感を持って並び立っている。いや、むしろ、先生の句の「土手」が余分のようにさえみえる。 燻りし男を連れて大花火 女が男を想っている気持ちは痛いほどわかる句だ。このような女が身近にいることは男にとってありがたいことだ。しかし、男が日々格闘している世の中は、女が思うほど甘くはない。大花火くらいで癒されることはないかもしれない。しかし、そんな時でも、女には、男を立ち直らせるだけの力があることを知っておいてほしい。 ゴーヤすゞなり苦き一生こそ旨き 755になっても、リズミカルなのが、恩田侑布子の句の特徴であろう。しかし、「苦い一生こそが旨さ」という言葉に軽さを感じてしまうのはなぜだろう。恩田侑布子が一生を語られるには、まだ年季が足りていないからなのかな。 百畳の竹林ぬけし良夜かな この「特別作品21句」の題が「竹百畳」なので、この句が掲載21句を代表する句なのであろう。 百畳ほど広い竹林は現存するであろうが、ここでは比喩として拝見したい。とすれば、先生は、抜けるのが容易ではない苦難の道を歩み続けてこられた結果、新境地に達せられたと自覚されたのであろう。さすれば、まさに、誠に良き夜である。新境地に達せられた後も、恩田侑布子は、コオロギの鳴く長い土手の道を走り続けられることであろう。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 樸に、最高齢の八十五歳で半年前に入会された上村正明さまは、メキメキ腕を上げられ、拙句に対しても忌憚なく伸びやかな鑑賞文を書いてくださいました。「まだ年季が足りていない」とふつう言われたらギャフンですが、上村さんなら、小さい頃から欲しかった「兄貴」から言われたような気がします。上村さんに感謝し、ご一緒に末長く俳句を楽しめますことと、益々の俳句の豊作をお祈りいたします。 (恩田侑布子)

好きこそものの、、、 小松浩 ときおり、いや、かなりしばしば、句会の直前になっても句が全く作れなくて、投げだしたくなることがある(これぞ「投句」?)。そんなさなか、8月初めの句会で恩田代表から、こちらの胸の内を見透かされるような一言があった。「投句は休みグセをつけたらダメですよ、皆さん。1回休んだらずーっと下に落ちますからね」。 確かに、継続こそが力だ。引き合いに出すのは気が引けるが、王、長島からイチロー、松井ら超一流のプロ野球選手は、他の誰より練習のルーティンを大事にし、人一倍の努力を続けたからこそ、あれだけの実績を残したと言われている。かの大谷選手などは、試合以外の時間を、ほとんどトレーニングと食事・睡眠にあてているのだとか。才能とは天賦のものではない。努力を継続できる、強い意思のことなのだ。 ずいぶん前の話になるが、ある有名な書家に展示会でお会いした際、すごいですね、自分は書の才能がないものですから、と、何気なく口にしたことがある。そのとき、その書家の方がニコニコ顔で話された言葉が、今でも忘れられない。「書はどれぐらいやりましたか? 自分に何かの才能があるとかないとかは、何十年かやってみて初めてわかるものですよ」。己の軽々しさに、私の顔からは火が出ていたかもしれない。 一つのことを継続できる意思の根っこには、いったい何があるのか。 芸術でもスポーツでも、成功者はよく、「辞めたいと何度も思ったけど、続けてきてよかったです」と言う。一家を成した音楽家が、小さな子どもの頃、怒鳴られて泣きながらバイオリンを何時間も練習させられていた映像などを見るが、たとえ理不尽な下積み時代であっても、その人は、成功の代償として受け入れているのだろう。 私を含め、会社員としての仕事を平凡に続けてきた普通の人間にも、最後までやり遂げたという達成感の裏には、辞めたくても辞められなかった家庭の事情とか、辞める決断ができなかった優柔不断への悔いが、あるのかもしれない。辛かったけど続けてよかった、と思えるのは、ようやくゴールに立って後ろを振り返った時だけだ。 いや、本題は俳句のことである。なぜ俳句を勉強し、俳句を作るのか、と聞かれたら、今の自分には、それが好きだから、としか言えない。継続の源泉は「好きだから」。裏返せば、好きでなくなったら辞めればいい、という気楽さもある。リタイア後の趣味の良さは、苦節何年、艱難汝を玉にす、と気張らなくてもいいことだ。古今の名句を知り、句会仲間の良き作品を味わい、「ああ、いいなあ」と無条件に思える心。これを持っているから、恩田代表の愛の鞭も、パワハラではなく甘い喜びになるのである。 好きなものに理屈はいらない、という点では、文学は音楽に似ている。モーツァルトとビートルズのどっちが素晴らしいかを論じたり、演歌好きの人に、なぜサザンやユーミンを聴かないのかと難癖をつけるのは、野暮というより無意味なことだ(自分は藤圭子も好きです)。音楽の好みが完全に個人的な領域のものであるのと同様に、文学の好みも、理屈ではなく、個人的な感受性の領域に属するものであると思う。 問題は、この先、好きこそものの上手なれ、の道を進むことができるのか、それとも、下手の横好きで終わるのか。「休んだらずーっと下に落ちますよ」と脅されても、そもそもまだ底辺で足掻いている自分には、どうせこれ以上は落ちようがないしなあ、と半分開き直る気持ちもなくはない。ただし、昨年9月の樸入会から1年、毎月6句の投句は欠かしたことはないし、これからもきっと欠かさないだろう。なぜなら、「ああ、いいなあ」とため息をつきたくなる素晴らしい句が、たくさんあるから。自分もいつかいい句を作りたい、という気持ちだけは、持ち続けていたい。かの漱石先生も、『こころ』の中で、「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」とおっしゃっておられるし。 (2023年8月21日)

2023年7月16日 樸句会報 【第130号】 連日のように熱中症警戒アラートが発表され、以前の7月の風景を忘れそうな日々が続いています。季語は、季節の変化を繊細に捉えて長い期間をかけて生み出されてきたのだと聞きますが、最近の気候変動によって今後も変化していくのでしょうか。そんな目で俳人の句を鑑賞するのも面白そうです。 今回の兼題は「涼し」「日傘」「ビール」、入選2句、原石賞2句を紹介します。 ○入選 指ながき男の選ぶ日傘かな 小松浩 【恩田侑布子評】 先頃まで日傘は女性のものだった。紫外線の害がいわれ、猛暑日が増えた現在では、若い層を中心に男性でも日傘を差して歩く人が珍しくない。作者はまだ、やや抵抗のある世代らしい。店頭のメンズ日傘のコーナーにさっきから男性がいる。見るともなく見ていると、ほっそりと長い指が選びあぐねている。力仕事や農作業などとは、一度たりとも縁がなさそう。選んだ日傘もユニセックスの軽さ。現代の都会生活の一コマをさらりと描いて涼味がある。 ○入選 父母の馴れ初め聞きし缶ビール 活洲みな子 【恩田侑布子評】 「父母の馴れ初め」に「缶ビール」が効いている。お見合いなどのかしこまった席ではなく、日常の場でひょんなことから出会ったという縁の不思議さ。プルトップ缶を両親と自分の三人で次々開ける軽快な響きと泡のさざめきは、仲の良い両親から生まれ育った満足感を存分に伝える。父と母の若かりし日へ楽しい想像が広がる句。 【原石賞】蝙蝠にベクトルの始点は何処? 益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 「ベクトルの始点は何処」が出色。確かに蝙蝠はどこから来たのか、そして、どこへ向かうのか、永遠の謎のよう。ただし、原句の「?」は、読み下した時のリズムの悪さを補うためのものに思える。調べの不安定さを解消するには、順序をひっくり返し、下五に五音の季語を据えるとよい。 【添削例】ベクトルの始点はいづこ蚊食鳥 【原石賞】日傘して区割の墓苑の果てもなし 天野智美 【恩田侑布子評・添削】 大都会の郊外に広がる広大な霊園だろう。住宅の何丁目何番地ではないが、墓地の住所もブロック割りされ、さらに縦横に伸びる通路には符牒が振ってある。のっぺりとした平面に茫漠と広がる墓石の群が見えてくる。まず、中七の字余りを解消し、次に、炎天を墓参に訪れて途方に暮れる思いと、うろうろと墓苑をさまよう姿の小ささを座五の「白日傘」に象徴させたい。 【添削例】果てもなき区割の墓苑白日傘 【後記】 今回は、樸俳句会にとって3ヶ月に一度の対面の句会でした。前後左右から声が飛び交い、心なしか会話も弾み、以前に行われていた対面句会の楽しさが蘇ってきました。 一方で、樸のZoom句会は10ヶ月目に入りました。静岡県外や海外に居る仲間が増え、これまで以上に多様な句に触れる楽しさを感じています。同じ兼題からこんなに自由な発想ができるのかと驚いたり、知らない言葉を目にして日本語の豊かさに触れたり…。まだまだ自分の感じている世界は小さいなぁと、反省することしきりです。 これからも多くの方に御参加いただき、樸俳句会の裾野を広くして豊かな句の世界に触れていくことと、たまにリアルにお会いして親交を深めていけることを楽しみにしています。 (活洲みな子) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) ==================== 7月2日 樸俳句会 兼題は「夏至」「登山」「凌霄の花」です。 入選3句、原石賞1句を紹介します。 ○入選 門柱と凌霄残る駐車場 天野智美 【恩田侑布子評】 「門柱と凌霄」だけが「残る駐車場」で、「だけが」が省かれている。すでに既存の家屋は解体され、更地になって駐車場として利用されている。しかし、まだ門柱だけは残り、凌霄花が取りついている。家族が住んでいたのか、旅館もしくは店があったのか、往時の夏と同じように咲き誇っているのである。真夏の凄まじさが感じられる。 ○入選 緑蔭にボタンダウンは小紋柄 益田隆久 【恩田侑布子評】 おしゃれな作者は他人の服装にも敏感。江戸小紋のような和風の繊細な木綿柄を、アイビールックのボタンダウンに仕立てた気の利いた和洋折衷の夏シャツで、緑陰におやっと目を止める涼しさ。軽快な小品である。 ○入選 禊祭 夏至の朝綱ゆったりと夫婦岩 上村正明 【恩田侑布子評】 伊勢の二見浦まで出かけて、暁闇から禊祭を修された作者。実地の海風に身をまかせたがゆえに「綱ゆったりと」の措辞が自然に口をついて出た。男岩と女岩は、猿田彦大神を祀る興玉大神おきたまのおおかみを拝する鳥居でもあり、日の出の遥拝所でもある。綱が海面上に弧を描いて、その果てから夏の朝日が登ってくる。太陽を崇拝し、根の国に憧れた古代人と、時を超えて一体化した夏至の朝ならではの満足感。品格ある吟行句。 【原石賞】浜通り蜥蜴の色に時止まり 益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 前書きがないと、福島県の海岸地域である「浜通り」を連想する。作者は、小泉八雲が避暑地とした焼津の浜通りが「蜥蜴の色」という。ならば、全国の読者に誤解を与えないために「焼津」の前書きが必要になる。さらに地元の人が、毎年滞在してくれた八雲を偲んで「八雲通り」とも呼んでいるなら、その別称の方がより陰影があって面白い。句末は連用形で流してはもったいない。碧い時を止めよう。 【添削例】 焼津 八雲通り蜥蜴の色に時止まる

小田島渚さんは2022年に第39回兜太現代俳句新人賞を受賞され、第一句集『羽化の街』を出版されました。恩田侑布子による『羽化の街』句集評を『小熊座』2023年7月号より転載いたします。 小田島渚句集『羽化の街』(現代俳句協会2022年10月刊) 再生の森 恩田 侑布子 (「樸」あらき代表) 視点の意外性 ユニークな大型新人の登場である。小田島渚の処女句集『羽化の街』は未知の白南風を孕んでいる。 何といっても切り口の意外性が出色。 芋虫に咆哮といふ姿あり 毛も棘もない青虫は、いたっておとなしい生き物だ。その地味ないのちが「咆哮」とは。しかし、これは虚仮おどしではない。葉の上や、転がり落ちた土の上を進む姿をよくみてみよう。尺取虫のように体を縮めてオメガの記号さながら背中を精一杯高めたかと思うや、今度は、前途に向かって筒状の胴を思い切り伸ばす。その瞬間、頭の先が空を向く。泳ぐのである。作者は刹那、無音の「咆哮」を聞いた。オメガはギリシャ語アルファベットの最後の文字だ。最終にして究極の存在から、たったいま咆哮が放たれたのである。 潰されし卵はあまた雲の峰 「雲の峰」と潰された多くの「卵」との取り合わせは、ありそうで無かった。荷台から大箱ごと滑り落として道にぐちゃぐちゃになった黄と白の氾濫を実際にわたしは見たことがある。なまなましさは禍々しさだった。ダブルイメージとして、裏に静かな日常がほの暗く張りつく。毎朝、殻を割って溶き潰す卵焼きの甘さはたまらない。日常の幸せは日の目も見ず蹂躙される無数のいのちによって成り立つ。地平線には琺瑯質の峯雲がかがやきわたって。 震へたる署名の文字や葡萄枯る 渚は憧れの作家のサイン会につながった。自分の番が来た。栄光の名前がいま、わがものとなった本の扉に書かれる…はずが、震顫する手、よろめく字。黒々とたわわな房をつけていた葡萄の木には、もはや水気がない。権威となった人の無残な芸術の死。辛辣な批評精神が異彩を放つ。 感受のダイナミズム こうした斬新な視点はすぐれた感性からもたらされる。感覚のよろしさは次の句群からも明らかである。 紫陽花の冷たさに触れ巡り逢ふ 萼片の密集する紫陽花の団々とした姿に「冷たさ」を感受する意外性。ちりばめられたアイウエオ五母音の配置が七変化さながらに美しい。「逢ふ」人と、梅雨冷えのある日、別れるであろう余韻が水脈のように尾を引く。 緑蔭やどの唇も開かれず 〈緑陰に三人の老婆わらへりき〉を思う。しかし、三鬼ほど悪魔的ではない。共通するのは「緑蔭」特有の明暗の夢魔感である。わらう老婆の皺に対して、こちらは「どの唇」もぽってりと肉感的だ。口から始まる深い管は一本ずつ内側へ閉じている。唇と管は樹幹の相似形となって静まり返る。虚と実の混淆が若々しい。 白南風や軋む音して羽化の街 白南風が吹いて街が羽化するだけならイメージで終わった。「軋む音して」がリアル。三・一一から復興し、変貌する未来都市は、そこで暮らした人々の思いを過去へ置き去る。言葉を奪われたものたちの哀しみに街は「軋む」。 こうした水準の俳句が全編に揃えば間違いなく圧巻の句集であった。が、まだ「俳句を独学ではじめた二〇〇九年」からわずか十三年である。溢れる才能が暴走した〈鵙の贄増え夕空の渦巻きぬ〉、幻視に至らず自壊した〈白鳥は悲恋を咽に詰まらせて〉、散文叙述体の〈蜂蜜に溺るる心地春の夢〉など未消化な句もある。小田島渚には胆力という美質がある。悠々と課題を乗り越え、大成してほしい。 大柄な句群 俳人の力量は瑕きずのない句を揃えることではない。人を感動させる大柄な俳句をつくれるかどうかだ。最終章「流星のたてがみ」は、小田島渚の作家魂が最も躍動している。 泥沸騰冬満月をあまた産む 異界の光景といえよう。ひとけのない沼沢地の泥が沸騰し、「冬満月をあまた産」んでいる。中国の古代神話に十の太陽がある。一本の木のてっぺんと脇に黄金の日が実る彫刻を見たことがある。が、月は知らない。三橋鷹女の遺作〈寒満月こぶしをひらく赤ん坊〉は浄らかなみどりごの掌から寒月が一つ生まれる。小田島渚の煮え激つ泥沼からはあまたの冬の月が出現する。先の〈震へたる署名の文字や葡萄枯る〉の玉座に座る老大家への幻滅は、ここに来て、沸騰してやまない作者自身の創作意欲に、しかと着地してみせるのである。 喪ひし舌を探しに寒林へ 寒々しい裸木の森へ、作者は何を探しに行くというのか。「喪ひし舌」だという。今朝もいつも通り、遺伝子組換の輸入納豆を食べた。化学調味料のタレに不満はなく、AIの管理下で悪無限のように産まれる卵はキレイだ。空気を読んで大人になり、フェイクニュースと「いいね」に、ペラペラに痩せこけた舌よ。二枚舌よ。そのむかし、ふっくらと大地から生えていた厚い一枚の舌は、何処いずこ。 寒林の奥に遠近法の消失点はない。ピカソのキュビスムの絵のように、この寒林は崩壊と組成が同時進行の迷宮をなす。渚は真実のぶ厚い舌を求め、寒木の影の網目をさまよう。江戸中期のロマネスクの詩人蕪村は〈桃源の路地の細さよ冬ごもり〉と詠った。現代人の原郷はもはや桃の花咲く洞窟の奥には無い。作者の回帰願望もデラシネの追懐ではない。寒林への遡行は切実な再生への祈りである。 鷹に掴まれ淵源の森見たり 「鷹に掴まれ」て小人になったかと思いきや、赤子に、いや胎児に、いや未生以前のいのちになって、渚は遡源する。その森のなんというゆたかさ。眼力の勁さ。 エピローグ 背中にも目のある巨人青嵐 後頭部でもお尻でもなく、背中に「目のある」巨人とは誰か。彼は全てを背負ってきたのに、いまはもうデイパックすら背負わない。無防備な背中が剥き出しである。後ろの生き物へやさしい眼差しをそそぐ巨人は、童話と哲学の結婚から生まれた。〈青空の一閃となり飛び込みぬ〉。そう。青空の瞳をもつ天の渚は、蒼穹に飛び込み、さらなる佳什を現代俳句にもち来たることであろう。