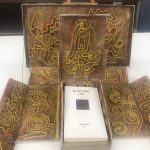2021年11月24日 樸句会特選句
銀杏落葉ジンタの告げし未来あり 田村千春 落葉は数しれずありますが「銀杏落葉」といい切ったことで映像が鮮やかに浮かびます。
「ジンタ」は下町の楽団。ちんどん屋と一緒によくアコーディオンを奏でたりしていました。作者はあったかくて時に調子っ外れになるメロディーの流れるなか、銀杏落葉を踏んでどこかに急いでいました。その時の情景がありありと胸に迫ります。ジンタが告げていたのは、はるか未来であったこの「今」です。今にたどり着いた作者の胸に、過去の銀杏落葉のあざやかな黄色と、人々の囃した音色…茫々の思いがこみ上げてきます。その時、一陣のつむじ風に黄色の扇面の落葉が一斉に空に舞い上がり。過去から未来へ、はるかな時間がつながります。「ジンタ」という死語になりかかったことばを一句はなつかしく蘇らせてもいます。
(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2021年7月4日 樸句会報 【第106号】
ここ何年も記憶に無い七月上旬の大雨。
被害に遭われた皆様には謹んでお見舞い申し上げます。
雨もようやく小降りになった七月四日。リアル参加とリモート併せて16名の連衆が句座を囲みました。 兼題は「茅の輪」「雷」「半夏生(植物)」です。
特選3句、入選4句を紹介します。 ◎ 特選
八橋にかかるしらなみ半夏生
前島裕子
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「半夏生」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
一列に緋袴くぐる茅の輪かな
島田 淳
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「茅の輪」をご覧ください。
↑
クリックしてください
◎ 特選
言はざるの見ひらくまなこ日雷
古田秀
特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「日雷」をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
雷遠く接種の針の光りけり
山本正幸 【恩田侑布子評】
貴重な時事俳句。コロナワクチンの接種をする。明日、痛みや副反応は軽くすむだろうか。本当に効くか。遠雷のひびきとあいまって不安がよぎる。日本は、世界は、今後収束局面に入っていけるだろうか。このゆくえは誰にもわからない。針先のにぶいひかりと遠雷の聴覚のとりあわせが、さまざまな感情を呼び起こします。
○入選
かへり路迷ひに迷ひ日雷
田村千春 【恩田侑布子評】
帰りたくない気持ち。どうしたらいいかだんだん自分でもわからなくなる切迫感。日雷が効いています。絵にも描けないおもしろさ。
○入選
白き葉のゆかしく揺れて半夏生
猪狩みき 【恩田侑布子評】
平凡という批判もきこえますが、むずかしい一句一章の俳句が、いたって素直。「ゆかしく揺れて」が半夏生のしずかさを表して、しかも清涼感がある。句に清潔なかがやきがあります。
○入選
躙口片白草へ灯を零し
田村千春 【恩田侑布子評】
草庵の茶室での夏の朝茶。そんなに本格的でなくても、夕涼みの趣向のお茶かもしれません。躙口のあたりの小窓から漏れる灯が、露地の脇に生えている半夏生の白い葉にかがよう繊細な光景。いかにも涼し気な日本の情緒。半夏生でも三白草でもなく「片白草」の選択が秀逸です。
本日の兼題の「茅の輪」「雷」「半夏生(植物)」の例句が恩田によって板書されました。 半夏生
今回の兼題の一つ「半夏生(植物)」について、恩田から補足説明がありました。ドクダミ科の多年草。半夏生(七月二日)の頃、てっぺんに反面だけ粉を吹いたような真っ白な葉を生ずる。半化粧の意味もある。片白草。三白(みつしろ)草ともいいます。ハンゲと呼ばれるのはカラスビシャクというサトイモ科の別の植物。これとは別に時候としての「半夏生」もあり、句作にも読解にも注意するようにと、それぞれの例句を挙げて恩田は説明しました。 同じこと母に問はるる半夏生 日下部宵三 亡き人の夫人に会ひぬ半夏生 岩田元子 いつまでも明るき野山半夏生 草間時彦
からすびしやくよ天帝に耳澄まし 大畑善昭
茅の輪 ありあまる黒髪くぐる茅の輪かな 川崎展宏 空青き方へとくぐる茅の輪かな 能村研三 雷 昇降機しづかに雷の夜を昇る 西東三鬼
遠雷や舞踏会場馬車集ふ 三島由紀夫
【後記】
今回の連衆の投句には、意図せず時候の半夏生になってしまっていた句が多かったと恩田は講評しました。そのうえで特選句と入選句について、「半夏生(植物)」を素直に丁寧に描写することで、それを見つめる自分の心のあり様を読者に伝えることが出来ていると評しました。
筆者の個人的見解ですが、恩田の出す「兼題」には、初学者が句作に頭を悩ますものが必ずと言っていいほど一つ含まれています。筆者にとっては今回であれば「半夏生(植物)」であり、次回では「甘酒」がそれに当たりました。それらはこの半世紀ほどで急速に身の回りから消えつつある環境であったり生活文化であったりするものです。筆者は東京近県の郊外に住んでいますが、こうした自然環境や文化的蓄積の残る静岡に羨望を禁じ得ません。
今回、連衆の投句から筆者が学んだのは、自分の感情や意識を殊更書こうとしなくても、対象をしっかりと描写することで読む者の共感を呼び起こすことができるということです。筆者の場合、「われ」と「季物」のうち「われ」が前に出過ぎているため、感覚的に描写しやすい「半夏生(時候)」の句になってしまっていたようです。
以前の樸俳句会で、芭蕉の言葉についてテキストを用いて恩田が解説するシリーズがありました。
「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中(うち)にいひとむべし」
「松のことは松に習へ、竹のことは竹に習へ」(いずれも「三冊子」)
初学者にとって、兼題に真正面から取り組むことが俳句の面白さを知る王道なのだと痛感した句会でした。筆者はずっとリモート投句が続いていますが、実際に句会に出られればさらに多くの薫陶と刺激を恩田と連衆から得られるのにと思う日々です。
(島田 淳) 今回は、特選3句、入選4句、△7句、ゝ11句、・7句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
============================ 7月28日 樸俳句会 入選句を紹介します。
○入選
向日葵や強情は隔世遺伝
海野二美
【恩田侑布子評】
向日葵のように明るく美しく、すっくりとお日様に向かって立っている作者。でも強情っぱりなの。この一本気は大好きだったおじいちゃん(あるいはおばあちゃん)譲りよ。へなへななんかしないわ。「隔世遺伝」という難しい四字熟語が盤石の安定感で結句に座っています。十七音詩があざやかな自画像になった勁さ。
【原】ドロシーの銀の靴音聞く夏野
山田とも恵 【恩田侑布子評】
「夏野」の兼題から「オズの魔法使い」を思った作者の想像力に感服します! 主人公の少女ドロシーは、カンザスから竜巻で愛犬のトトと飛ばされます。私も幼少時、大好きな童話でした。ブリキのきこりに藁の案山子、臆病なライオンとのちょっと知恵不足のあたたかい善意の支え合い。エメラルドの都へのあこがれと、故郷カンザスへの郷愁。それら一切合財を「銀の靴」に象徴させた作者の詩魂は非凡です。ただし、表現上は「靴音聞く」が惜しい。「靴音」といった時点で、俳句に音は聞こえています。 【改】ドロシーの銀の靴音大夏野 または 【改】ドロシーの銀の靴ゆく夏野かな など、「聞く」を消した案はいろいろと考えられましょう。
【原】いつからか夏野となりし田は静か
望月克郎
【恩田侑布子評】
地方都市の郊外のあちこちでみられる憂うべき光景です。無駄のない措辞に、本質だけを剔抉してくる素直な眼力が窺えます。それをいっそう際立たせるには、 【改】いつからか夏野となりし田しづか 字足らずが効果を上げることもあります。

天心への旅
――恩田侑布子「天心」を読む――
田村千春
旅に出ると時間の流れ方が違う。一分一秒が濃い。美しい景色をいそがしく胸に刻み込みながら、これまでの軌跡を振り返ったりもする。もしかしたら自分と向き合うために、人は初めての地を訪れようとするのかもしれない。
俳句が詠めるまでの試行錯誤は、そうした旅と似ている。樸の会に入って、この喜びと出会った。兼題がホワイトボードに書き出されると、心ときめく。これは次の句会のテーマを指し、たいてい季語が選ばれる。新たな旅のパートナーと呼べるだろう。その日を迎え、兼題にまつわる各々の体験が披露される。選句をし、解釈を述べる。俳句を「読む」とは、「あなたはどんな旅をしてきたのですか」とたずねる行為にほかならない。
今回、とっておきの旅を紹介したい。樸の会の指導者である恩田侑布子の「天心」――角川「俳句」2021年四月号に掲載され、樸の会では四月の句会において取り上げられた。その二十一句から、まずは「山茶花」と「寒牡丹」の冬の二句を。
植物の句は難しい。取り合わせで作れば、ともすれば季語が動く。一物仕立てでは季語の説明に陥りがちに。それに対し、おそらく誰にも真似できない方法で挑んでいる。対象に入り込み、自分と同化させるという――鮮やかな仕上がりに、思わず息をのむ。 山茶花や天の真名井へ散りやまず
「真名井」は古事記にも記載のある聖なる井戸のことで、「天の真名井」とは最高位の呼称。神々の水を賜った湧水として、高千穂や米子市高井谷のものが有名だ。遠州森町にもあるらしい。なぜか私には月光にきらめく流れが浮かび、実景か幻想かはどちらともつかない。山茶花の樹間より瀬音がこぼれている。おもむろに水面に歩み寄る作者。我が身を投影させるうち、意識はいつしか水の循環へ。すべての雫がまばゆい光となる。神の恩寵に感謝し、「山茶花」は豊かに湧き出る水のように、惜しみなく花びらを散らす。 身のうちに炎(ほむら)立つこゑ寒牡丹 冬の牡丹には二種類ある。春咲き品種を温室などを利用して「春が来た」と勘違いさせ咲かせているものと、春だけでなく初冬にも咲く「二季咲き」という性質を持ち合わせているもの。後者が「寒牡丹」で、冬とわかっていながら健気に花をつける。作者の身のうちの炎、葉を捨ててまで寒牡丹がからくも灯す炎、この二つを繋ぐのが「こゑ」。炎を詠み上げるのに色、揺らめき、温度、匂いを題材にするのはしばしば見かけるが、聴覚に訴えるとは――作者が炎そのものとなっている証といえよう。寒牡丹の背後に雪が見える。吹き荒ぶ雪風へ、作者の眼差しも凛として向けられ、少しもたじろがない。
「山茶花」の句が一句目、そして「寒牡丹」の句で、冬は終りを告げる。では、つづいて春の旅へ。例えば、次の一句はいかが。 花の雲あの世の人ともやひつゝ 「舫う」(舫ふ)とは「もやい」で船を他の船や杭とつなぐこと。「もやい」とはそのための綱である。強固につなぎ留められているようでいて、波に弄ばれ心許ない。まして此岸と彼岸、それぞれに浮かぶ魂を、茫漠たる境界をゆく道連れにさせようというのだ。切ない、しかし何とも美しい旅路への誘い。誰もがつい引かれてしまうのではないだろうか。今、作者はその境界――「花の雲」に身を任せたままでいたいと、ぼんやり願っている。永遠に慕い続ける相手と共有する、羊水の如くほのあたたかい空間。 天心のふかさなりけり松の芯 晩春の松の芽は蠟燭のような姿で、「松の芯」として俳人たちに愛されてきた。「若緑」という季語も、松の新芽や若葉を色で表現したものである。まさに生命の色。松の芯を志に見立てる句など、清新な気配に充ちた例句がならぶ。しかし、するりとそこに入り込み空を仰いだ作品というと類をみない。小さな若芽は天心の深さに打たれつつ、よろこびに震えている。
思えば壮大な旅は、真名井の聖なる水より始まった。その一滴から木の道管を経て花弁へ、雪へ、炎へ――自在に姿を変えてきた作者が、ついに天に至った瞬間。ここでは六句のみの紹介にとどめるが、「天心」は全句が前に述べた独自の方法に則る、記念碑的作品だ。舞台は限りなく広く、この世ならぬ場所にも及ぶ。桜の繚乱に彼岸の人との交信を果たした作者は、命のもつ哀しみや美しさと常に向き合う道を選んだのだろう。特筆すべきは、考え抜かれた並びであること。それによって生命の根源が水にあると、あらためて気づかせる仕掛けである。最後に置かれたのは、次の一句。 山藤の帰途なき空を揺らしては どうやらこの旅は終わらないらしい。道なき道をたよりなく進む。「山藤」は庭の藤よりも香りが強く、他の木々に巻き付き、びっしりと花房を垂らし、隙間に見え隠れする空までも昏ませる。猛々しいほどの美しい紫に囲まれているが、これもまた水から生まれたものである。もしここで果ててしまうとしても、出発点に帰るだけ。幽玄の美に抱かれながら、輪廻に取り込まれる幸せを甘受すべきかもしれない。恩田侑布子という無二の師により導かれる俳句の旅も、どうか永遠であれ。
いつもの句会に向かうとき、駿府城のお堀に沿った道を歩くのが好きだ。いかにも静岡らしい道、ことに富士山が見えれば、古の人々とも気持ちが通い合う気がする。何にもまさる日本人の心の拠り所であろう。そこで「天心」の唯一の新年の季語を扱った句を掲げ、拙稿の締めとしようと思う。「初富士」がはらう雪は、作者自身が身にまとっていた雪でもある。 初富士や大空に雪はらひつゝ
(たむらちはる 樸会員・樸編集委員) ※ 恩田侑布子「天心」21句はこちらからどうぞ

2021年6月6日 樸句会報【第105号】
今朝は梅雨が戻ったような空模様。
でも句会が始まるころには小降りとなる。
そんな中うれしいことに、御二人の見学者がおみえになる。五月にお仲間になった御二人と、樸に新しい風を吹き込んでくれそう。
本日は新人の方が多いので、副教材はお休みし、投句の選評、それも高得点からではなく、無点句から始まりました。 兼題は「雪の下」「蝸牛(でで虫)」「青嵐」です。
入選1句、原石賞1句、△4句を紹介します。
○入選
おんぶ紐要らなさうだね雪の下
田村千春 【恩田侑布子評】 「雪の下」の兼題からおんぶ紐を発想した詩的飛躍が非凡です。梅雨時の雪の下という植物の、日影っぽい静かさ。我が家の背戸にも竹山との境の低い石垣に雪の下が生えています。春先は天ぷらにしておいしい繊毛の密生した葉は、梅雨時になると赤紫の茎を伸ばし、鴨の足のようなちぐはぐな細い白い花びらを傾きがちに咲かせます。おんぶ紐は赤ん坊には必需品だが、使う時期は短いもの。捨てるに惜しく、そうかといって取っておいても使い道はありません。わずか一年ほどの母子密着の乳児期のやるせなさと懐かしさ、そして瞬く間に大きくなってゆく幼年時代との別れがしみじみとした抒情を醸します。目の前の子や孫を育てる日常生活を超えて、人の世に昔から繰り返されてきた子育てという懐かしくもはかないいとなみの感触が存分に描かれています。山の端に滲む薄墨がかった梅雨夕焼を見るような、不思議な味があります。
ただ、口語の面白さの半面、「だね」は雪の下の仄かさを打ち消さないでしょうか。
「おんぶ紐もう要らなさう雪の下」なら◎特選と考えてそう言うと、作者がまさにこの通りの句を考えて、その後「だね」に推敲してしまったとおっしゃいました。
【原】擂粉木に胡麻うめきたる暑さかな
古田秀 【恩田侑布子評】 日常の中から詩をみつけた良さ。ごまをするときの実感があります。ただ「うめきたる」は「呻きたる」で、声が聞こえて、しつこすぎませんか。即物的に、たくさんあるという意味の「擂粉木に胡麻うごめける暑さかな」なら◯です。 【改】擂粉木に胡麻うごめける暑さかな
【合評】 感覚的な句。暑さを伝えるのに「胡麻のうめき」ととらえたのがなかなかいい。
△ 繰り返し傷舐める犬夏の闇
萩倉 誠 【恩田侑布子評】 犬は傷を舐めてなおす。静かだと思ったらまた舐めている。犬にしかわからない傷の痛みがあるのだろう。内容はいい。弱点は、犬小屋なのか、座敷犬が電気を消した部屋の隅で舐めているのか、場所が特定できず、映像が浮かびにくいのが惜しい。
【合評】 読んだ瞬間、怖いと思った。野良犬が路地裏で傷を舐めている。そこを作者が通りかかった。
飼犬が釘かなにかでけがをし、それを舐めている。
△ でで虫や己が身幅に道を食み
島田 淳 【恩田侑布子評】 「身幅に道をはむ」に素晴らしい詩の発見があります。頭の作ではなく、現場にいて蝸牛と会っている人の作品です。さらに調べをととのえて、
「かたつむり身幅に道を食みゆくも」
なら◯です。
【合評】 「身の丈にあった」はよくきくが、「身の幅に食んでいく」といっているのがおもしろい。
△ 月食のかげにさざめく雪の下
前島裕子 【恩田侑布子評】 感性のすばらしい作品です。リズムを考慮し、
「ささめける月蝕のかげ雪の下」なら、さらに◯入選です。
【合評】 月蝕(5月26日)はみていた。雪の下は知らなかったが調べてみて、葉の緑が「さざめく」と合っているよう。
△ 坪庭の暮れて仄かに雪の下
海野二美 【恩田侑布子評】 正攻法の「雪の下」の句。映像がはっきりと浮かぶ。陰翳ゆたかな品の良い坪庭が眼前する。「仄かに」はいかにも雪の下らしい。 本日の兼題の「青嵐」「かたつむり」「雪の下」の例句が恩田によって板書されました。
雪の下 歳月やはびこるものに鴨足草 安住敦
低く咲く雪の下にも風ある日 星野椿 蝸牛 かたつむり甲斐も信濃も雨のなか 飯田龍太
かたつむりつるめば肉の食ひ入るや 永田耕衣 かたつぶり角ふりわけよ須磨明石 芭蕉
でゞむしにをり/\松の雫かな 久保田万太郎 青嵐 猫ありく八ツ手の下も青あらし 前田普羅
面・籠手の中に少年青嵐 中尾寿美子
選句に入るまえに恩田より、特に初心者の方へ選句の仕方について次のようなコメントがありました。
・俳句は水準で選ぶのが大事
・好ききらいで選ばないこと
・そうした選句を重ねてゆくと句作も良くなってゆく
つぎに、選評。いつもと違い無点句からで、
・どこを直せばよくなるか
・どうすればいい句になるか
・本題季語で詠んだほうが句が広がる
・擬人化は詩的飛躍がないと卑俗になりがち
・奇をてらうよりは平凡の方がいい
・俳句という詩を詠む
・<平明で深い句>…高浜虚子のことば
と、一句一句丁寧に指導いただきました。
【恩田より総論の感想として】 ・季語には本題がありますが、滅多に使われない珍しい傍題季語を使う句がこのごろよく目立ちます。絶対に悪いわけではありませんが、本題季語のほうが共感しやすく、連想もひろがるものです。
・突飛なことばや思いつき、鬼面人を驚かす語を使ってカッコつけたくなるのは初心者の弊です。気をつけましょう。
・上に関連しますが、田舎歌舞伎で大見得を切っているような、そこだけ悪目立ちするような力みかえったことばの使い方には気をつけましょう。
【後記】
本日は、新しい仲間も加わり、いつもに増して熱の入った句会でした。
無点句から始まった選評も一句一句、かみしめ聞き入りました。
そして本題季語で詠むことの大切さを知り改めて、季語と向きあってみようと思いました。
選句についても、「好みではなく俳句の水準で選ぶ」ことを肝に銘じたいと思いました。 コロナのワクチン接種が始まりました。
これで収束に向かい、みんながリアル句会に参加できますように。
(前島裕子)
今回は、入選1句、原石賞1句、△4句、ゝシルシ14句、・2句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
============================
6月23日 樸俳句会 入選句を紹介します。 ○入選
鉄板の足場ひびけり梅雨夕焼
塩谷ひろの 【恩田侑布子評】 建設現場の鉄骨に渡した鉄板の足場でしょう。しかもこれは二階や三階ではなく、かなりの高層建築を思わせます。そこに梅雨夕焼を鉄板と同時に踏んでいるかの空中感覚と、黒ずんだ夕焼けが響き返してくる臨場感があります。油断すれば転落する厳しい建設現場の仕事です。緊張感と、まだ仕事の終わらない一抹の淋しさ、孤独感。都会のブルーワーカー同士、声を掛け合ういたわりも想像されます。視覚や聴覚にダイレクトに迫る訴求力が素晴らしい。労働俳句のソリッドさが梅雨夕焼に合っています。作者が初投句の塩谷ひろのさんと知って、びっくり仰天いたしました。
○入選
照りかへす一円玉や夏燕
古田秀 【恩田侑布子評】 道路にきらっと白くひかるのは一円玉。誰も拾わない一円玉。夏つばめが急降下して地面すれすれに腹を擦り付けたかと思うや、あっという間に青空に吸い込まれる。その早さ、切れ味のよさ。なにもいわず、ただ一円玉と夏燕の詩が展開する空間の気持ちよさ。

2021年1月10日 樸句会報【第100号】
樸代表 恩田侑布子 第100号記念祝詞
このたびの初句会が樸句会報の100号記念になるとのこと、慶賀に存じます。これも連衆のみなさまの熱意のたまものです。心から感謝しおん礼申し上げます。
樸は一人ひとりが真剣に、「リアル・オンライン融合句会」の全俳句を選句し、口角泡を飛ばして合評し、笑い合う楽しい句会です。そこにぱらぱら振られる恩田のカプサイシンが心地よい緊張感をもたらすことを庶幾しております。もちろんコロナ禍とあって、だだっぴろい部屋には三方向から風が吹き込み、美男美女があたらマスクをしております。が、そこからはみだす頬のかがやかきは隠しようもございません。三時間余の句会を、「生きがいです」とも「ボケ防止です」とも言ってくださる連衆のイキイキした俳句に私自身が毎回励まされております。三役と編集委員のみなさまのたゆまぬご支援にもつねづね頭が下がります。
そうと教えられるまで夢にも知らなかった第100号記念、本当にありがとうございます。これからも一人ひとりの目標に向かって、互いに温かく見守りあい切磋琢磨して、一句でもいい俳句をつくってまいりましょう。
2021年の初句会は、新型コロナウイルス感染再拡大の影響もありネット句会となりましたが、新年に相応しい力作が寄せられました。 兼題は「初雀(初鴉、初鶏)」「去年今年」です。 特選1句、入選1句、原石賞6句を紹介します。 ◎ 特選
ししむらを水の貫く淑気かな
古田秀 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記(淑気)をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
初鴉燦々とくろ零しゆく
田村千春 【恩田侑布子評】
元日の淑気のなかをゆく鴉の濡れ羽色がきわやかです。黒い色はひかりを吸いますからふつうは「燦々と」は感じられません。ところがこの句では、「燦々と」にたしかな手応えがあります。「初鴉」を句頭に置き、「くろ」をひらがなにしたことでしなやかな羽根の動きが眼前し、「零しゆく」で、青空に散る水滴が墨痕淋漓としたたるのです。みどりの黒髪ならぬぬばたまの羽の躍動は斬新です。一句一章の句姿も新年のはりつめた空気さながら。
【原】終電ののちの風の音去年今年
猪狩みき
【恩田侑布子評】
終電の通り過ぎたあとの風に去年今年を感じるとは、まさにコロナ・パンデミックに襲われた昨年をふりかえる二〇二一年ならではの新年詠です。ただ「カゼノネ」という訓みかたはクルしくないですか。
【改】終電ののちの風音去年今年
あるいは都会の無機質な風の質感に迫って
【改】終電ののちのビル風去年今年
などにされると、コロナ禍に吹きすさぶ深夜の風がいっそうリアルに感じられるでしょう。
【合評】 終電を降り人がほとんどいないホームに立つと、私はまず「こんなこといつまで続けるんだろう」と思い、次に「今日はやり切った。そして続けるしかない」と気持ちを切り替え、さらに移動し始めます。気持ちの境目と去年・今年の境目という二重構造になっている点が優れていると思います。
終電を降りて深夜の家路を急いでいます。すでに年は改まりました。自分ではよく働き、よく生きてきたと思う…。耳元で風が囁きます。「あゝ、おまへはなにをして来たのだと…」(by中也)。作者の心情がよく伝わってくる句だと思いました。
コロナ禍で深夜の初詣も自粛。終電も早くなったことのむなしさと淋しさが後の風に良く響く。さりげない一句に、例年にない年明けの哀感が滲み出ている。
【原】胸に棲む獅子揺り起こす去年今年
金森三夢 【恩田侑布子評】
力強い新年の詠草です。ただ終止形の「す」だと一回きりの感じがしてもったいないです。「去年今年」の季語ですから、いくたびも揺りおこしつつという句にしたいです。そこで、
【改】胸に棲む獅子揺り起こし去年今年 一字の違いで秀句になります。
【合評】 作者の内にある獅子を起こす。今年の意気込みを感じる。
【原】今年こそ麒麟出でよと富士映ゆる
金森三夢 【恩田侑布子評】
ご存知のように中国の古典では麒麟は聖人がこの世に現れると出現するといわれ、才知の非常にすぐれた子どものことを麒麟児といいます。郷土の誇り富士山に、気宇壮大な幻想を力強くかぶせたところがすばらしい。惜しいのは最後の「映ゆる」。「麒麟出でよ」と富士山が身を乗り出しているようで俗に流れます。ここは作者自身の肚にどーんと引き受けたいところ。
【改】今年こそ麒麟出でよと富士仰ぐ 格調のある特選句◎になります。座五は大事。俳句の死命を制します。
【原】干涸びし甲虫の落つ煤払い
島田 淳 【恩田侑布子評】
「煤払い」のさなかに貴重な体験をしました。いえ、俳句の眼がはたらいていたからこそ、この瞬間を見逃さなかったのでしょう。「夏のカナブンがその姿を止めていた」と作者はコメントしています。その感動にたいして「落つ」はもったいない。正直なたんなる報告句になってしまいます。
【改】干凅びし甲虫と会ふ煤はらひ 詩的ドラマが生まれます。
【原】初雀しばし「じいじ」に浸りおり
萩倉 誠 まだ幼い孫におじいちゃんおじいちゃんと慕われ、まといつかれる作者。「初雀」と「じいじ」の取り合わせがなかなかです。そのぶん「浸りをり」でいわゆる「孫俳句」に転落しかかったのが惜しいです。 「孫が逗留中。「じいじ」「じいじ」の大洪水。溺死しそうな毎日が続く」の作者コメントを生かし、こんな案を考えてみました。
【改】初雀「じいじ」コールに溺死せり
浸るのではなく溺死。俳味を得ればもう「孫俳句」とはいわせません。
【原】レジとづれば大息つきぬ去年今年
益田隆久 【恩田侑布子評】
コロナ禍の日本で、いえ世界中の小売店でどれほどこのような光景が日々繰り返された去年今年であったことでしょう。「大息つきぬ」に理屈抜きの実感があります。ただ「レジとづれば」の字余りの已然形はいかがでしょうか。「…するときはいつも」は現実に忠実かもしれませんが俳句表現としては弛みます。ここはレジを閉じる一瞬に焦点を当て定形で調べを引き締めたいです。
【改】レジ閉ぢて大息つきぬ去年今年 これならすぐれた時代詠の入選句◯になります。
【合評】 年中無休が当たり前のようになった現代の小売業。サントムーンもららぽーとも大晦日元日関係ないかのように営業していました。掲句はずっと小規模な商店かもしれませんが、大晦日も営業していたのでしょう。「大息」に実感があり、レジを閉じる音とともに年が変わってしまったような錯覚が生きています。ああもう今年は「去年」に、来年は「今年」になってしまった… [後記]
新年詠に際して連衆のそれぞれの思いを一部抜粋してみました。 昨年の初句会で恩田代表から、新年の季題は明るく、めでたしが良しと伺った。それを基に作句・選句しました。
「去年今年」が平べったく「去年と今年」「去年から今年」となってしまいとても難しい季語だと思いました。新年の明るさや喜びの句が少なかったのはやはりコロナ禍のせいでしょうか。
たった一語の違いで、つまらない句が活き活きと動き出すおもしろさ。日本語の素晴らしさ。
年始の慶びを実感できない、表現しづらい社会状況だった。きっといまの時代にしか作れない俳句があると思うので、喧騒ややるせなさを逆手にとって、したたかに頑張っていきましょう。
俳句という器のサイズと、季の中に私自身を往還させることの大切さを改めて認識出来ました。季語ともっと親しくなるために、机の上で作句するだけでなく、自然環境に身を置く事を大切にする一年としたい。
緊急事態宣言が再発令され、なかなかコロナ収束が見通せない年初です。
句座をフルメンバーで囲める日の来ることを心より願います。思う存分口角泡を飛ばしたい筆者です。 (山本正幸) 今回は、◎特選1句、○入選1句、原石賞6句、△4句、ゝシルシ9句、・5句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
===================== 1月27日 樸俳句会 特選句と入選句を紹介します。
◎ 特選
レコードのざらつき微か霜の夜
萩倉 誠 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記(霜夜)をご覧ください。
↑
クリックしてください
○入選
風花舞へり六尺の額紙
萩倉 誠 【恩田侑布子評】
「額紙」は「葬式のときに棺を担いだり位牌を持ったりする血縁者が額につける三角形の紙」と、辞書にあります。私の経験したお葬式にはそうした風習はなく、初めて知った言葉です。知ってみるとなかなか迫力のある光景です。
六尺の大男の額に三角の白紙がひらひらして、そこに風花が舞うとは、きっと喪主なのでしょう。悲しみに寡黙に耐えて白木の仮位牌を胸に抱き出棺の儀式に歩むその瞬間でしょう。句またがりのリズムが効果的。
作者がわかってお聞きすると、御殿場市の田舎では1950年代まで土葬だったそうです。棺を担ぐ男たちを「六尺」といって、みな白い三角の額紙をつけて土葬の野辺まで歩いたそうです。帰りには浜降りといって、黄瀬川や千本松原で仮位牌に石をぶつけて流したそうです。日本の古い送葬の儀式の最後の証言ともいうべき大変貴重な俳句です。
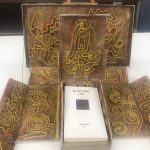
「無音の滝」 ―芹沢銈介美術館を訪ねて― 田村千春 人は美に憧れ、芸術に触れたいと欲する動物です。時には感動を大勢で分かち合い、明日への活力に変えてきました。まさか新型コロナの蔓延を防ぐため、そうした欲求にまで制限がかかる事態となるとは、誰が予想したでしょう。それ以前に俳句という、限られた条件の下、美を見出す極意そのものに出会えていて、つくづく幸運だったと思います。
今、私の手に静岡市立芹沢銈介美術館からのリーフレットが。「日本のかたち」と銘打ち、芹沢の収集した膨大な工芸品の中から日本の絵馬、玩具、やきもの、漆器、木工、家具、染織品等250点を特集し、2021年3月21日まで展示するとの知らせです。こちらを睨んでいるのは「かまど面」の写真――目は真ん丸、胡坐をかいた鼻、きっと結んだ口、異様なインパクト。かまど面とは何? 調べたところ、家を守る神様を土や木でかたどり、竈近くの柱に祀るという風習が東北地方でみられたようです。初めて見たのに懐かしく感じるのは、頑固親父を連想するからかもしれません。
芹沢銈介といえば、紅型の技術をきわめた、親しみやすくも先進的な作風で知られる染色家。世界の工芸品の収集家としても有名です。素朴な土色のお面を好んだとは意外な気がし、興味をそそられました。これは行ってみなければ。なにしろ月に一度は「一人吟行」に出掛けている私です。
いよいよ2020年12月、車で出発。まず登呂公園にあるという立地の良さ。博物館には弥生時代の住居も復元されていて、機織りなど当時の暮らしぶりもしのべます。そこから脈々と受け継がれる名工の系譜に思いを馳せながら、美術館へ。
特筆すべきは白井晟一の設計した建物――「石水館」の名にふさわしく、自然を生かし精神性を重視した造りは、威容を誇るビルディングとは対極にあります。驚いたことに外からは全容が知れないのです。この不思議をぜひとも体験し、館内をめぐる際には指定された品の県名を書き込むクイズにも挑戦してみてください。出来上がった用紙と引き換えに、芹沢による型染の富士山の葉書をいただけます。
着物や漆絵の色彩の妙、木箱や酒樽の洗練ぶり、かまど面の凄まじいまでの表情。これらに囲まれ、潤いある生活を送ってきたのだと気づかされます。芹沢の物を見る目は温かく、誰よりも確かでした。
この慧眼が彼の美の礎となったのでしょう。芹沢自身の作品も60点、どれも明快にして親しみ深いものばかり。紅型のスタッカートが効いており、時代を超え、世界中の人々を元気にするに違いありません。例えば、屏風の考え抜かれたレタリング――「春夏秋冬」――なんと愛らしいこと、あたかもバレエを観るよう。それぞれ羽をすぼませたり、アラセゴンに広げてみせたり。
自然と一体化して産み出された作品には、明るさの中に何とも言えない静けさがあります。例えば1962年作の「御滝図のれん」。生きている滝に胸を打たれ、能狂言に通じる抑制された美にしばし見惚れました。1948年には既にアイディアがあったらしく、制作に取り掛かるのに長い年月を要し、さらに芹沢邸の訪問客で、図案がどんどん変わっていく様を目撃した方もいたのだとか。時間をとことんかけ、人の反応も参考にしながら完璧を求めるとは、謙虚な姿勢に頭が下がります。伝えられる「自分というものなどは、品物のかげにかくれてしまうような仕事をしたい」との言葉にも考えさせられました。これは無我の境地に至った作家だからこそ口にできるのではないでしょうか。幾多の線より正解を選び取れる芹沢でなければ、一条の滝に命を吹き込むという偉業は成し遂げられなかったのですから。
清新なる世界へといざなう暖簾からは、片時も離れたくなくなります。出口に近い特別室と展示室とを、何遍も行ったり来たりしてしまいました。特別室からは硝子越しに坪庭を眺められます。その坪庭は、まさに白井晟一の手による一幅の絵。枝垂梅が一身に日射しを浴び、何だかあたたかそう。身に余る体験をさせていただいた一日を振り返って、一句。
坪庭の枝におもたき冬日かな 住宅街を駐車場へ向かう途中、何軒も芹沢の暖簾を掛けているのを垣間見ました。愛される人間国宝、今も自らの願いを存分に叶えています。日々なにげなく使う品物に愛情を注ぎ、精魂込めてくれた芸術家がいたことに、心から感謝を。コロナ禍で舞台芸術などの開催が難しくなっても、無限の美を手に入れるための鍵ならば、ここに残されていると確信しました。 (たむらちはる 樸俳句会員)
静岡市立芹沢銈介美術館のホームページはこちらです
↑
クリックしてください

令和2年10月21日 樸句会報【第97号】
秋晴の午後、十月2回目の句会がもたれました。久しぶりに神奈川県から参加した連衆もありおおいに盛り上がりました。
兼題は「鵙」「野菊」です。
入選2句、原石賞1句を紹介します。 ○入選
熱気球ゆさり野菊へ着地せり
村松なつを
地上から見上げて居た秋天の熱気球は点のようだったのに、高度を下げはじめるや、みるみる大きくなり、「ゆさり」と野菊の咲く原っぱに着地した。熱気球の篭の大きさとそこに乗っている人の重みの実感が「ゆさり」というオノマトペに見事に籠もっています。野菊の白さと、細やかな花弁のうつくしさ、気球の渡ってきた秋空の美しさが充分に想像でき、映像として迫ってくる空気感ある秋の俳句です。
(恩田侑布子)
【合評】 秋の空の美しさと地面に咲く野菊の様子が気持ちよく浮かんでくる。
私なら野菊を花野で詠んでしまいそうですが、野菊としたことで、秋の野原の中の、野菊が咲いている一点をクローズアップ出来ています。「熱気球ゆさり」という措辞も面白い。
熱気球は、風を読む力とバーナーの熱の調節だけで操縦するため、思い通りの場所に着地するのはとても難しい。この気球のパイロットも、意図せずに野菊の上に着陸してしまったのかも知れない。「ゆさり」というオノマトペが、熱気球の巨大さと、偶然かつ静かな着地を表現している。
野菊を詠った句の中で、新しい切り口だと思います。
気球と野菊、空と地、大と小の対比を「ゆさり」のオノマトペでつないだ良い句。
野菊でなくてもいいのでは?
秋の澄んだ空が見えてきます。
「野菊に(•)」としたらどうなのでしょう? ← この質問に対して恩田は「ここは<野菊へ(•)>でなくてはいけません。方向と動きが出るのです。<へ>という助詞は使い方が難しいけれど、この句は成功しています」と解説しました。
○入選
クレジツト払ひの火葬もず日和
村松なつを
「クレジット払ひの火葬鵙日和」の表記のほうがカチッとします。なんでも電子決済になってゆく世の中。とうとう葬儀費用どころか火葬場の支払いまでクレジットカードになった。清潔この上ないつるつるの床の火葬場。無臭で、どこにも人間の体温の気配すらしません。谷崎の陰翳礼讃の日本はどこにかき消えたのでしょう。死者を送る斎場からも一切の陰影が拭われてしまいました。現代の葬儀と、死者をとむらう意味を現代人に問いかけてくる怖ろしい俳句です。
(恩田侑布子)
【合評】 葬儀だけではなく、体と気持ちを寄せ合う機会が急速に減っていることの意味を問う俳句です。
句の現代性がまず良いと思いました。日々の生活の中での新しい視点。クレジットにするとポイントがつきます。人の死に対してポイント? ギャップがあり、恐れ多いことかもしれませんが、そこを繋げる面白さがあります。季語が落ち着かない秋の空気感を表していると思います。
現代を象徴していて、俳味が感じられます。
「もず日和」のイメージと合わないのでは?
火葬料は役所に払うわけですからたぶんクレジット払いはできない。ここは葬儀代ではないのですか?(作者によれば、掲句はじつは飼犬の火葬場を詠んだもので、クレジットカード払いができたとのことです)
【原】ラ・フランス友の名字がまた変はり
田村千春
再婚し、こんどまた三度目の結婚をした友達でしょうか。
おしゃれな味ながらどこか腐臭の美味しさを楽しむラ・フランスに、その女性の人物像が髣髴としてくる面白い俳句です。一字のちがいですが、
【改】ラ・フランス友の名字はまた変はり
こうすると調べが軽快になるとともに果物と友のノンシャランな雰囲気も出てきます。
(恩田侑布子)
【合評】 ラ・フランスは、季節にならないと意識に上らない果物。この友人との関係も、引っ越しの挨拶や年賀状のやり取りが中心の距離感なのかも知れません。座五には、経緯のわからない軽い驚きと、ラ・フランスのように人生を追熟して幸せを掴んでほしいという祈りが込められているようです。
取り合わせの意外さに思わず採ってしまいました!また名字が変わるということは結婚と離婚をしたということなのでしょうが、ラ・フランスの効果なのか、私には再婚して名字が変わったように読めました。そして作者はそれを聞いて、あまりネガティブな感情を持っていないような気がしました。
離婚・再婚を繰り返している友なのでしょうか。ラ・フランスとの取り合わせのセンスがとてもいいと思いました。
本日の兼題の「鵙」「野菊」の例句が恩田によって板書されました。
野菊
頂上や殊に野菊の吹かれ居り
原 石鼎
秋天の下に野菊の花辨欠く
高浜虚子
夢みて老いて色塗れば野菊である
永田耕衣
けふといふはるかな一日野紺菊
恩田侑布子
鵙
たばしるや鵙叫喚す胸形変
石田波郷
百舌に顔切られて今日が始まるか
西東三鬼
はらわたのそのいくぶんは鵙の贄
恩田侑布子
(冬季)
冬鵙を引き摺るまでに澄む情事
攝津幸彦
合評に入る前に、芭蕉『鹿島詣』を読み進めました。本日は美文調の擬古文のくだりです。
芭蕉一行は、「句なくばすぐべからず」(句を詠まなければとても通りすぎられない)ほど畏敬する筑波山を見たあと、鹿島への渡船場のあるふさ(布佐)に着く。その地の漁家にて休み、月が隈なく晴れるなかを夜舟で鹿島に至った。
芭蕉は鹿島に「月見」に行ったというのが通説だが、単に月見に行こうしたのではないのではないか。芭蕉の故郷の伊賀から見れば常陸の国はまさに「日出づる処」である。月が昇る三笠山を光背としている春日大社。春日曼荼羅には神鹿(鹿島からはるばるやってきた鹿)が描かれていて、鹿島神宮と春日大社は深い関係にある。芭蕉には、日本人の文化の古層に迫りたいという気持ちがあったのではないかと思う。芭蕉は近世の人だが、ここの文章は中世・平安に近い感じがします。以上、恩田からユニークな解説がありました。
今回の句会のサブテキストとして、「WEP俳句通信」118最新号の「珠玉の七句」欄の井上弘美さんと恩田侑布子の秋の俳句を読みました。
次の句が連衆の共感を集めました。
汽水湖をうしなふ釣瓶落しかな
井上弘美
歳月は褶曲なせり夕ひぐらし
恩田侑布子
[後記]
本日の句評の中で恩田から「<故郷の>は感傷的になりやすい措辞なのでみだりに使わないほうがいいです。叙情・情趣と、感傷との違いを峻別しましょう」との指摘がありました。
これを「lyrical」と「sentimental」と(勝手に)言い換えてみて実に納得できた筆者です。なるほど「センチメンタルジャーニー」はあっても「リリカルジャーニー」はあまり聞かないよなあ、と独りごちました。
句会が果て、投句をめぐる熱い議論をアタマの中で反芻しつつJR静岡駅へ向いました。駿府城公園の金木犀の香にうたれながら。
(山本正幸)
次回の兼題は「そぞろ寒」「刈田」です。
今回は、〇入選2句、原石賞1句、△9句、✓シルシ9句、・4句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

令和2年8月2日 樸句会報【第95号】
Withコロナの時代、リアル句会が復活して4回目です。県外の連衆は来館制限されているため少人数でしたが熱い議論となりました。
兼題は、「髪洗ふ」と「裸」です。 ◎特選1句、○入選2句、原石賞1句を紹介します。 ◎ 特選
ラ・クンパルシータ洗ひ髪ごとさらはれて
田村千春 特選句についての恩田の鑑賞はあらき歳時記に掲載しています
↑
クリックしてください
○入選
立ち漕ぎの踵炎昼踏み抜きぬ
山田とも恵 自転車で出発。思わず立ち漕ぎをして急ぎます。心が逸り、炎昼も汗も眼中にはありません。私はそこに行く。まっしぐらに行くのです。もう、心は向こうにあるから。そのとき、です。炎天を踏み抜いた、底が抜けた!と思ったのです。映像を即物的に「立ち漕ぎの踵」に絞ったことが奏効しました。座五の「踏み抜きぬ」で、踵がリアルに異界に突き抜けた感じが出ています。
(恩田侑布子)
【合評】
暑さの激しさと立ち漕ぎで踏み抜くという動きの強さとがマッチしている。
○入選
裸子の羽あるやうに逃げまはる
前島裕子 ひとは赤ん坊から幼児期に移行するほんのひととき、肩甲骨のあたりに透明な羽をつけます。まだいちども強い日光にさらされていないやわらかな肌。ふくふくした手足のくびれ。その子をバスタオルを拡げて捕獲しようとする母の、なんというしあわせな一瞬。
(恩田侑布子)
【合評】
逃げまわっている子どもの動きが見えるよう。裸であることで楽しさが増すような。
子どもの貝殻骨はよく動く。その光景がよく見えます。
「羽あるやうに」がいいですね。幼児の肩甲骨は天使の羽に擬せられますから。
【原】裸子や目に羊水の波頭
見原万智子 おかあさんの胎内の羊水にただよう胎児を裸子とみた着眼にインパクトがあります。ただ「波頭」はどうでしょうか。強すぎませんか。推敲はいろいろ考えられますが、たとえば一例として次のようにすると、羊水と母なる海とがダブルイメージとなり、内容にふくらみがうまれそうです。 【改】はだか嬰よ目に羊水のしじら波
(恩田侑布子)
【合評】
羊水を海に喩えたのですね。精神分析の世界のようにも思えます。
「生まれたての赤ちゃんの目を覗き込んだら、羊水の波頭が見えた」という風に読みました。なんだか本当の波の音も近くで聞こえているような気もします。とても詩的な光景だと思います。羊水の波頭っていいなぁ…。
披講・合評に入る前に、恩田から本日の兼題の例句が板書されました。 裸
伸びる肉ちぢまる肉や稼ぐ裸 中村草田男
はだかではだかの子にたたかれてゐる 山頭火
海の闇はねかへしゐる裸かな 大木あまり
髪洗ふ
洗ひ髪身におぼえなき光ばかり 八田木枯
洗い髪裏の松山濃くなりぬ 鳴戸奈菜
髪洗ふいま宙返りする途中 恩田侑布子
風切羽放つごとくに髪洗ふ 恩田侑布子
サブテキストとして、恩田がSBS学苑で指導している「楽しい俳句」の会員の句(2020年5月1日静岡新聞掲載)を読みました。
連衆の共感を集めたのは以下の句でした。
春の雨知らぬ男の傘がある 美州萌春
歌がるた公達の恋宙を跳び 都築しづ子
春の雨窓に小さき鼻の跡 活洲みな子
鉄瓶の湯気やはらかし女正月 石原あゆみ
[後記]
やっぱりリアル句会に勝るものはないようです。合評における言葉のやりとり(ときに応酬)が次々に化学反応を起こし新しい世界が現出していく様は、まさに「句座を囲んでいる」ことを実感させるものでした。特に今回は身体に即した兼題でしたので、連衆の生活の一端が垣間見え、大いに盛り上がったのです。恩田も全体の講評の中で「選評にはおのずと異性観や恋愛観があらわれ、愉快な句会でした」と述べています。そうか、おのれの異性観・恋愛観を振り返る契機としての句会でもあったのだな…いやまだこれから異性観などを変えることができるのかもしれないなぁ…などと独りごちた筆者でした。 (山本正幸) 次回の兼題は「天の川」「門火(迎火、送火)」です。
今回は、◎特選1句、○入選2句、原石賞1句、△2句、ゝシルシ3句、・13句でした。
(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)
8月26日句会 入選句 兼題「天の川」・「門火(迎火、送火)」 ○入選
天の川みなもと辿る野営かな
金森三夢
それきりのをんな輪切りの檸檬かな
古田 秀
代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。